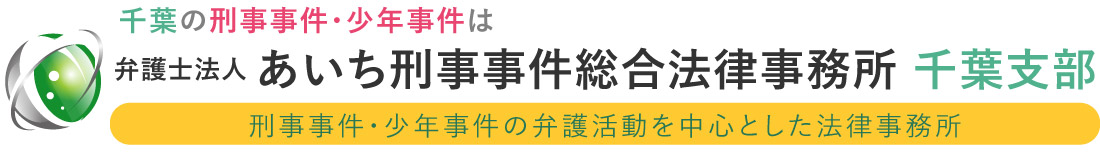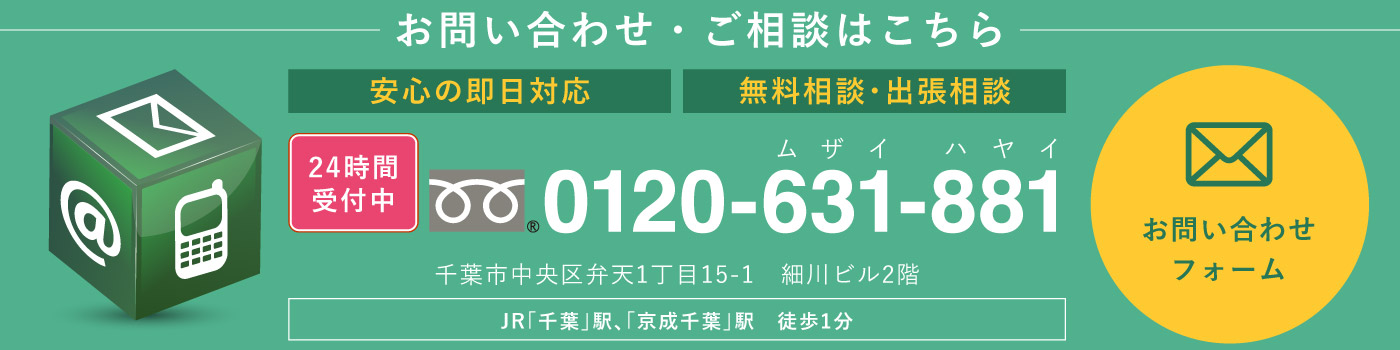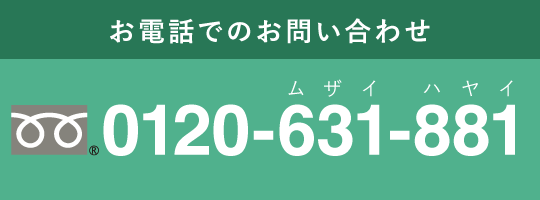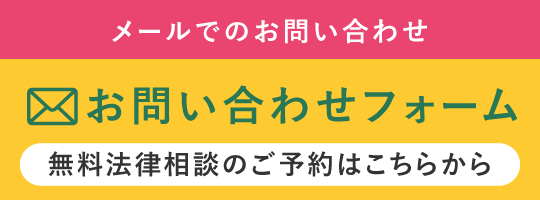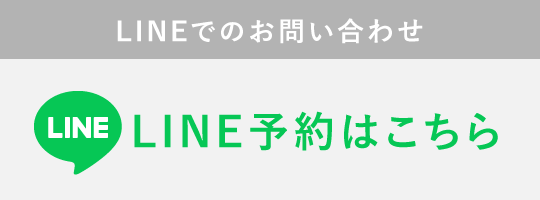Archive for the ‘刑事事件’ Category
市川市の犯罪に強い弁護士
Aさんは、千葉県市川市内の駅のホームで電車を待っていたところ、ホームに到着した電車から制服姿の女性Vさんが降りました。
それを見たAさんは、Vさんについていってエスカレーターに乗り、スマートフォンをVさんのスカートの中に差し込んで盗撮しました。
その様子を背後にいた目撃者に見咎められ、駅員の通報により市川警察署の警察官が駆けつけました。
そして、千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻に事件を依頼された弁護士は、Aさんの勾留を阻止して釈放を実現することにしました。
(フィクションです。)
【盗撮の罪について】
盗撮の禁止と違反に対する罰則は、刑法などの法律ではなく、各都道府県が定める条例により禁止されています。
条例は各自治体がその地域的特色などに合わせて独自に制定することが可能ですが、盗撮に関しては全ての自治体(都道府県単位)において禁止されています。
千葉県においても、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が盗撮に関する規定を置いています。
一般的に、「盗撮」というとカメラで他人を秘密裏に撮影する行為全般を指すかと思います。
ですが、条例が規制している盗撮は、そうした盗撮の中でも限定的な範囲になっています。
具体的には、公共の場所または公共の乗物における、人の身体や下着などの盗撮がその対象です。
千葉県は少し特殊な部類に属し、盗撮の禁止を明記しておらず、「卑わいな言動」に盗撮が含まれるとしています。
そのため、一見して盗撮に関する規制が分かりづらくなっていると言えます。
千葉県における盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮事件において注意すべき点は、特定の1件が発覚した場合に、携帯電話やパソコンなどが押収されて発覚していなかった件が明らかになる可能性があることです。
こうして発覚した事件は、警察により事件化される場合とそうでない場合があります。
もし事件化されれば、最初に発覚した1件と相まってより厳しい刑が科される可能性もないとは言えないでしょう。
【勾留阻止による早期釈放】
刑事事件における身体拘束には、逮捕と勾留という2段階の手続が存在します。
いずれも被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐという点で共通していますが、期間の長さが異なります。
逮捕については最長72時間であるのに対し、勾留については最長20日間(起訴後の勾留を除く)となっているのです。
その理由は、身体拘束の手続を短期と長期に分け、それぞれにつきその必要性を検討する機会を設けることで、被疑者の権利の保護を厚くするというものです。
上で見たように、勾留は逮捕に比べて長期に渡ります。
そこで、捜査機関と裁判所は、勾留に至るまでに厳格な手続を踏むことが要求されています。
まず、被疑者を逮捕した警察官は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁へ送致するか警察署で釈放するか選択しなければなりません。
次に、事件の送致を受けた検察官は、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留を請求するか釈放するか選択しなければなりません。
最後に、検察官から勾留の請求を受けた裁判所が、被疑者の勾留の当否を検討して結論を下すというかたちになっています。
上記の手続が行われる際、弁護士としては関係機関(特に裁判所)に対して被疑者の勾留が妥当でないと意見を述べます。
こうした活動が奏功すると、長期の身体拘束である勾留を阻止する結果、逮捕から2~3日という短期間で釈放を実現することができます。
これに対し、勾留の決定が出てしまった場合には、勾留決定に対する準抗告という不服申立てを行うこともできます。
この不服申立ては、簡易裁判所や地方裁判所が下した決定の当否について、より上級の裁判所に再び検討してもらうというものです。
認められる可能性は一般的に低いですが、被疑者にとってデメリットはないことから、常に考えておくべき手段の一つと言えます。
以上のような活動は早ければ早いほど被疑者のためになるので、もし逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕された方を一日でも早く釈放すべく手を尽くします。
ご家族などが盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
公然わいせつ罪で逮捕
Aさんは、千葉県松戸市内にある居酒屋で酒を飲み、すっかり酔った状態で居酒屋を出ました。
その日は夜になっても気温が高かったことから、酔ったAさんは近くにあった人気のない公園で裸になって寝転びました。
その姿を警ら中の警察官に見られ、警察の存在に気づいたAさんが逃げようとしたこともあってか、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、勾留阻止により早期釈放が実現できないか弁護士に相談してみました。
(フィクションです)
【公然わいせつ罪について】
刑法(一部抜粋)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、その名のとおり公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
まず、「公然と」とは、不特定または多数人がわいせつな行為を認識できる状態であることを指します。
飽くまでも認識が可能であればよく、実際に認識したことは必要ではありません。
ですので、上記事例のように人気のない公園においても、誰でもAさんの姿を認識できた以上「公然と」に該当すると考えられます。
次に、「わいせつ」な行為とは、いたずらに性欲を刺激・興奮させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的観念に反する行為を指します。
この定義自体は強制わいせつ罪における「わいせつ」と同様ですが、必ずしも対象となる「わいせつな行為」の範囲が一致しない点には注意が必要です。
強制わいせつ罪が個人の性的意思決定の自由を害する罪であるのに対し、公然わいせつ罪は社会における性秩序や健全な性的風俗を害する罪です。
こうした罪の性質の違いに照らし、同じ行為であっても強制わいせつ罪の成否と公然わいせつ罪の成否を分けて考えるのです。
これらの罪の成否が異なる典型例として、他人に無理やりキスをするという行為が挙げられます。
キスの相手方からすれば、無理やりされたことから性的意思決定の自由を侵害されたと言え、強制わいせつ罪に当たることが考えられます。
しかし、それが公の場でされても、性秩序や健全な性的風俗が乱されるようには思えません。
そのため、公然わいせつ罪には当たらないと考えられます。
【勾留阻止による早期釈放の可能性】
刑事事件においては、被疑者による逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、逮捕という身体拘束が行われることがよくあります。
この逮捕による身体拘束は、法律上最長でも72時間以内と定められており、それ以上拘束を継続する必要があれば勾留という別個の手続によらなければなりません。
こうして身体拘束を短期の逮捕と長期の勾留に分けることで、身体拘束の必要性を厳格に審査し、人権保障を徹底するというのが法律の建前です。
勾留を行う場合、捜査機関と裁判所は一定の手順を踏む必要があります。
まず、警察が被疑者を逮捕したあと、弁解の録取などを行ったうえで48時間以内に身柄を検察庁に送致する手続をとります。
被疑者の身柄を受け取った検察官は、24時間以内に勾留を請求すべきか判断し、勾留を請求しないのであれば直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
そして、勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者の情報や言い分などを聞いたうえで、勾留の妥当性を認めた場合に勾留を決定します。
以上から分かるように、検察官と裁判官は、被疑者を勾留するかどうかにつき一定の裁量があると言えます。
そこで、被疑者の勾留の阻止を目指すのであれば、検察官と裁判官に対し、勾留が妥当でないことを法的な観点から説明することが大切になります。
もし勾留を阻止できれば、2週間から最悪数か月に及ぶはずだった身体拘束が3日程度で終わる可能性も出てきます。
ですので、もし逮捕の知らせを受けたら、すぐに弁護士に勾留の阻止を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、勾留の阻止を目指して可能な限りの環境調整を行います。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
虐待で逮捕
千葉県浦安市に住むAさんは、娘であるVさん(2歳)に対し、日頃から虐待を咥えていました。
虐待の内容は、腕をつねる、熱いシャワーを浴びせる、自宅の押入れに閉じ込める、といったものでした。
こうした虐待の事実は、Vさんが泣き叫ぶ声を聞いた近隣住民が警察に通報したことで発覚しました。
これにより、Aさんは虐待をしたとして傷害罪などの疑いで浦安警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの夫は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【虐待と刑事事件】
子どもに対する虐待は、昨今の悲痛な事件な発生もあって社会的に問題意識が高まっています。
親にとってはしつけやスキンシップだと思っていても、客観的に見れば虐待であるということは往々にしてあります。
今回は、虐待を行った際に成立することが多い罪について見ていきます。
まず、多くの虐待事件に見られるものとして、暴行罪・傷害罪が挙げられます。
人の身体に「暴行」、すなわち不法な有形力の行使を加えた場合、暴行罪が成立すると考えられます。
更に、これにより「傷害」、すなわち生理的機能の傷害が生じた場合、傷害罪が成立すると考えられます。
罰則は、暴行罪が2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(1日以上30日未満の拘置)もしくは科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
次に、いわゆるネグレクトを行った際にありうるものとして、保護責任者遺棄罪が挙げられます。
この罪は、幼年者などに対し、生活に必要な諸行為をしなかった場合に成立しうる罪です。
罰則は3か月以上5年以下の懲役であり、もし死傷(病気も含む)が生じれば保護責任者遺棄致死傷罪として更に重くなります。
また、虐待の内容が性的なものであった場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪に当たる可能性も出てきます。
これらの罪は、本来であれば暴行または脅迫を要件としますが、対象が13歳未満の者であれば暴行・脅迫なしに成立します。
罰則は、強制わいせつ罪が6か月以上10年以下の懲役、強制性交等罪が5年以上の有期懲役(上限20年)
以上はごく一部であり、その他にも強要罪や監禁罪など様々なものが考えられます。
【初回接見で事件の見通しを知る】
逮捕された被疑者は、警察署などの留置施設に隔離され、ひたすら捜査機関からの取調べなどを受忍する立場に置かれることになります。
こうした状況下で可能な限り上手く立ち回るためには、初回接見を通して弁護士からアドバイスを聞いておくことが有益となります。
逮捕中の被疑者の大きな関心事は、自身がいつ釈放されるのか、最終的に処分がどうなるのか(刑務所に行かなければならないのか)といった点ではないかと思います。
まず、初回接見を行った弁護士は、逮捕中の被疑者から逮捕された理由が分かるか問うことになります。
もし逮捕状などから逮捕の理由をはっきりと理解していた場合、事件の詳細を聞き取ったうえで、今後予想される事件の流れを検討します。
そして、身体拘束(特に勾留)が何日続くと考えられるか、起訴されて裁判が行われるか、最終的に言い渡される刑がどの程度か、などの見立てを答えることになります。
上記の事件の見立ては、事件の内容を認めるかどうかにより変わってくることがあります。
その点は弁護活動にも関わってきますので、いずれにせよ的確な対応するのであれば弁護士に事件を依頼するのが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、初回接見で逮捕された方のご質問に自信をもってお答えします。
ご家族などが虐待の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
窃盗罪で逮捕
千葉県市川市に住むAさんは、近所に住む面識のないVさんに好意を抱いていました。
ある日、AさんはVさんが自宅の鍵をポストに入れて外出しようとするところに出くわしました。
そこで、ポストから鍵をとってVさん宅に侵入し、タンスにあった下着を懐に入れてVさん宅を出ました。
そうしたところ、Aさんの交際相手である男性に見つかり、住居侵入罪および窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの母親は、行徳警察署から逮捕の連絡を受け、弁護士に不起訴にできないか聞いてみました。
(フィクションです)
【窃盗罪について】
窃盗罪は、ご存知のように他人の物を盗んだ場合に成立する可能性のある罪です。
窃盗罪の成立要件は、他人の財物を「窃取」すること、および「不法領得の意思」があったことです。
今回は、上記事例において問題となりうる「窃取」と「不法領得の意思」の有無について検討します。
まず、「窃取」とは、他人の意思に反して物の支配を移転することを指します。
この支配の移転が完遂できれば窃盗罪は既遂となる一方、移転に着手したものの完遂できなければ未遂にとどまります。
問題はどの時点で完遂したと言えるかですが、それは対象物の特性や周囲の状況などにより異なります。
上記事例のように下着を盗んだ場合であれば、懐に入れた時点で自己が支配するに至ったとして、窃盗罪は既遂になる可能性が高いでしょう。
次に、「不法領得の意思」とは、権利者(他人)を排除し、対象物をその経済的・本来的用法に従い利用・処分する意思を指します。
こうした要件が要求される趣旨は、物を一時的に借りるだけの行為や、隠したり壊したりして物の利用を妨げる行為との区別をすることにあります。
窃盗罪に当たる行為はこれらの行為より悪質であることから、行為者の内面により線引きを図るというわけです。
上記事例のように下着を盗むケースでは、通常その下着を転売するなどして利益を得ようとするわけではありません。
ですが、性的欲求の満足など何らかの効用を享受する以上、不法領得の意思は認められると考えられます。
以上より、Aさんの行為は窃盗罪に当たり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【不起訴の獲得は可能か】
ご存知の方も多いかと思いますが、刑事事件というのは、その全てが裁判にかけられて刑罰を科されるわけではありません。
ある事件について裁判を行うかどうかは検察官が握っており、検察官の判断次第では不起訴となってそのまま事件が終了することもあります。
この点は逮捕されようがされまいが変わらないので、逮捕されたからといって必ず起訴されるかというとそういうわけではありません。
不起訴の理由には様々なものがありますが、そのうちの一つとして起訴猶予というものがあります。
起訴猶予とは、被疑者の境遇、犯罪の内容、犯罪後の事情などの多種多様な事情を考慮し、有罪立証の見込みがある場合でも敢えて起訴を見送ることです。
犯罪の疑いが晴れるわけではありませんが、不起訴であることには変わりないことから、前科が付くのを回避できます。
窃盗事件には様々な態様のものがありますが、たとえば少額の万引きとは異なり、住居侵入・窃盗事件というのは決して軽いものではありません。
ただ、被害者との示談が締結するなど、事情次第では不起訴となることもありえます。
ですので、もし不起訴を目指したいということであれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事案に応じた的確な弁護活動によって不起訴を目指します。
ご家族などが窃盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
収賄罪で逮捕
千葉県市川市では、一般企業に公共下水道の修繕工事を依頼することになり、入札に関する広告を行いました。
その入札期間中、市職員のAさんは、Xの代表取締役Bさんから高級料亭で食事をごちそうになりました。
そして、Bさんから「次の入札はぜひうちにお願いします。この話はどうかご内密に」と言われたことから、Xに有利な取り計らいをしました。
その結果Xが指名されましたが、のちに上記やりとりが明るみに出たことで、Aさんは加重収賄罪の疑いで市川警察署に逮捕されました。
Aさんの弁護士は、執行猶予の獲得に向けて弁護活動を開始しました。
(フィクションです)
【収賄罪について】
収賄罪は、公務員が職務に関して賄賂を収受し、またはその要求や約束をした場合に成立する可能性のある罪です。
公務員が「全体の奉仕者」(憲法15条2項)であることから、職務の公正中立とそれに対する社会一般の信頼を保護するために規定された罪です。
行為の内容によって細かく分かれますが、今回は①単純収賄罪、②受託収賄罪、③加重収賄罪に絞って解説します。
まず、単純収賄罪は、収賄罪の中で最も基本的なものです。
公務員が職務に関して「賄賂」を収受し、またはその要求や約束をした場合に成立しうるものです。
ここで言う「賄賂」とは、職務執行の対価となる不正な報酬のことであり、有形・無形を問わず様々な利益が含まれます。
上記事例では、AさんがBさんから高級料亭で食事をごちそうになっています。
このように、お金以外を収受した場合であっても、それが職務執行の対価たる利益である以上、「賄賂」に当たる可能性があります。
法定刑は5年以下の懲役です。
次に、受託収賄罪は、賄賂の収受等の際に、特定の行為をするよう、またはしないよう引き受けた場合に成立する可能性のあるものです。
特定の内容のお願いを引き受けることから、単純収賄罪よりもより重いものとして見られています。
法定刑は7年以下の懲役です。
最後に、加重収賄罪は、賄賂の収受等をした結果、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合に成立する可能性のあるものです。
公務員の職務の公正を危険にさらすにとどまらず、特定人に肩入れすることで公正を損なうことにより、受託収賄罪よりも更に重く罰せられるものです。
法定刑は1年以上の有期懲役(上限20年)です。
【執行猶予を目指して】
収賄罪は、たびたびニュースなどで目にする汚職事件の典型例と言うべきものです。
そのため、証拠が不十分などの事情がない限り、高い確率で起訴されて裁判に至ることが見込まれます。
そこで、第一に行うべき弁護活動として、執行猶予に向けた情状弁護が挙げられます。
執行猶予とは、被告人に有利な事情を考慮して、刑の執行を一定期間猶予するというものです。
執行猶予となる刑の範囲には全部と一部がありますが、実務上目にする機会が多いのは全部の執行猶予ではないかと思います。
刑の全部が執行猶予となった場合、収賄罪のように懲役刑のみが定められている罪を犯しても、刑の確定後直ちに刑務所に行くという事態は回避できます。
それだけでなく、猶予期間中に新たな罪を犯すなどして執行猶予が取り消されない限り、猶予期間の経過後は刑を科されることがなくなるのです。
収賄罪を犯したケースについては、直接的な被害者がいないことから、有力な弁護活動である示談という手段をとることが基本的にできません。
ですので、執行猶予を目指すのであれば、個々の事件に合わせて弁護士に情状弁護の材料を検討してもらうのが賢明です。
弁護士への依頼が事件の明暗を分けることもありえるので、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、執行猶予の獲得に向けて事件を綿密に検討します。
ご家族などが収賄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
建造物侵入罪で逮捕
Aさんは、中学生の着替えを盗撮しようと思い、千葉県鎌ケ谷市にある中学校に忍び込みました。
その中学校は、部活動に来る生徒がいることから休日に校舎を開放しており、誰でも比較的容易に侵入できる状態になっていました。
Aさんが教室にいたところ、見回りをしていた警備員に見つかり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
弁護士は、Aさんに聞かれたことから現行犯逮捕について説明しました。
(フィクションです)
【建造物侵入罪について】
刑法(一部抜粋)
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法130条前段は、住居侵入罪をはじめとする各種の侵入罪についての規定であり、建造物侵入罪についても定めています。
「侵入後に何かを行う」というかたちで、他の罪とセットで成立することが多く見られます。
実務上比較的よく見られるものとして、窃盗罪・建造物侵入罪という組み合わせがあります。
建造物侵入罪の要件である「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法なものとして正当化できる事情のことを指します。
たとえば、建造物の管理者が立入りに同意している場合のほか、暴漢から逃げるため近くの建物に逃げ込んだ、などのケースが考えられます。
また、「建造物」とは、住居や邸宅といった居住用のものを除く、建造物一般を指します。
「人の看守する」という限定がありますが、人が現にいる必要はなく、管理・支配のための設備(たとえば施錠)などがされていれば事足ります。
仮に人が住んでおらずなおかつ看守もされていない建造物に立ち入った場合、住居侵入罪には当たらないと考えられます。
ただし、その場合は軽犯罪法違反の罪に当たり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科されるおそれがあります。
ちなみに、上記事例のAさんが盗撮を遂げた場合、建造物侵入罪とは別に千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)に当たる余地が出てきます。
そうなると、当然ながらより重大な事件と評価されることになるでしょう。
【現行犯逮捕とは】
ご存知の方も多いかと思いますが、現行犯逮捕とは、犯罪の最中または終了直後の被疑者を直ちに逮捕する手続を指します。
逮捕状を示されて自宅や警察署で行われる通常逮捕とは異なり、以下のように法律上は例外的なものとして位置づけられています。
本来、逮捕という行為は被疑者の身体の自由を奪うことから、犯罪の疑いの程度や身体拘束の必要性を裁判官に審査してもらわなければなりません。
ですが、現行犯逮捕については、こうした審査を経る逮捕状請求を行うことなくできると定められています。
その理由として、現行犯逮捕の場合、犯人の身柄確保の必要性が大きく、なおかつ誤認逮捕のおそれが小さいからだと説明されます。
先述のとおり、現行犯逮捕というのは、通常逮捕とは異なり即座に行われるものです。
この事実は一見デメリットのように思えますが、場合によってはメリットと捉えることができます。
なぜなら、現行犯逮捕の場合、通常逮捕の場合ほど被疑者の身体拘束の必要性を綿密に検討していないと言えるからです。
この点を突けば、たとえ現行犯として逮捕されたとしても、身柄拘束の必要性がないとして勾留阻止により釈放されることがあるのです。
ですので、万が一周囲の方が現行犯逮捕されたと知っても、まずはできるだけ冷静になって弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、現行犯逮捕された方のために可能な限り早く初回接見を行います。
ご家族などが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
傷害致死罪で正当防衛
Aさんは、かつて交際していたVさんに別れを切り出し、交際の解消を頑なに拒むVさんから距離を置きました。
それから数カ月経ったある日、Aさんが友人の紹介で知り合った女性Bさんと千葉県船橋市内を歩いていたところ、目の前にカッターナイフを持ったVさんが現れました。
Aさんはすぐに逃げよう思いましたが、Bさんがハイヒールを履いていたことから逃げ遅れることを懸念し、持っていた傘をVさんに数回突き当てました。
これにより、Vさんは顔面や上半身に傷を負い、Aさんは傷害罪の疑いで船橋東警察署にて取調べを受けることになりました。
その後、Aさんによる傷害が原因でVさんが死亡したため、Aさんの捜査は傷害致死罪で進められることになりました。
そこで、Aさんは弁護士に正当防衛を主張できないか相談しました。
(フィクションです)
【傷害致死罪について】
人の身体を傷害し、結果的にその人が死亡した場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
同じく人の死亡を生じさせる罪として殺人罪がありますが、殺人罪と傷害致死罪とでは決定的に違う点があります。
それは、行為時における殺意の有無という点です。
殺人罪の場合、暴行を加えた時点において殺意があり、思いどおり殺害を遂げることが成立要件となっています。
それに対して、傷害致死罪の場合、暴行の際に殺意こそなかったものの、暴行が原因となって結果的に死亡が生じることが成立要件となっています。
最終的に生命が侵害されている点は共通ですが、問われるべき責任の重さという観点から明確に区別されているのです。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(上限20年)です。
一方、殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の有期懲役のいずれかであるので、その差は相当なものと言うに値します。
ここで注意すべきは、殺意の有無が一見して明確に分からないことから、捜査においていずれを疑われるかが流動的な場合がありうることです。
これは「殺すつもりじゃなかった」と供述すれば済むほど単純な問題ではなく、最悪の場合殺人罪として不相応に重い刑罰が下されかねません。
こうしたリスクがあることに十分注意し、弁護士に相談して入念に主張を検討することが重要となるでしょう。
【正当防衛として無罪の主張をするには】
日常生活でも耳にするように、「正当防衛」という言葉自体は広く周知されていると言っても過言ではありません。
ですが、正当防衛というのは、本来違法な行為を公的に適法と認めるという重大な効果を持つものです。
そのため、その成立要件は厳しく、時には裁判においてその成否が激しく争われることも珍しくありません。
正当防衛の主張をした場合、「正当防衛の名目で加害に及ぶことが必要だったか」という点があらゆる角度から検討されることになります。
たとえば、本当に身の危険があったか、単に機会を利用して痛めつけたかっただけではないか、複数回反撃する必要はあったのか、などです。
こうした諸事情は、動揺、恐怖、怒りといった人間の心理も関わってくるものであり、そのことも踏まえて的確な主張をしなければなりません。
ですので、もし正当防衛の主張により無罪を目指すのであれば、腕の立つ弁護士に依頼することを強くおすすめします。
有罪か無罪かは人生の明暗を分けると言っても過言ではないので、ぜひ慎重にご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、正当防衛のような難しい主張も可能な限り検討します。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
児童福祉法違反(淫行)で逮捕
千葉県船橋市内の高校に勤務するAさんは、音楽の教員を務めるかたわら、顧問として吹奏楽部の指導に励んでいました。
そんなAさんは、部員のひとりであるVさん(16歳)から特に慕われており、Aさんとしても部活後に個人レッスンをするなど気にかけていました。
コンクールメンバーを決めるオーディションを控えたある日、Aさんは不安を吐露するVさんに愛おしさを覚え、それとなく性行為を誘いました。
Vさんが誘いに乗ったことから性行為に及んだところ、後日この事実が公となり、Aさんは児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)の疑いで船橋警察署に逮捕されました。
Aさんは、初回接見に来た弁護士から今後の流れを聞きました。
(フィクションです)
【児童福祉法における淫行の禁止】
日本では、児童(18歳未満の者)を保護するなどして健全な育成を実現すべく、児童福祉法という法律が定められています。
児童福祉法の規定の中には、児童の健全な育成を妨げる行為を禁止し、違反した場合に刑罰を科すものがあります。
今回は、実務において比較的よく見られる「児童に淫行をさせる行為」について説明します。
児童福祉法(一部抜粋)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一~五 略
六 児童に淫行をさせる行為
七~九 略
「淫行」とは、18歳未満の者との間で行うみだらな行為を指します。
性交だけでなく、たとえば性器を触るなどの行為も含まれると考えられます。
こうした「淫行」を禁止する法令としては、児童福祉法のほか、各都道府県が定める青少年健全育成条例が挙げられます。
ですが、児童福祉法における「児童に淫行をさせる行為」は、裁判例によってその定義が限定されています。
児童福祉法を適用する場合、淫行に際して児童に事実上の影響力を行使したと言えなければなりません。
つまり、精神面で児童に働きかけるなどして、児童が淫行に及ぶような状況をつくりだしたという事情が必要となるのです。
上記事例では、高校の教員かつ部活の顧問であるAさんが、コンクールメンバーのオーディション前に、生徒であるVさんと淫行に及んでいます。
このような事情の下では、AさんがVさんに対して明示的あるいは黙示的に影響力を行使して行為に至ったと考えられます。
そうすると、Aさんの行為は児童福祉法違反となり、10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあるということになるでしょう。
【初回接見で事件を把握】
突然逮捕された被疑者は、自身が置かれている状況や今後の手続の流れなどが全く分からないことが珍しくありません。
仮に家族など周囲の者が顔を合わせようにも、面会できない時期(たとえば逮捕から勾留決定までの2~3日間)がある、面会時間が著しく制限されるなど、障害は数多く存在します。
こうした状況下における特効薬として、弁護士による接見(面会のこと)が挙げられます。
弊所で行っている初回接見を利用すれば、以下のようなメリットを享受することが期待できます。
まず、連絡を受けてから迅速に接見を行い、法律の専門家として現在の状況や予想される事件の流れなどを逮捕された方にご説明できます。
「何日後に何が行われる」ということが分かれば、現在の自分の立場を理解して多少なりとも安心感を得られるでしょう。
次に、ご家族などとの伝言を仲介し、言葉を交わす手助けをすることができます。
弁護士の接見は先述した面会禁止や時間制限などの制約を受けないので、弁護士倫理(たとえば証拠隠滅の禁止や守秘義務の遵守など)に反しない限り何でも気兼ねなく伝達できます。
そして、接見報告を通して事件の詳細を聞くと共に、必要に応じて弁護士に質問をすることで疑問点を解消できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが児童福祉法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
営業妨害で逮捕
Aさんは、千葉県八千代市内のスーパーマーケットでサラダを買って食べようとしたところ、なめくじが混入していることに気づきました。
そこで、すぐに店内に戻り、サービスカウンターでなめくじが混入していたことを騒ぎ立てました。
その際、対応した店長の態度が気に入らなかったことから、「どうなっとんじゃこの店は。金を出せ。誠意を見せろ」などと言って店長の胸倉を掴みました。
この行為が仇となり、Aさんは恐喝未遂罪の疑いで八千代警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです)
【営業妨害をした場合に成立しうる罪】
ニュースなどで見られるように、上記事例のようなケースは日本各地で時々発生しています。
今回は、上記事例を題材に、Aさんのような客にどのような罪が成立する可能性があるのか見ていきます。
①恐喝罪
恐喝罪は、暴行または脅迫を加えて相手方に財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う暴行・脅迫は、抵抗が不可能または著しく困難とは言えないまでも、人を畏怖させるに足りる程度のものが必要とされています。
法定刑は10年以下の懲役です。
②強盗罪
およそ抵抗が困難なほど強度の暴行・脅迫を加えて財産を奪取した場合、恐喝罪ではなく強盗罪が成立する余地が出てきます。
たとえば、激しい暴行を加えた場合、脅迫に刃物などの凶器を用いた場合、強盗罪となる可能性が高くなると考えられます。
法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)です。
③威力業務妨害罪
「威力」を用いて他人の円滑な業務の遂行を妨げた場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「威力」には、たとえば怒号を飛ばすなど、暴行や脅迫とは言えない程度のものも含まれます。
スーパーなどの店内で暴れて混乱を生じさせれば、この罪が成立する可能性は高いでしょう。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
以上のほか、暴行罪、傷害罪、器物損壊罪など、考えられるものは数多くあります。
【早期釈放を実現するには】
被疑者として逮捕された場合、その後48時間以内に事件が検察庁に送られ、検察庁で24時間以内に勾留請求が行われる可能性があります。
そして、もし裁判官が勾留の妥当性を認めれば、逮捕中の被疑者は10日から20日もの間拘束されていまいます。
逮捕を含めると身体拘束の期間は最長23日間に及び、様々な不利益を受けることが予想されます。
この間に行うべきことの一つとして、被疑者の釈放を実現するための身柄解放活動が挙げられます。
特に重要なのは、長期の身体拘束である勾留が決定する前の段階です。
この段階では、検察官と裁判官に対して、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶおそれが低いことや、仮に及ぼうとしてもそれを阻止できることを主張する必要があります。
勾留がつく理由というのは基本的に逃亡と証拠隠滅のおそれの存在なので、この点を解消することが不可欠となってくるのです。
上記事例のように恐喝などの粗暴な面が見られる場合、被害者(被害店舗)との接触がどうしても懸念されるところです。
そうしたケースでは、やはりその点のフォローが非常に重要になってくるでしょう。
早期の釈放に向けてベストな対応を行うなら、ぜひ弁護士に事件を依頼して的確な弁護活動を行ってもらってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のスペシャリストを自負する弁護士が、一日でも早い釈放の実現に向けて尽力します。
ご家族などが営業妨害をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
麻薬で逮捕
Aさんは、大学を卒業してから3年勤めた会社を退職し、数か月間は貯金を崩して怠惰な生活を送っていました。
ある日、Aさんが千葉県習志野市内を歩いていたところ、「気持ちよくなる薬買わない?」と外国人に声を掛けられました。
その薬はいわゆるMDMAであり、Aさんは服用後の作用から何らかの違法な薬物であることに気づきました。
その後、Aさんは定期的にMDMAを購入するようになり、やがて麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで習志野警察署に逮捕されました。
弁護士に事件を依頼したAさんは、執行猶予の獲得に向けて更生を目指すことを誓いました。
(フィクションです)
【麻薬所持について】
上記事例で登場しているMDMAは、身体に様々な作用を及ぼす化学物質を成分とする錠剤型の麻薬です。
幻聴や幻覚の発生、脳の機能不全など、その悪影響は数多くあります。
日本においては、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律が麻薬に関する種々の規制を定めています。
まず、規制対象である「麻薬」の具体例は、法令により化学物質が列挙されるかたちで指定されています。
先述の法以外に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」などに定めがあります。
麻薬に関して禁止されている行為は多岐にわたります。
中でも特によく見られるのは、やはり麻薬の所持と言えるでしょう。
麻薬所持の罰則は、所持した麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(「等」は塩類も含む趣旨)を含むものだったか否かにより異なっています。
まず、「ジアセチルモルヒネ等」を所持した場合については、10年以下の懲役となっています。
もし営利目的(たとえば販売目的)での所持であれば、罰則は1年以下の有期懲役(上限20年)、更に場合により500万円以下の罰金が併科されます。
次に、「ジアセチルモルヒネ等」以外を所持した場合については、7年以下の懲役となっています。
こちらに営利目的がつくと、1年以上10年以下の懲役、更に場合により300万円以下の罰金が併科されます。
いずれにせよ、年単位で懲役刑が科されることから重大と言えるでしょう。
【執行猶予を目指して】
麻薬所持を含む薬物事犯は、基本的に不起訴で終わるということがあまり期待できません。
ですので、もし事件が発覚すれば、よほどのことがない限り起訴されて裁判に至ると考えて構いません。
逮捕および勾留による身体拘束の可能性も高くなっています。
上記の点と罰則の重さを踏まえると、麻薬所持事件において第一に目指すべきは執行猶予の獲得だと考えられます。
執行猶予が獲得できれば、裁判が確定してから直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
そのため、裁判が終わってから社会復帰をすることが可能となっています。
更に、執行猶予期間中に罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、期間の満了をもって刑を免れることができます。
有罪となって刑を言い渡された事実が消えるわけではありませんが、もはや刑の執行を憂う必要がない点は有益です。
執行猶予を獲得するうえで重要なのは、裁判で更生の意思をきちんと示し、目指すべき将来があることを裁判官に訴えることです。
そのためには相応の労力を費やすことが必要であり、闇雲に行うのは賢明ではありません。
少しでも執行猶予の可能性を高めるのであれば、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
もし事件を依頼すれば、執行猶予獲得に向けた手厚いサポートが受けられるはずです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予の獲得に向けて手を尽くします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
« Older Entries Newer Entries »