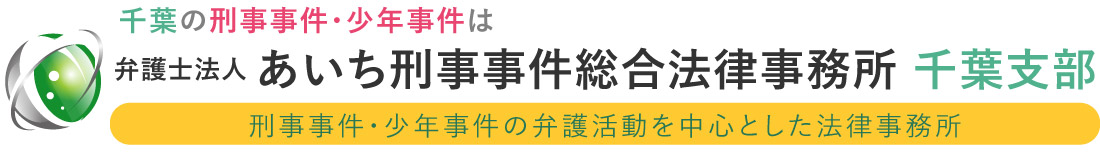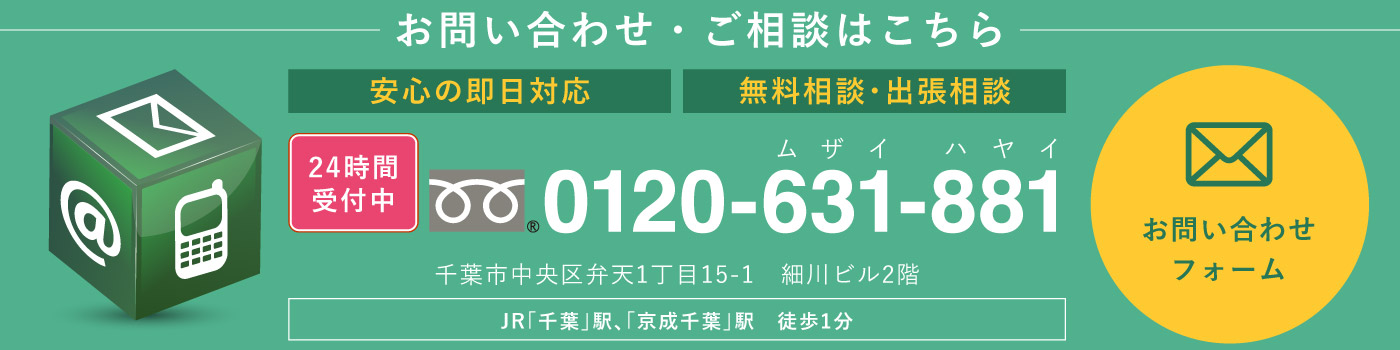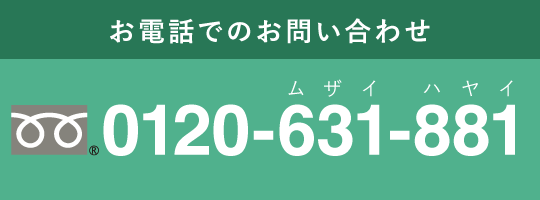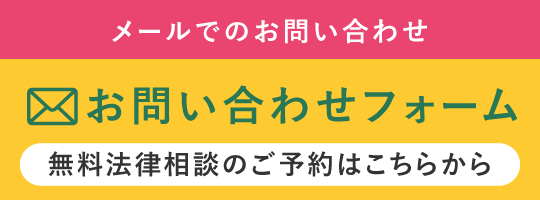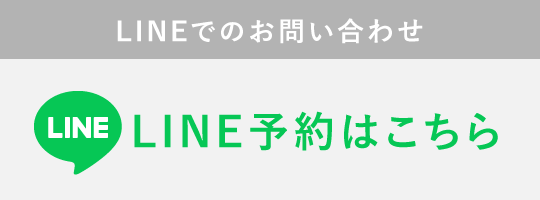Author Archive
詐欺罪で不起訴
詐欺罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県船橋市に住むAさんは、自宅からほど近い銀行のATMで記帳を行ったところ、身に覚えのない200万円の入金が行われていることに気づきました。
Aさんはそれが誤って振り込まれたものだと気づきましたが、「せっかくだから自分のものにしよう」と考えるに至りました。
そこで、銀行の窓口に行き、通帳と印鑑を用いて200万円を引き出しました。
後日、Aさんがふと誤振込みについてインターネットで調べると、詐欺罪に当たる場合があるという記載が目に入りました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、刑事事件になった際には不起訴を目指す余地があると説明しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、他人から財産を騙し取った場合に成立する可能性のある罪です。
より詳しく言うと、①他人を欺いて②その他人の勘違いなどを引き起こし、③勘違いなどに陥った他人から財産の交付を受けた場合に詐欺罪が成立します。
上記事例において、Aさんは自己の口座に誤って入金された200万円を銀行の窓口で引き出しています。
おそらく、こうした行為が詐欺罪に当たる可能性があると聞くと違和感を持たれるのではないかと思います。
ですが、結論から言うと、Aさんに詐欺罪が成立する可能性はあります。
詐欺罪の成立要件である「他人を欺く行為」は、積極的に嘘をつくことのみならず、言うべきことを敢えて言わない、というのも含まれると考えられています。
ここで銀行側の事情を見てみると、銀行を含む金融機関においては、誤振込みが発覚した場合にそれを元に戻すための手続を行う必要があります。
そうすると、銀行が金銭の引出しに応じる際に、それが誤振込みされたものでないかどうかは重要な事柄ということになります。
それにもかかわらず誤振込みの事実を黙ってお金を引き出そうとするのは、詐欺罪の成立要件である他人を欺く行為に当たると評価できます。
こうして、誤振込みされたお金を敢えて引き出したAさんには、詐欺罪が成立する可能性があるのです。
【不起訴の可能性】
上記事例において、Aさんは今後銀行か警察から連絡が来る可能性があります。
仮に警察が介入して刑事事件となった場合は、以下のとおり不起訴を目指すことが考えられます。
①起訴猶予による不起訴
検察官は、ある事件について起訴するか不起訴にするか決める際、事件の内容以外にも様々な事情を考慮します。
起訴猶予による不起訴は、たとえ有罪を立証できる見込みがあっても、上記のように様々な事情を考慮した結果起訴を見送るべきだと考えられた場合にするものです。
主に考慮される事柄としては、被害者との示談の有無とその内容、被告人の反省の程度、起訴して有罪となった場合の影響などが挙げられます。
以上から、弁護士としては、示談を行うなどして起訴猶予による不起訴を目指すという手があります。
②嫌疑不十分による不起訴
日本においては、検察官が有罪をほぼ確実に立証できると考えた場合に限って起訴する傾向にあります。
そのため、検察官としては、「裁判を行ったとすれば有罪を立証できる証拠が揃っているか」という点を常に意識していると考えられます。
このことから、ある事件について証拠が乏しい場合、その事件については被疑者の嫌疑が不十分として不起訴となります。
そこで、弁護士としてはこの点を突いて嫌疑不十分による不起訴を目指すことも想定できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、不起訴を目指して弁護活動を尽くします。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
公務執行妨害罪で略式起訴
公務執行妨害罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県千葉市内の居酒屋で大量に飲酒したあと、自宅まで歩いて帰っていました。
すると、警察官から職務質問を受け、鞄の中身を見せるよう言われました。
Aさんが「任意だろ。なら拒否するわ」と所持品検査を拒んだところ、警察官は突然Aさんの鞄を無理やり奪おうとしました。
これに対してAさんが抵抗したところ、公務執行妨害罪と言われて現行犯逮捕されました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、略式起訴について説明しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
公務執行妨害罪を目にするのは、警察官に対して暴行を振るったというケースが少なからず見受けられるかもしれません。
ですが、公務執行妨害罪の適用を受ける公務員は、警察官のように有形力を行使する(たとえば被疑者の身柄の拘束)公務員に限られません。
そのため、たとえば生活保護などの申請を取り扱う市役所の職員に暴行を加えた場合も、公務執行妨害罪に成立する余地があります。
ただし、「公務員が職務を執行するに当たり」とあるように、公務員の身分を持つ者であればいかなる状況(たとえば休みの日)でも公務執行妨害罪の対象となるわけではありません。
また、条文に明記されているわけではありませんが、公務執行妨害罪の成立を認めるには公務が適法なものであることが必要だと解釈されています。
先述のとおり、公務執行妨害罪は円滑な公務の遂行を保護しているところ、公務が違法であれば保護に値しないと考えられるからです。
そのため、上記事例においても、警察官の行為が違法だとすれば公務執行妨害罪に当たらない余地があります。
【略式起訴に応じるべきでない場合はあるか】
略式起訴とは、事件を通常の裁判より簡易・迅速な手続で処理する特殊な起訴の形式を指します。
具体的には、検察官の判断と被疑者の同意を経たうえで、裁判官が事件の審理を書面上で行うというものです。
有罪・無罪の判断が下されて刑罰(罰金刑)が科されるのは通常の裁判と同じですが、わざわざ関係者や傍聴人がいる法廷での審理をしない点で通常の裁判と異なります。
検察官が略式起訴による意思を示した場合、通常の裁判に伴う心身の負担の軽減が期待できることから、被疑者としてはそれに同意するのが得策のように思えます。
ですが、略式起訴につき注意すべき点として、基本的に捜査機関が提出した資料に沿って事実の認定が行われることが挙げられます。
このことは、たとえ事実関係を争って無罪になる可能性があっても、その点が検討されることなく有罪となってしまうおそれがあることを意味します。
上記事例では、警察官がAさんの鞄を無理やり奪おうとしていることから、違法な捜査に当たるとして公務執行妨害罪による保護を受けない可能性があります。
もしそうであれば、Aさんは略式起訴ではなく通常の裁判を要求し、無罪を目指して徹底的に争うのも一つの手だと考えられます。
こうした選択に悩んだら、ひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴に応じるべきか否かについて的確なアドバイスを致します。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
中学生の通貨偽造罪と保護観察
中学生の通貨偽造罪と保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県習志野市に住むAさん(14歳)は、最近発売された新作のゲームを買いたいと両親にお願いしましたが、成績が下がっていることを理由に拒否されました。
それでもゲームが欲しかったAさんは、1万円札を模したメモ帳を購入したうえで、プリンターなどによる加工を経て1万円札様の偽札を複数枚つくりました。
そして、市内にあるショッピングモールにて偽札を差し出したところ、偽札だと見破られて警察に通報されました。
その結果、Aさんは通貨偽造罪および偽造通貨行使未遂罪の疑いで習志野警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、なんとか保護観察にとどめることを目指すべきだと助言しました。
(フィクションです)
【通貨偽造罪について】
刑法(一部抜粋)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
通貨偽造罪は、その名のとおり「通貨」(日本で使用できる硬貨や紙幣)を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
まず、通貨偽造罪は、その成立に「行使の目的」という主観的な事情を要する類型です。
そのため、通貨偽造罪の成立を認めるためには、単に通貨を偽造しただけにとどまらず、その際に通貨を行使する目的があったと言えなければなりません。
ここで言う「行使の目的」とは、偽造したものを真正な通貨として流通させる目的を指します。
偽札を買い物に使おうとして通貨を偽造したのであれば、基本的にこの要件に該当すると考えられます。
次に、「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た見た目のものを作成することを指します。
ただし、偽造した通貨の完成度は、一般人が本物の通貨だと誤信するに足りる程度でなければならないと考えられています。
つまり、一目見て偽札だと見破れるものであれば、「偽造」したとは言えず通貨偽造罪に当たらない余地が出てきます。
とはいえ、その場合であっても「通貨及証券模造取締法」という法律により罰せられる可能性があるため注意が必要です。
【少年事件における保護観察の特徴】
「少年」(20歳未満の者)が罪を犯した場合、その少年に対しては原則として刑罰が科されません。
その代わりに、少年の更生と健全な育成を図るべく、保護処分という少年事件に特有の処分が予定されています。
保護処分は家庭裁判所の審判を経て行われるものであり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察の3つがあります。
また、上記のような処分が下されないケースとして、不処分(審判の結果何らの保護処分も下さないこと)や審判不開始(そもそも保護処分を決めるための審判をしないこと)とされる場合があります。
今回弁護士が目指すべきだとしているのは、上記のうち③の保護観察という処分です。
少年事件における保護観察は、上記①②と異なり、基本的に在宅で少年の更生を図る処分です。
少年は心身共に発育段階にあるので、やはり本来の居場所である各家庭で円満な生活を送るのが望ましいと思われます。
そうであれば、数ある処分の中から保護観察を目指すのは有力な選択肢となるでしょう。
先述のとおり、保護観察は主に在宅での更生を目指すものであることから、果たして少年の家庭がそれに適するかどうかが見られることになります。
その点につきいかなるアピールができるかという点は、弁護士に相談して助言を得ることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、保護観察をはじめとする、少年ひとりひとりに応じた最善の処分を検討して活動します。
お子さんが通貨偽造罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
万引き事件で裁判
万引き事件で裁判
万引きと裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、夫の浮気によってショックを受けたことをきっかけに、特にお金に困っていないにもかかわらず万引きを繰り返すようになりました。
そのうち何度かは店に発覚しており、警察署で取調べを受けたこともありましたが、裁判になった記憶はありませんでした。
ある日、Aさんが千葉県千葉市所在のスーパーマーケットVにて万引きを行ったところ、店長に反抗を見咎められて警察に通報されました。
Aさんは千葉中央警察署にて取調べを受けることになり、警察官から「過去にもやってるよね。次は裁判になってもおかしくないよ。」と言われました。
そこで、不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【万引きに成立する可能性のある罪】
ご存知の方も多いかと思いますが、万引きとはスーパーやコンビニなどの店で勝手に商品を持ち去る行為を指します。
万引きを行った場合、成立する可能性のある犯罪として最初に挙げられるのはやはり窃盗罪です。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法定刑の上限は10年の懲役となっており、事案によっては決して軽くない刑が科されることがありえます。
具体的にどの程度の刑が言い渡されるかは、被害額の多寡、犯行の手口、前科の有無とその内容など、様々な事情を考慮して決定されます。
後述のように処罰を受けずに済むケースもあれば、初犯でも懲役の実刑を受け刑務所での生活を余儀なくされるケースもあるでしょう。
更に、万引きが発覚した際に捕まるまいと抵抗すると、窃盗罪ではなく事後強盗罪に当たる可能性が出てきます。
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的で他人に暴行または脅迫を加えた場合に、強盗罪と同じ取り扱いを認めるものです。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪の法定刑である5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
そうなると、単なる万引きでは済まなくなるでしょう。
【万引きでも裁判になるか】
過去に万引きをされたことがある方の中には、万引きが発覚したものの何の処分も受けなかったという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
その理由としては、①店が警察に被害を申告しなかった、②警察官が微罪処分をした、③検察官が不起訴処分をした、という3つが考えられます。
②の微罪処分は、事件が軽微で被疑者の反省が見られる場合に、警察署限りで事件を終了させるというものです。
また、③の不起訴処分は、事件の内容や被疑者の反省を含む様々な事情を考慮し、検察官が裁判にかけるのを見送るというものです。
いずれについても、万引きの被害が少額に収まっていた場合になされると考えられます。
上記の②③だった場合、裁判や刑罰こそ受けないものの、万引きを疑われた記録は捜査機関に残ります。
そのため、たとえ少額の万引きであっても、それを繰り返せば裁判に至る可能性は当然生じます。
「万引きをしても裁判にならない」というわけではないので、その点に関しては十分に注意しておく必要があります。
仮に万引きを繰り返して裁判が予想されたとしても、示談や再犯防止策などにより処分を軽くできる可能性はあると考えられます。
まずは弁護士に相談し、最悪の結果を避けるためにできることがないか一緒に考えてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、裁判に関する様々なご相談をお受けします。
万引きをしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
児童買春で略式起訴
児童買春と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、インターネット上の掲示板で援助交際を求める書込みを探していました。
すると、書込みの中に「JK2」と記載されたものがあり、興味を持って連絡してみました。
後日、Aさんはその書き込みをしたVさんと千葉県鴨川市で待ち合わせ、2万円を支払って市内のホテルで性行為に及びました。
2人が行為を終えてホテルを出たところ、鴨川警察署の警察官から職務質問を受け、Aさんは児童買春の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、「1件のみなら略式起訴による罰金刑で終わる可能性がある」と伝えました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春の定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、処罰の対象となる「児童買春」とは、以下の要件の全てを満たすものを言います。
①次のいずれかの者に対して、性交等の対償を供与し、またはその約束をしたこと
・児童(18歳未満の者)
・児童に対する性交等を周旋する者
・児童の保護者または児童をその支配下に置いている者
②児童に対して性交等を行ったこと
そして、「性交等」には、性交とその類似行為のみならず、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童に自己の性器等を触らせたりする行為も含まれます。
これらのうち、性器等を触ったり触らせたりする行為については、「自己の性的好奇心を満たす目的で」という限定が付されています。
とはいえ、そうした目的がなかったとして児童買春の成立を否定しても、不合理な弁解だとして一蹴されるケースが少なくないでしょう。
児童買春の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
この罰則自体も重いものですが、注意しなければならないのは13歳未満の者と性交またはその類似行為をした場合です。
この場合については、児童買春ではなく強制性交等罪となり、5年以上の有期懲役(上限20年)が科されることが見込まれます。
児童買春を含め、児童に対する行為については特に警戒しておくべきです。
【略式起訴とは何か】
ニュースや新聞などで「略式起訴した」といった言葉を見かけられたことがあるかもしれません。
刑事事件は、捜査機関により必要な捜査が遂げられたあと、検察官が起訴か不起訴か(裁判にかけるべきかどうか)を決定することになります。
略式起訴も検察官による起訴であることには変わりないのですが、通常の起訴とは異なる特徴が見られます。
略式起訴の最大の特徴は、事件の審理を裁判所の法廷ではなく書面上で行う点だと言えます。
これにより、裁判所にわざわざ出頭し、傍聴人などが存在する公の場で裁判を受けることは回避できます。
また、略式起訴がされた事件については、基本的に100万円以下の罰金刑が科されて終了します。
そのため、懲役刑を選択する余地がある罪については、検察官が略式起訴にする意向を示した時点で刑が比較的軽いものになると予想がつきます。
これらの点は、多くの方にとって略式起訴に特有のメリットだと言えるでしょう。
一方で、略式起訴により事件が処理されるということは、充実した審理が多かれ少なかれ犠牲になるリスクが生まれることになります。
この点をフォローすべく、略式起訴に対しては一定の条件下で不服を申し立てることができるようになっています。
そのことも含めて、略式起訴に関するご相談は弁護士にお申し出ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴に関する様々なお悩みの解決に尽力します。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
傷害事件で勾留阻止
傷害事件で勾留阻止
傷害事件と勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県館山市に住むAさんは、市内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。
その際、ついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。
怒りが収まらなかったAさんは、Vさんの顔面を1発殴り、一緒にいた友人に慌てて制止されました。
Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた館山警察署の警察官により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、暴行などによって人に「傷害」を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
一般的には、殴る蹴るといった行為により出血や骨折を負った、などのケースが典型かと思います。
ですが、こうしたケース以外にも、相手方に何らかの身体の不調を生じさせれば傷害罪が成立する余地があります。
なぜなら、傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと解されているからです。
この「傷害」にさえ至れば、それがたとえ暴行によるものではなかったとしても傷害罪の成立は妨げられません。
裁判例では、嫌がらせ行為により抑うつなどの精神障害を生じさせたケースについて、傷害罪の成立を認めたものがあります。
傷害を負わせた他人が死亡した場合、殺意があれば殺人罪が、殺意がなければ傷害致死罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役のいずれか、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(上限20年)とされています。
また、死亡には至らなかったものの重い障害が残るなど結果が甚だしければ、成立するのは傷害罪でも相応の重さの刑が見込まれます。
傷害事件はよく目にするものですが、その刑罰が決して軽くないことは改めて認識しておくべきです。
【勾留阻止による早期釈放の可能性】
警察署などに拘束されている状態を「逮捕されている」と表現することが多いかと思いますが、この身体拘束は厳密に言えば逮捕と勾留の2段階に分けられます。
刑事事件に関するルールを定めた刑事訴訟法は、逮捕の期限を最長72時間とし、それより長く拘束する必要がある場合は勾留という別個の手続によるものとしています。
そのため、正確に言えば身体拘束の開始から2~3日が逮捕で、そこから先は勾留ということになります。
逮捕から勾留までの流れを詳しく見ると、以下のようになるのが通常です。
①逮捕による身体拘束
②警察署での弁解録取などの手続
③検察庁への送致
④検察庁での身柄の受理や弁解録取などの手続
⑤検察官による勾留請求(ここまでで最長72時間)
⑥裁判官による勾留質問と勾留の当否の判断
⑦勾留
早期釈放を実現する場合、弁護士としては主に⑤および⑥の段階で勾留を阻止することを目指します。
具体的には、書面の提出や電話での面談により、検察官や裁判官に対して勾留が妥当でないことを主張することになります。
こうした活動が奏功して勾留を阻止できれば、逮捕されても2~3日のうちに釈放されます。
逆に勾留が決定されれば、10日から数か月単位で身体拘束が継続してしまいます。
以上で見たように、勾留されるかどうかという点は、逮捕された多くの方にとって一つの分岐点となりうる事柄です。
勾留の阻止による早期釈放の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき身柄解放の見通しなどをお伝えいたします。
ご家族などが傷害事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
女子トイレでの盗撮事件と勾留②
女子トイレでの盗撮と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県千葉市に住むAさんは、盗撮目的で市内にある公民館の女子トイレに侵入しました。
そして、個室に入ってしばらく息を潜めていたところ、隣の個室に人(Vさん)が入ってきました。
Aさんが個室の隙間からスマートフォンを差し向けると、たまたま画面に手が当たって動画の撮影終了ボタンをタップしてしまい、その音でVさんに盗撮していると気づかれました。
Aさんが女子トイレを出たところ、Vさんの悲鳴を聞いた男性に身柄を確保されました。
その後、Aさんは建造物侵入罪の疑いで千葉西警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留の阻止または短縮を目指して弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)
【勾留の当否を争って身体拘束の期間を短縮する】
刑事事件における身体拘束は、厳密に言うと①逮捕と②勾留の2種類に分かれています。
逮捕された被疑者は、多くの場合、2~3日の間に警察署→検察庁→裁判所と移動することになります。
これは、長期の身体拘束である勾留をすべきかどうか判断するためのものであり、その必要がないと判断されればその時点で釈放されます。
裁判所までいって裁判官の判断を経た結果、長期の身体拘束の必要性が認められると、勾留という手続に移行して最低10日間の身体拘束の継続が決定します。
更に、勾留延長や起訴などが行われると、場合によっては数か月単位で勾留されることになります。
勾留は上記のとおり長期の身体拘束を余儀なくされるものであり、それが行われることによる不利益は殆どの方にとって著しいものと言えます。
そうした不利益を可能な限り抑えるべく、適切なタイミングで勾留の当否を争い、逮捕された方の釈放を目指すことが考えられます。
①勾留決定が下される前
勾留決定に至る過程には、検察官による勾留請求、裁判官による勾留の判断という段階が存在します。
そこで、検察官や裁判官に対して、弁護人の立場から勾留が妥当でないという意見を述べるのが適当です。
具体的には、逃亡や証拠隠滅の可能性に欠けること、仮に勾留するとなると仕事や学校などの面で著しい不利益を被ることなどを主張します。
②勾留決定が下された後
まず、裁判官が下した勾留決定が妥当でなかったとして、上級の裁判所に改めて勾留の是非を問う不服申立てをするという手があります。
専門的には、「(勾留決定に対する)準抗告」と呼ばれます。
仮にこれが認められなければ「特別抗告」という手続もありますが、それが認められる可能性は著しく低いのが実情です。
③勾留延長の前後
事件の内容次第では、10日間の勾留では十分な捜査ができなかったとして、更に10日の範囲で勾留延長がなされることがあります。
こちらも検察官の請求と裁判官の決定を経て行われるものです。
こちらについても、①②と同様に意見の申出と不服申立てを行うことが可能となっています。
④起訴後
裁判を行うべく検察官が起訴をすると、被疑者は被告人と呼ばれるようになり、勾留されている場合はその期間は最低2か月伸びることになります。
その際には、裁判所に一定の金銭を預けて行う、保釈という身柄解放の手続をとることができるようになります。
保釈は預けた金銭が逃亡や証拠隠滅を抑制する手段となるため、上記①から③に比べて身柄解放を比較的実現しやすいというメリットがあります。
以上から分かるように、刑事事件において身体拘束の期間を縮めるには、勾留の当否をどれだけ争うかに掛かっているといっても過言ではありません。
そうした主張は弁護士の得意分野なので、勾留についてはいち早く弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、一日でも早い身柄解放を実現すべく勾留の当否を争います。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
女子トイレでの盗撮事件と勾留①
女子トイレでの盗撮と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県千葉市に住むAさんは、盗撮目的で市内にある公民館の女子トイレに侵入しました。
そして、個室に入ってしばらく息を潜めていたところ、隣の個室に人(Vさん)が入ってきました。
Aさんが個室の隙間からスマートフォンを差し向けると、たまたま画面に手が当たって動画の撮影終了ボタンをタップしてしまい、その音でVさんに盗撮していると気づかれました。
Aさんが女子トイレを出たところ、Vさんの悲鳴を聞いた男性に身柄を確保されました。
その後、Aさんは建造物侵入罪の疑いで千葉西警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留の阻止または短縮を目指して弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)
【女子トイレでの盗撮に成立する罪】
上記事例のように、女子トイレに侵入したうえで盗撮を行った場合、以下のとおり犯罪に当たる可能性があります。
①女子トイレへの侵入
男性(女性)が女子(男子)トイレに侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
まず、「正当な理由」とは、建造物侵入罪の違法性を阻却するような事情を指すと考えられています。
簡単に言うと侵入を正当化できるような事情であり、たとえば暴漢から隠れようとした場合、精神疾患の影響で自身の行為の意味が正しく認識できなかった場合などが考えられます。
次に、「人の看守する」とは、人や設備によって外部からの侵入を防止できるような措置がとられていることを指します。
ただ、四六時中厳重に管理がなされている必要はなく、誰も管理していない空き家などでない限りこの要件が否定されることはないかと思います。
また、「建造物」については、トイレや物置小屋などの小さな単位でも該当します。
最後に、「侵入」とは、管理者の意思に反する立入りを指すと考えられています。
通常、男性が盗撮目的で女子トイレに侵入することを管理者が許容しているとは考えられないでしょう。
以上の各要件を上記事例に当てはめると、Aさんには建造物侵入罪の成立が見込まれます。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
②女子トイレでの盗撮
一般的に、盗撮とはカメラなどで他人を密かに撮影する行為全般を指すかと思います。
犯罪として処罰の対象となるのは、そうした盗撮のうち特定の態様のものに限られています。
具体的には、下着や裸などの盗撮です。
そうした盗撮を処罰する条例として、第一に各都道府県が定める迷惑(行為)防止条例が挙げられます。
千葉県においても「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が定められています。
この条例は、「公共の場所又は公共の乗物」における「卑わいな言動」を禁止しており、「卑わいな言動」に下着や裸などの盗撮が含まれるとされています。
上記事例では、Aさんが公民館の女子トイレにおいてVさんを盗撮していることから、上記条例違反に当たると考えられます。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ちなみに、公共の場所や公共の乗物以外での盗撮(たとえば人の住居)については、軽犯罪法違反として拘留また科料が科される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、盗撮をはじめとする多種多様な刑事事件に関するご相談をお受けしております。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
高校生の恐喝罪と保護観察
高校生の恐喝罪と保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県富津市在住のAさん(17歳)は、友人2名と共に自宅近くのゲームセンターへ行ったところ、中学生と思しき男性Vさんが1人でいるのを見かけました。
そこで、Aさんは友人らと共にVさんを囲み、「なあ、痛い目見たくなかったら金貸してくんね。」などと言って肩を抱きました。
すると、Vさんは財布から1000円札を3枚出したため、Aさんはそれを受け取りました。
後日、Vさんが両親に相談したことをきかっけに事件が公となり、Aさんらは恐喝罪の疑いで富津警察署にて取調べを受けることになりました。
そのことを知ったAさんの両親は、弁護士に保護観察について聞いてみました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪は、暴行または脅迫により他人から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
恐喝罪について規定した刑法249条を見ると、1項に「財物」という記載が、2項に「財産上不法の利益」という記載がそれぞれ見受けられます。
簡単に言えば、前者は形あるもの、後者は形なきものです。
馴染みがないのは「財産上不法の利益」の方かと思いますが、こちらはたとえばサービスの提供や債務の免除などが挙げられます。
恐喝罪が成立するのは、①暴行または脅迫の存在、②①による相手方の畏怖、③畏怖した状態での財産の交付、の全てを満たす場合です。
①の暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するには至らない、比較的軽度のものを指すと考えられています。
ただし、「暴行」は殴る蹴るといった典型的なものにとどまらず、不法な有形力の行使全般(たとえば胸倉を掴むなど)を指すと解釈されています。
ですので、殴る蹴るといった典型的な暴行を加えていなくとも、恐喝罪が成立する余地はあるでしょう。
ちなみに、暴行・脅迫の程度が著しければ、恐喝罪よりも重い強盗罪に当たる余地が出てきます。
強盗罪に当たる可能性が高いケースとしては、暴行・脅迫の際に凶器を用いた場合が考えられます。
【少年事件における保護観察】
20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は少年事件として扱われ、成人による通常の刑事事件とは異なる手続に付されることになります。
少年事件の最大の特色は、最終的に行われるのが刑罰ではなく保護処分という少年の発達に資する措置である点です。
保護処分は家庭裁判所での審判を通して行われるものであり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察の3つがあります。
保護観察とは、保護観察所という機関の助力を受けながら、家庭など本来の生活圏において少年の更生や育成を図る処分です。
上記①②との明らかな違いは、少年に本来の生活圏を離れて特定の施設で生活させる必要がない点です。
経過を見守るという点において、通常の刑事事件における執行猶予に類似のものと言えます。
観護措置を目指すに当たっては、家庭内などでも十分に少年の健全な育成が目指せることを積極的にアピールする必要があります。
犯した罪の重さだけでなく保護者の監督能力なども非常に重要であり、弁護士の助言を受けつつ真摯に対応することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察をはじめとする各種保護処分について丁寧にご説明します。
お子さんが恐喝罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
飲酒運転で執行猶予
飲酒運転と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、自他ともに認める酒豪であり、週末に居酒屋を回って酒を飲むのを趣味にしていました。
Aさんは飲酒運転について「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考えており、過去に2回飲酒運転をして罰金刑を受けていました。
ある日、Aさんは千葉県千葉市の居酒屋で酒を飲んだあと、「ばれなければいいや」と思って飲酒運転をしました。
そうしたところ、千葉南警察署の警察官から声を掛けられ、呼気検査の結果が0.4だったことから道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、裁判になる可能性があること、そうなった場合は執行猶予を目指すべきであることを伝えました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転については、道路交通法に禁止規定と罰則が置かれています。
まず、道路交通法65条は、「酒気帯び運転等の禁止」と題して「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
この規定が飲酒運転の禁止を定めたものです。
一方、飲酒運転の罰則については、飲酒運転の具体的な内容に応じて以下のとおり2パターン存在します。
第一は、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。
酒気帯び運転は、身体に一定程度以上のアルコールを保有した状態で運転した場合に成立するものです。
具体的なアルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、令和元年12月現在は①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
実際の飲酒運転のケースでは、②の基準の方が用いられるかと思います。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
第二は、「酒酔い運転」と呼ばれるものです。
酒酔い運転は、「酒に酔つた状態」、すなわち「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合に成立します。
これに当たるかどうかは、基本的に飲酒運転を検挙した警察官などが視認することになります。
たとえば、道路の白線の上を真っすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などの事情を参考にすると考えられます。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
【執行猶予獲得の可能性を高めるには】
飲酒運転が発覚した場合、初犯であれば基本的に略式命令(法廷ではなく書面で裁判を行う簡易な手続)による罰金刑で終わると見込まれます。
ですが、上記事例のAさんのように回数が重なると、懲役刑を科すことを見越して検察官が裁判を行う可能性が出てきます。
そうなった場合、刑務所への収容を回避するには、やはり執行猶予を目指すことが重要となります。
執行猶予に付するかどうかは、事件の内容、被告人の反省の程度、更生の可能性などの様々な事情を考慮して決めるものです。
飲酒運転をして裁判を受けるケースでは、Aさんがそうであるように、それ以前にも飲酒運転をして刑罰を受けた経歴があるのが殆どだと考えられます。
そうなると、率直に言って裁判官は反省の程度や更生の可能性につき否定的な評価を下すことが当然予想されます。
そうした状況下で執行猶予の可能性を高めるのであれば、今回の件を真摯に受け止めていること、更生の余地があることをよりしっかりとアピールする必要があるでしょう。
そうはいっても、裁判に向けた方策を闇雲に行うことはおすすめできません。
執行猶予を目指すなら、まずは弁護士に相談するのが賢明と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して尽力します。
飲酒運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介