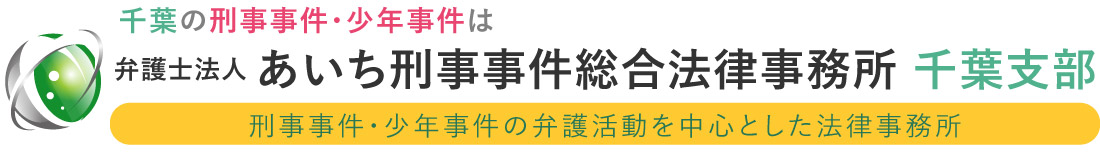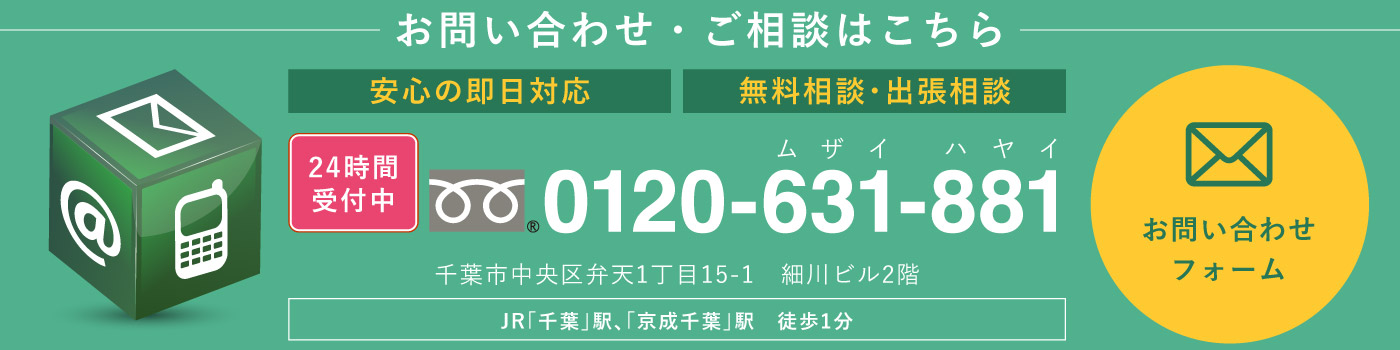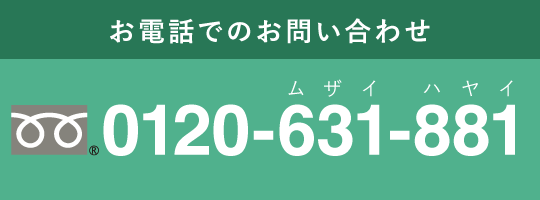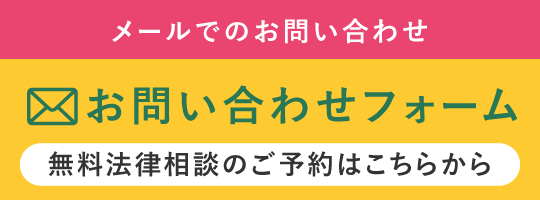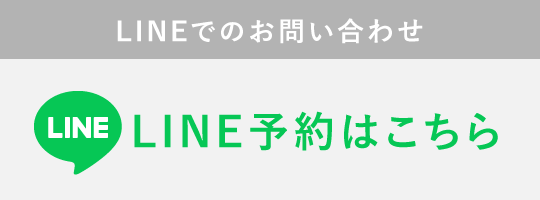Archive for the ‘刑事事件’ Category
死体遺棄罪の捜査の流れ
死体遺棄罪の捜査の流れ
死体遺棄罪の捜査の流れについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県八千代市に住むXさんは、就職氷河期の影響で就職することができず、自宅でいわゆる引きこもりの生活を送っていました。Xさんは現在、今年で75歳になる父親と2人暮らしで、母親は、幼いころに亡くしていました。
Xさんは、数十年間引きこもりを続けており、その間働いたことはありません。生活の糧は、父親の年金のみでした。
ある日、Xさんの父親が病気になり寝込んでしまいました。しかし、Xさんは特に看病することもなく普段通りの生活をつづけました。
Xさんが最近父親の姿を見ないなと思い、寝室に向かうと、Xさんの父親が亡くなっていることに気が付きました。
Xさんは、このまま父親が亡くなってしまったことが発覚すれば年金をもらえなくなり、生活することができなくなると考え、父親が亡くなったことを隠し、年金をもらい続けるため、父親の遺体を自宅の寝室に放置しました。
ところが、周辺住民からの「異臭がする」との通報を受けた千葉県警八千代警察署の警察官が自宅を訪ね、事件が発覚、Xさんはそのまま逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
【死体遺棄罪について】
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されます。要するに、きちんとした手続きや常識的な死体の取り扱いといえるかという観点から判断し、死体の取り扱いとして妥当ではないとみなされる場合に成立する犯罪です。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出や葬儀などを行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置した場合、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると解されています。
そのため、上記事例のXさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科される可能性があります。
犯罪と聞くと積極的に何かする場面を想定しがちですが、不作為犯といって、「ある行為を行うべき人が、行うべき行為を、行わなかった」場合にも犯罪となる余地があると法律上考えられており、死体遺棄罪の場合、このケースのように、唯一の同居人であったXさんは、「死体をきちんと処理すべき人」として、「きちんと死体を処理すべき」であったのに、「きちんと処理を行わなかった」として、犯罪が成立する可能性があります。
ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。
なお、死体遺棄罪が成立する場合には、基本的にはこちらが優先的に適用されることになります。
【捜査の流れ】
死体遺棄罪の疑いで逮捕されると、捜査の流れは通常以下のとおりになると考えられます。
①警察官が被疑者の弁解を録取し、必要に応じて48時間以内に検察庁へ事件を送致する
②検察官も被疑者の弁解を再度、録取し、身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官が被疑者の勾留請求を行うべきか判断する
③検察官が勾留請求を行った場合、被疑者は裁判所に連行され、裁判官から犯罪事実に関する陳述の聴取などがなされる(勾留質問)
④裁判官は、検察官から送られた記録と勾留質問における陳述を考慮し、勾留が妥当だと考えれば、勾留決定を行う。
⑤勾留決定されると、被疑者はまずは、10日間(捜査の進捗次第では最長20日間)拘束され、その期間に取調べや現場検証などが行われる
⑥勾留期間中に検察官が起訴するかどうか決定し、起訴されれば勾留の期間が2か月(その後1か月ごとに更新)延長される
以上から分かるように、逮捕から起訴までの期間(③~⑤)は、長くとも23日間とそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は、被疑者の釈放を目指す活動と、最終処分軽減に向けた活動をメインに行動することになります。
上記事例では異なりますが、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
仮に、殺人罪を疑われた場合、困難な事件対応を迫られる可能性があります。弁護士を依頼し、より慎重に取り調べに対応していく必要が出てくるでしょう。
逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けても、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、お申込みから遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
(無料法律相談のご案内はこちら)
傷害致死罪と正当防衛
傷害致死罪と正当防衛
傷害致死罪と正当防衛について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
会社員のAさん(25歳・女性)は,仕事帰りに千葉県鎌ヶ谷市内の駅で電車を待っていたところ,泥酔した様子のVさん(推定50代・男性)に声をかけられました。
Vさんは近づいてきてAさんの身体を触ってきたため,Aさんは「やめてください。警察呼びますよ」といってVさんと距離を取りました。
それでもVさんがしつこく絡んできて,Aさんの肩を抱いて胸を触ってきたため,Aさんは咄嗟にVさんの肩を腕で軽く押しました。
そうしたところ,Vさんがバランスを崩して線路に落ち,ちょうどホームに到着した列車と衝突しました。
これによりVさんは即死し,Aさんは鎌ヶ谷警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は,傷害致死罪が成立する可能性があることを指摘したうえで,正当防衛を主張する余地があることを説明しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は,殺人罪と同様,他人を死亡させた場合に成立する可能性のある罪です。
殺人罪との違いは,殺人の故意をもって行為に及んだかどうかという点にあります。
つまり,他人を殺すつもりはなかったものの,故意に暴行を加えるなどして結果的に死亡させた場合に,傷害致死罪が問題となります。
ちなみに,故意ではなく過失(簡単に言えば不注意)により他人を死亡させた場合,傷害致死罪ではなく過失致死罪として処罰されます。
今回のケースでは,弁護士が指摘しているように,結論として傷害致死罪の構成要件に当たる(この表現については後述)可能性があります。
ただ,AさんはVさんに傷害を負わせるつもりはなく,せいぜいVさんを引き離そうという暴行の故意しかなかったと考えられます。
このことから,傷害致死罪に当たるという結論は妥当でないようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ですが,実務上は傷害致死罪の成立が認められる傾向にあります。
その理由としては,故意に暴行を行っている時点で非難を受けるべき立場にあり,それにより生じた結果についてはきちんと責任を負うべきだからだと説明されます。
以上から,Aさんに傷害罪の故意がなかったからといって,傷害致死罪の成立が否定されるわけではないということになります。
そして,Aさんの行為とVさんの死亡との間には因果関係が認められることが見込まれます。
そうすると,Aさんの行為は傷害致死罪の構成要件に当たるでしょう。
【正当防衛の主張】
仮に犯罪に当たる行為をしたとしても,一定の事情があることを理由に犯罪の成立が否定されることがあります。
今回のケースでは,Aさんが性被害から逃れようと行為に及んでいることから,正当防衛の成立により行為の違法性が否定されないか検討する余地がありそうです。
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
今回のケースで最も問題となりうるのは,Vさんの死亡という極めて重大な結果を招いたAさんの行為が,Aさんの権利・利益を守るうえで果たして適当だったかという点でしょう。
本来,権利・利益の違法な侵害に対する救済は国家が行うべきであり,正当防衛のように自ら救済を実現するのは違法とされています。
このような考えから,いくら正当防衛の名目であっても,不必要に他人の権利・利益を侵害するのは許されていません。
正当防衛について定めた刑法36条1項が「やむを得ずにした行為」であることを要求しているのは,正にこの考えを明言していると言えます。
それでは,Vさんの死亡を招いたAさんの行為は「やむを得ずにした行為」には当たらないのでしょうか。
結論から言うと,Aさんの行為は「やむを得ずにした行為」に当たる可能性があります。
ここでいう「やむを得ずにした行為」とは,結果ではなく行為が相当な限度(「必要最小限」などとも表現されます)であることを要求していると考えられているからです。
今回のケースにおいて,Aさんの行為はVさんの肩を腕で軽く押すというものであり,AさんがVさんを線路に突き落として轢死させようなどと考えていたとも思えません。
そうすると,Aさんの行為は正当防衛を達成するうえで必要最低限のものであり,たまたま重大な結果が生じたに過ぎないと評価できます。
以上より,Aさんの行為は「やむを得ずにした行為」であり,正当防衛としてAさんに傷害致死罪は成立しない余地があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、正当防衛のような難解な概念も丁寧に説明いたします。
傷害致死罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
監禁罪で執行猶予
監禁罪で執行猶予
監禁罪と執行猶予について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Xさん夫婦は千葉県花見川区に暮らしており、今年で30歳になる息子がいました。息子は、統合失調症を患っており、ときどき大声を上げ暴れることがあり、Xさん夫婦も手を挙げられ、怪我をすることがありました。
ある日、夫婦警察から連絡があり、息子が暴れ、喧嘩をしているとのことで、警察署に息子を迎えに行ったことがありました。
Xさん夫婦は、「今後も息子が外出中に暴れ、人様を傷つけてしまったら大変だ」と考え、息子を自宅の部屋に隔離し、部屋の外にカギを付け、息子の行動を管理するようにしました。
息子はしばらくは、落ち着いて生活していましたが、1週間が経過したころ、息子が部屋の中で大声を出し暴れまわりました。その声を聞いた近所の人が警察に通報し、千葉県警千葉北警察署の警察官がやってきました。
警察官は、様子を見せてほしいと部屋の中に入り、息子の部屋の鍵を確認しました。そこで、Xさん夫婦は、監禁罪の疑いで警察から捜査を受けることになりました。
(フィクションです。)
【監禁罪について】
刑法第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
監禁罪とは、正当な理由なくして人の場所的移動の自由を奪う犯罪です。
監禁罪における「監禁」とは、一定の場所から脱出できないようにし、場所的移動の自由を不可能または困難にする行為です。
たとえば、部屋に鍵をかけて出られなくするなどが典型例ですが、車に乗せたうえで、本人が「降りたい」という意思を明確にしているにもかかわらず、降ろさない場合にも成立します。
ちなみに、監禁罪においては、「監禁」をどう定義付けするかという点で法律の解釈上の争いが存在します。
そもそも、監禁罪は、「人が移動することの自由」を保護するための法律であり、「人が移動することの自由」をどう考えるかという点で、大きく分けて2つの解釈が存在します。一つ目が、「可能的自由説」で、もう一つが「現実的自由説」といいます。前者は、移動の自由を最大限保護しようとするもので、もし人が移動したいと思った時その状況が阻止されていればそれで犯罪の成立を認めます。
他方で、後者の場合、実際に人が移動したいと思った時にその状況が阻止されていた時に限り犯罪の成立を認めます。
具体的に問題になる場面としては、たとえば、「人が寝ている最中に部屋の外から鍵をかけた場合に犯罪が成立するかどうか」といったシーンが想定されます。前者であれば寝ていたとしても、「起きて移動したいと思う可能性がある」ので、この場合にも犯罪は成立します。
他方、後者の場合、「実際は寝ていて移動したいと思わなかった」以上、犯罪は成立しません。
【執行猶予を目指すには】
執行猶予付きの判決とは、被告人に対し、懲役刑を課しながら、一定期間社会内で更生のチャンスを与え、その期間被告人が何らかの犯罪行為を犯すことなく期間が経過した場合には、懲役刑を免除するという判決であり、懲役刑の判決を受けたとしても、刑務所に行かず引き続き社会内で生活を行うことができる判決です。
執行猶予付きの判決になるかどうかは、具体的な事案次第ではありますが、初犯でなおかつ監禁の時間もそう長くなかった場合、監禁罪で有罪判決を受けたとしても執行猶予付の判決を獲得できる可能性があります。
刑の全部の執行猶予を得るためには、法律上、言い渡された刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金でなければなりません(刑法25条1項)。
この条件に該当する場合には、常に執行猶予付きの判決が言い渡されるというものではなく、事件の内容、動機、被告人の犯行に至った経緯、反省状況等様々な事情を考慮し、裁判官が執行猶予付きの判決がふさわしいと判断した場合にのみ、執行猶予付きの判決となります。
執行猶予を目指すのであれば、事件の内容次第の部分もありますが、被告人に有利な情状をきちんと主張し、執行猶予付きの判決がふさわしいことを示していくことが必要となるでしょう。
執行猶予付きの判決を得ることができなければ、刑務所に収容されることになり、その後の人生に大きな影響を及ぼすと言っても決して過言ではありません。
執行猶予付きの判決の可能性を少しでも高めるため、弁護士に事件を依頼し、充実した弁護活動を行ってもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の経験豊富な弁護士が、執行猶予を目指してできる限りの弁護活動を行います。
もし監禁罪の疑いで逮捕されたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、執行猶予に向けた最適な弁護活動が行えるよう、弁護士が迅速に初回接見を行います。
(無料法律相談のご案内はこちら)
脅迫罪で釈放
脅迫罪で釈放
脅迫事件で釈放を目指すケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Xさんは大学3年生で同じサークルの彼女がいました。ある日、大学の講義を受け終わり、昼食を食べるために移動していると、彼女が別の男性と一緒に食事しているところを見つけました。
その場では声をかけなかったXさんでしたが、昼食後に彼女にLINEを送り、「今日何していたの?」と声をかけると、「今日はバイトで忙しく大学に行かなかった」と言われました。Xさんは、彼女に嘘をつかれたことに憤りを感じましたが、それ以上は言及することなく、やり取りは終わりました。
それから、1週間後、Xさんは同じ時間帯に彼女がまたあの男と一緒にいるのではないかと思い、彼女を探していると、案の定その男性と一緒にいるところを見つけました。Xさんは、彼女が言い逃れできないよう、その場で彼女に「何してるの?」と話しかけました。彼女は、友人と食事をしていると取り繕いましたが、Xさんは「恋人がいるのに他の男と食事をするなんて考えられない」と怒り、彼女を連れ出し、彼女に対し、「先週も同じ男と食事をしていただろう。その時嘘をつかれたことが許せない。また同じことがあったらぶっ殺すからな」と言って彼女の髪を掴んで引っ張りました。
その日の夜LINEでXさんは彼女に対し、「さっき言ったことは本当だからな。あの男と会ってやがったら本気でぶっ殺す。お前の家族もぶっ殺すからな。」とメッセージを送りました。彼女は、また暴力を振るわれるのではないかと不安になり千葉中央警察署に駆け込んだところ、Xさんは、同警察署の警察官により、脅迫罪で通常逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
【脅迫罪について】
刑法第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
人に恐怖心を抱かせるような内容の害悪を告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法222条は、被害者本人に害を加える旨の脅迫だけでなく、被害者の親族に害を与える旨の脅迫についても定めています。
そのため、上記事例彼女に対し、彼女の家族にも脅迫すると脅している点についても脅迫罪が成立することになります。
また、脅迫罪における「脅迫」は、相手を「畏怖」させるものでなければなりません。同じ文言であっても、シチュエーションや、言動を発する相手によって、「畏怖」するかどうかは異なります
たとえば、仲の良い友人とお酒を飲んでいるときに気やすく話す「殴るぞ」という言葉と不良集団に絡まれて「殴るぞ」と言われた場合の言葉では意味が違うということです。
上記事例では、Xさんが彼女に対し、「さっき言ったことは本当だからな。あの男と会ってやがったら本気でぶっ殺す。お前の家族もぶっ殺すからな。」と伝達しています。
Xさんがそのまえに髪の毛を掴んで暴行を加えてきた状況や、家族にまで言及してきたことを考慮すると、上記文言は少なくとも暴行を振るわれるのではないかと「畏怖」するに足りるものと判断される可能性が出てきます。
【釈放の可能性】
脅迫罪の疑いで逮捕されると、その後勾留されることで最長23日間もの期間、身柄を拘束される可能性が出てきます。
こうした長期の身柄拘束が行われると、当然ながらその間会社や学校などに行くことはできなくなり、著しい不利益を被ることになりかねません。
刑事事件において、釈放が期待できるタイミングというのは何度かあります。
大きく分けると、①勾留決定時、②勾留決定から起訴時点まで、③起訴後の3つになります。
上記事例のケースにおいては、①の勾留決定時か、被害者の方との示談が成功すれば、②の段階での釈放も期待できます。
日本では勾留される確率が比較的高くなっており、①の段階での釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼し、弁護士から、勾留決定時までに加害者側の事情をまとめ勾留請求を行う検察官と、勾留決定を行う裁判官に対し、「意見書」を提出することが有用です。
他方、仮に「意見書」がうまくいかなかった場合にも、早急に被害者との示談を成立させることができれば、早期の身柄解放も期待できます。
身柄の拘束は、仕事や学校に行けないといった現実的な不利益はもとより、行動を管理、監視されているため、肉体的精神的な負担も小さくありません。もちろん、罪を犯してしまった場合には自業自得とも言えますが、必要以上の負担とならないよう身柄解放に向けて動くことも必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕されている方の釈放に向けて充実した弁護活動を行います。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、早期釈放に向けて迅速に初回接見を行います。
(無料法律相談のご案内はこちら)
体罰で示談
体罰で示談
体罰をして示談するケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Xさんは、千葉県千葉市の公立中学校で英語の授業を担当している教員で、教師になってから3年目でした。
Xさんの勤める中学校は、素行のよくない生徒が少なくなかったため、授業中集中して授業を受ける生徒の数の方が少なく、多くの生徒はスマホをいじっていたり、会話をしたり、授業と関係ない作業を行っていました。
そういった状況でも普段は、淡々と授業を行ってきたXさんでしたが、この日は体調が悪かったこともあり、生徒に対し、イライラが募っていきました。
この日、Xさんは、普段と違って、生徒に対し、スマホを使用しないよう注意しました。すると、ある生徒がXさんに反抗し、そのままスマホをいじり続けていました。
Xさんは突発的な怒りから、スマホをいじっていた生徒の手をたたき、スマホを取り上げました。
クラスは大騒ぎになり、被害生徒の両親が被害届取下げを提出、その結果、Xさんは、千葉県警千葉中央警察署の警察官により傷害事件の犯人として取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
【体罰と刑事事件】
学校というのは、生徒に対して心身の発達段階に応じた教育・指導を行い、個人の健全な育成を図る場です。
そうした学校の役割から、学校教育法11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と定めています。
この懲戒は当然ですが、「教育上必要があると認められるとき」にしか行えません。
そして、生徒に対して暴力を振るったりする「体罰」は、いかなる場合においても許されません。
では、どういった行為が、「懲戒」として許され、どういった行為が「体罰」として許されないのでしょうか。
文部科学省はホームページ上で参考事例と称し、具体例を挙げています(文部科学省HP 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例参照)。
具体的には、「体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける」、「授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする」行為は、体罰として許されない行為であるが、
他方、「授業中、教室内に起立させる」、「立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる」行為は懲戒の範囲として許されると考えられています。
体罰が発覚した場合、生徒の親をはじめとする関係者から責任を追及されたり、人事権者から懲戒処分を下されたりする場面はよく見られます。
ところが、体罰は、懲戒処分で済むとは限らず、当然ですが、それが、犯罪に当たる行為であれば、懲戒処分に加えて、刑事責任を追及される可能性があることも忘れるべきではありません。
暴行を加えれば、暴行罪や傷害罪などになる可能性があり、義務のないことを無理やり行わせれば強要罪になることもあります。
以上のような犯罪が成立する場合の刑事責任の追及は、先ほど挙げた懲戒処分などとは別であることには注意が必要です。
謝罪や依願退職などを行い、学校内での処分を免れたとしても、刑事手続きが終了するとは限りません。
特に、被害者やその両親が被害届を出したとなると、刑事事件として扱われる可能性は高まるでしょう。
【示談で解決するには】
体罰が刑事事件となった場合には、通常の刑事事件と同じく示談は重要な弁護活動になります。
体罰という名前がついていたとしても、傷害ないし暴行事件という実態に変わりはないからです。
ただ、体罰が問題になるケースにおいては、当事者が教員と生徒の関係にあるという特殊性があります。
保護者が交渉の窓口になるため、これまでの保護者と先生との人間関係が示談交渉に直接的に関係してくることになります。被害届が出てしまっている場合には、保護者の感情が悪化している恐れがあるため、示談交渉は難航するおそれがあります。
そうしたケースでは、少なくとも弁護士に示談交渉を委ねる必要があるでしょう。
加害者側の先生としては、たとえ保護者の連絡先を知っていたとしても、安易に接触することにより逮捕の可能性が高まることはもとより、交渉そのものも感情面が先に立ちうまくいかない可能性が高まります。
示談交渉は、感情がこじれると長期化、難化する可能性が高まるため、最初から弁護士を入れたうえで交渉に臨む方が示談成功の可能性は高まるでしょう。
示談が成立すれば不起訴や執行猶予となることも十分考えられます。
自己の体罰を反省して再び前を向くためにも、示談は弁護士に依頼して不起訴や執行猶予の可能性を少しでも高めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、体罰をしてしまった方のための示談交渉に手を尽くします。
もし体罰をしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、示談交渉をはじめとする多様な弁護活動に取り組みます。
(無料法律相談のご案内はこちら)
詐欺事件で保釈請求③
詐欺事件で保釈請求を行うケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは,知人であるBさんからの誘いを受け,あるバイトをすることになりました。
そのバイトの内容は,「民事訴訟最終通達書」と題する文書を葉書に印刷し,その葉書を投函するというものでした。
葉書に印刷された文書は「訴訟告知センター」という架空の団体名義(押印つき)であり,民事訴訟が提起されていること,記載してある連絡先に連絡しなければ強制執行が行われることなどが書かれていました。
そして,実際にこの葉書を見て連絡した人が,電話の相手に言われるがまま口座に金銭を振り込むという詐欺事件も起きていました。
Aさんは,バイトが詐欺に関するものだとうっすら気づいていましたが,時給が良いという理由で続けていました。
そうしたところ,Aさんは有印私文書偽造罪の疑いで我孫子警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は,今回の件で詐欺罪に問われる可能性を伝えたうえで,身柄解放の手段として保釈について説明しました。
(フィクションです。)
【保釈制度の概要】
「保釈」という言葉は,たとえば芸能人が逮捕された事件に関するニュースなどで耳にすることがあるのではないかと思います。
今回の記事では,保釈について詳しく見ていきます。
保釈とは,一定額の金銭を裁判所に預けるのと引き換えに,少なくとも判決が下されるまで身体拘束を解いてもらうという手続です。
逮捕された直後から行えるわけではなく,起訴されて被告人となった段階ではじめて可能となるものです。
保釈に至るまでの流れは,①裁判所に対する保釈請求,②裁判所による保釈の許可,③保釈保証金の納付,④保釈,というかたちになっています。
まず,保釈の許可を受ける前提として,裁判所に対して保釈請求をしなければなりません。
請求を受けた裁判所は,保釈請求書や事件記録の内容に基づき,法律上保釈を許可しても差し支えないか審査することになります。
もし裁判所が保釈を認めてもよいと判断した場合,保釈の許可決定と保釈保証金の額を伝えられます。
その伝達を受けたら,裁判所にて保釈保証金の納付の手続を行い,それが正常に処理されてはじめて保釈に至ります。
保釈の際に預けた保釈保証金は,被告人が逃亡や証拠隠滅などの特定の行動に及ぶと没収されるおそれがあります。
そして,保釈保証金は個々人の経済力などを考慮して高額と感じるような金額が設定されるため,被告人としては逃亡や証拠隠滅などを図りづらくなります。
このようなかたちでいわば担保が存在しているからこそ,逃亡などに及ぶ可能性が低いとして身柄解放が比較的認められやすくなっているのです。
起訴前の段階では身柄解放の実現が難しい事案でも,保釈による身柄解放であれば実現する可能性があるということは珍しくありません。
上記のとおり,保釈保証金は没収のリスクにより被告人の逃亡などを防ぐ役割を果たします。
そのため,被告人が逃亡などに及ぶことなく無事に判決が下された場合には,一定の期間を置いて最終的に返還されます。
この点は,たとえ被告人が刑務所へ入ることになったとしても変わりません。
もし保釈保証金の捻出が難しければ,保釈支援協会という機関を頼ることもできます。
ですので,お金を支払えないからという理由で早々に保釈を諦めるのはもったいないと言っても過言ではないでしょう。
以上のとおり,今回の記事では保釈について取り扱いました。
ですが,今回述べた事柄は保釈制度の一部に過ぎず,このほかにどうしても法律上の難解な点がつきまとうことになります。
もし保釈に関して何か疑問点などございましたら,お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、個々のケースに応じて保釈に関するご説明を致します。
ご家族などが詐欺事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
詐欺事件で保釈請求②
詐欺事件で保釈請求を行うケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
このテーマは前編・中編・後編と分かれており,前編と中編(今回)で詐欺事件を,後編で保釈請求を取り扱います。
【ケース】
Aさんは,知人であるBさんからの誘いを受け,あるバイトをすることになりました。
そのバイトの内容は,「民事訴訟最終通達書」と題する文書を葉書に印刷し,その葉書を投函するというものでした。
葉書に印刷された文書は「訴訟告知センター」という架空の団体名義(押印つき)であり,民事訴訟が提起されていること,記載してある連絡先に連絡しなければ強制執行が行われることなどが書かれていました。
そして,実際にこの葉書を見て連絡した人が,電話の相手に言われるがまま口座に金銭を振り込むという詐欺事件も起きていました。
Aさんは,バイトが詐欺に関するものだとうっすら気づいていましたが,時給が良いという理由で続けていました。
そうしたところ,Aさんは有印私文書偽造罪の疑いで我孫子警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は,今回の件で詐欺罪に問われる可能性を伝えたうえで,身柄解放の手段として保釈について説明しました。
(フィクションです。)
【今回のケースにおいて問題となる行為】
今回のケースで問題となりうるのは,①葉書の作成および投函,②葉書を受け取った者による金銭の振込,の2点です。
今回の記事では,このうち②について取り扱います。
【②について~詐欺罪成立の可能性~】
まず,今回のケースで問題となっている葉書は,民事訴訟が提起されていること,記載してある連絡先に連絡しなければ強制執行が行われることなどが書かれているものです。
そして,この葉書を見て連絡した人に対し,電話担当が金銭の振込を促し,これにより葉書を見た人が金銭を振り込んでいると考えられます。
このような行為について,詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は,他人を欺いて財産を受け取った場合に成立する可能性のある罪です。
具体的に言うと,①他人を欺く行為(「欺罔行為」と呼ばれます)により,②その他人が錯誤に陥り,③錯誤に陥った状態で財産を交付することが詐欺罪の要件です。
今回のケースにおける葉書の郵送と電話での案内は,民事訴訟が提起されており,指定された口座に金銭を振り込まなければ強制執行などの不利益を被ると他人に誤信させる内容のものと考えられます。
そうすると,金銭を支払う必要があるように装う点で,①の他人を欺く行為に当たると言えます。
更に,振込を行った人は,葉書と電話を受けてそのように誤信したと考えられるため,②の錯誤も認められるでしょう。
そして,これにより振込を行った以上,③の財産の交付はあったと評価できます(厳密に言うとこの点はもう少し検討が必要ですが,難解であるため割愛します)。
よって,やはり詐欺罪が成立する可能性があります。
それでは,Aさんも詐欺罪の責任を負うことになるのでしょうか。
Aさんは葉書を作成して投函しただけで,金銭を振り込ませるような行為は行っていないことから,せいぜい詐欺未遂罪の責任を負うに過ぎないようにも思えます。
ですが,結論としては,Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
今回のように複数人が互いに通じ合って犯行に及び,なおかつそれぞれが重要な役割を果たしている場合,犯罪に関与した者は「共同正犯」(刑法60条)という関係に当たる余地が出てきます。
仮に共同正犯の関係に立つとすると,たとえ一部の行為しかしていなくても,全部の行為をおこなったものとして責任を負うことになるのです。
したがって,Aさんは他の者が行った行為についても責任を負うおそれがあるということになります。
前回の記事で確認したように,今回のケースではAさんに有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪も成立する可能性があります。
これに詐欺罪が加わるので,事件としては重い部類に属すると評価できます。
ちなみに,文書偽造罪,偽造文書行使罪,詐欺罪はそれぞれ牽連犯(前回の記事参照)の関係に立つとされています。
そのため,1個の罪とみなされて1個の刑が科されることが予想されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、比較的なじみのある犯罪である詐欺罪についても詳しく説明いたします。
ご家族などが詐欺事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
詐欺事件で保釈請求
詐欺事件で保釈請求を行うケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
このテーマは前編・中編・後編と分かれており,前編(今回)と中編で詐欺事件を,後編で保釈請求を取り扱います。
【ケース】
Aさんは,知人であるBさんからの誘いを受け,あるバイトをすることになりました。
そのバイトの内容は,「民事訴訟最終通達書」と題する文書をはがきに印刷し,そのはがきを投函するというものでした。
はがきに印刷された文書は「訴訟告知センター」という架空の団体名義(押印つき)であり,民事訴訟が提起されていること,記載してある連絡先に連絡しなければ強制執行が行われることなどが書かれていました。
そして,実際にこのはがきを見て連絡した人が,電話の相手に言われるがまま口座に金銭を振り込むという詐欺事件も起きていました。
Aさんは,バイトが詐欺に関するものだとうっすら気づいていましたが,時給が良いという理由で続けていました。
そうしたところ,Aさんは有印私文書偽造罪の疑いで我孫子警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は,今回の件で詐欺罪に問われる可能性を伝えたうえで,身柄解放の手段として保釈について説明しました。
(フィクションです。)
【今回のケースにおいて問題となる行為】
今回のケースで問題となりうるのは,①はがきの作成および投函,②はがきを受け取った者による金銭の振込,の2点です。
今回の記事では,①の行為につきどのような犯罪が成立する可能性があるか順に見ていきます。
【①について~文書偽造罪成立の可能性~】
Aさんは,「訴訟告知センター」という名義の文書を作成し,それをポストに投函しています。
このような行為につき,文書偽造罪と偽造文書行使罪が成立する可能性があります。
文書偽造罪は,一定の内容の文書を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
文書偽造罪における「偽造」とは,①作成権限のない者が文書を作成することを指すと考えられています。
また,このことを別の観点から説明した定義として,②「作成者と名義人の人格の同一性を偽ること」を指すとされることもあります。
今回のケースでは,結論から言うと「偽造」に当たる可能性があると言えます。
Aさんはバイトの業務として指示のもと「訴訟告知センター」を名乗っているので,この名義ではがきを作成することにつき作成権限はあるように思えます。
しかし,文書偽造罪というのは文書に対する社会一般の信頼を保護する罪なので,文書の名義についてはその名義が持つ意味なども重要になると考えられます。
そう考えたとき,今回問題となったはがきの名義人は,「訴訟に関して一定の対応を行うことが許されている『訴訟告知センター』という団体」だと言えます。
一方,はがきの作成者であるAさんを含め,「訴訟告知センター」という団体名を名乗っている者に,訴訟に関して一定の対応を行うことは許されていません。
こうした場合については,作成者と名義人が異なるとして「偽造」に当たると判断されることが予想されるのです。
Aさんによるはがきの作成が「偽造」に当たるとすると,はがきの内容などからして,Aさんには有印私文書偽造罪が成立すると考えられます。
更に,作成したはがきを郵送することで他人が閲覧できる状態にしたことから,更に偽造有印私文書行使罪の成立もありえます。
有印私文書偽造罪の法定刑は3か月以上5年以下の懲役であり,偽造有印私文書行使罪の法定刑も偽造罪と同様です。
これらの罪は,手段と結果の関係に立つとして54条1項が適用されます(こうした関係は「牽連犯」と呼ばれます)。
そのため,それぞれの罪につき別々に刑が科されてそれが合算されたりせず,1個の罪を犯した場合と同様に1個の刑が科されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、個々のケースを丁寧に聞き取ったうえで文書偽造罪の成否をお伝えします。
ご家族などが詐欺事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
強要罪と逮捕
強要罪と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【ケース】
Aさんは,千葉県松戸市のコンビニで弁当を買った際,従業員のVさんが弁当を雑に扱ったことに怒りを覚えました。
Aさんがそのことを指摘しましたが,Vさんはぼそぼそと「すんません」などと口走っただけでした。
それに激昂したAさんは,Vさんに怒鳴り散らしたうえで,「お前土下座しろや。せんとどうなるかわかっとんのやろな」と詰め寄りました。
これを受けて恐怖心を抱いたVさんは,Aさんに対して土下座をしました。
後日,Vさんがコンビニの店長に事の詳細を話したのがきっかけで,松戸東警察署が強要罪の疑いで捜査を開始しました。
後日,Aさんは松戸東警察署から呼び出しを受けたため,逮捕のことなどを含めて出頭前に弁護士に相談しておくことにしました。
(フィクションです)
【強要罪について】
刑法第二百二十三条
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
他人に義務のない行為を無理やり行わせたり,本来であれば他人が自由に行える行為を無理やり妨害したりした場合,強要罪に当たる可能性があります。
強要罪の具体的な成立要件を挙げると,①暴行または脅迫,②相手方による義務のない行為または権利の不行使,③①と②との間の因果関係,です。
強要罪を疑われた事件の中で記憶に新しいものとして,今回のケースのようないわゆる土下座強要が挙げられるかと思います。
今回のケースでは,AさんがVさんに対し「お前土下座しろや。せんとどうなるかわかっとんのやろな」と発言し,これに恐怖心を抱いたVさんが土下座しています。
まず,Aさんの発言は,世間一般の感覚からすれば「土下座をしないと身体に危害を加えられる」と受け取られるものだと考えられます。
この点は,発言に至った経緯や発言の仕方といった具体的な状況に左右されますが,おおむね「脅迫」と評価されても不思議ではないでしょう。
そして,この発言を受けたVさんは,最終的に土下座に至っています。
いくらVさんが謝罪すべき立場にあったとしても,土下座という方法をとることに義務はないと言えます。
以上より,Aさんは脅迫によりVさんに義務のない行為をさせていることから,強要罪に当たると考えられます。
【逮捕がもつ本当の意味】
刑事事件において行われる逮捕については,一般の方々の認識と実際の意味とにずれがあるかもしれません。
第一に,逮捕はしばしば刑事事件を起こしたことに対する制裁のように捉えられますが,実際にはそうではありません。
逮捕が行われる段階というのは,有罪か無罪かの判断が下される前に当たり,逮捕される被疑者は飽くまでも罪を犯した疑いがあるに過ぎません。
逮捕の本当の目的は,被疑者の行動の自由を制限することで,逃亡や証拠隠滅を防止して裁判の準備をしやすくするというものなのです。
また,ニュースを見ていると,重大な犯罪と共に「逮捕」という文字を見ることが多いかもしれません。
ですが,本来犯罪の重さと逮捕の可能性とは直接的な結びつきを持ちません。
重大な犯罪と逮捕が結びつきやすい理由としては,犯罪が重大であればあるほど,被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高いと考えられやすいからです。
結局のところ,逮捕の目的は逃亡と証拠隠滅の防止にあるので,これらの行為に及ぶ危険性が高ければ犯罪の軽重を問わず逮捕されやすくなると言えます。
更に,細かいことではありますが,厳密な意味での「逮捕」というのは,捜査機関による身柄の確保から72時間の身体拘束のことです。
これより長い身体拘束については,正確に言うと「勾留」という手続であって,本来の逮捕ではありません。
とはいえ,弁護士であっても身体拘束されている状態一般を便宜上「逮捕されている」と言ったりするので,この点に殊更気をつける必要はあまりないように思えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,釈放を実現した実績のある弁護士が,逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご案内はこちら)
飲酒運転と執行猶予
飲酒運転と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Xさんは普段はお酒を飲まないため、同僚や上司飲み会を断っていました。ところが、年末の忘年会だけはどうしても断ることができず、参加することになりました。
忘年会でもXさんはお酒を飲むつもりがなかったため、当日は自身の車で千葉県市原市にある会社まで通勤し、仕事終わりに、会社の近くにある居酒屋で会社の同僚と忘年会を行いました。
忘年会では飲むつもりはなかったXさんでしたが、社長から「乾杯くらいはいいだろ。あと数時間もすればお酒も抜けるよ。」と言われ、どうしても断ることができず乾杯だけすることにし、ビールをグラスで1杯だけ飲みました。
その後、Xさんはお酒を飲むことなく忘年会が終了し、自分の車で帰ることになりましたが、普段からの疲労と久しぶりの飲み会で気が緩んだのか、うとうとしてしまい、運転中、壁に激突してしまいました。
その後、通行人から通報があり、千葉県市原警察署の警察官がやってきて、呼気検査がなされ、その結果が呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.3mgであったため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで取り調べを受けることになりました。
実は、Xさんは、3年前に飲酒運転で罰金刑を受けたことがあり、今回注意をしていたのですが、すっかりアルコールが抜けていると思っていたので運転してしまっていたのでした。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転については、道路交通法に禁止規定と罰則が定められています。
まず、道路交通法65条は、「酒気帯び運転等の禁止」として、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
この規定が飲酒運転の禁止を定めたものです。
他方で、飲酒運転の罰則については、飲酒運転の具体的な内容に応じて以下のとおり2通り存在します。
ひとつは、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。
酒気帯び運転は、身体に一定程度以上のアルコールを保有した状態で運転した場合に成立するものです。
具体的なアルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、令和元年12月現在,①血液1mlにつき0.3mgまたは②呼気1ℓにつき0.15mgです。
実務においては、②の基準を通常利用します。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(同法117条の2の2の3号)。
もうひとつは、「酒酔い運転」と呼ばれるものです。
酒酔い運転は、「酒に酔つた状態」、すなわち「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合に成立します。
酒酔い運転に該当するかどうかは、飲酒運転を検挙した警察官などが視認することで確認する場合が多く、呼気検査の数値が大きいかどうかだけで判断されるものではありません。
たとえば、道路の白線の上を真っすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などの事情が考慮されることとなります。
警察によりこういった判定がなされた結果、酒酔い運転と判断された場合、たとえ呼気検査の結果が低かったとしても安心することはできないので、注意が必要です。
罰則は、酒気帯び運転よりも重い、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています(117条の2の1号)。
【執行猶予を獲得するには】
飲酒運転が発覚した場合、初犯(これまで前科がなかった人)であれば、呼気検査の結果がそれほど重いものでなければ、略式命令(法廷ではなく書面で裁判を行う簡易な手続)による罰金刑で終わる可能性があり、裁判所に出頭することなく、簡便に事件が終了する可能性も見込めます。
ところが、上記事例のXさんのように2回目の飲酒運転となると呼気検査の結果が高い数値でなかったとしても、反省を促すなどの目的で、検察官が裁判を請求する可能性が出てきます。
そうなってしまった場合、刑務所への収容を回避するために、公判廷で罰金刑を求めるかあるいは、懲役刑を受けるとしても、執行猶予を目指していくこととなります。
執行猶予付きの判決とは、被告人に対し、懲役刑を課しながら、一定期間社会内で更生のチャンスを与え、その期間被告人が何らかの犯罪行為を犯すことなく期間が経過した場合には、懲役刑を免除するという判決であり、懲役刑の判決を受けたとしても、刑務所に行かず引き続き社会内で生活を行うことができる判決です。
裁判官が、懲役刑執行猶予を付するかどうかは、アルコール濃度ももちろんですが、アルコールを摂取するに至った経緯や飲酒運転に至った経緯、事件後の被告人の反省の程度、更生に向けた被告人の動きなどの様々な事情を考慮して決めるものです。
今回のXさんは2度目の飲酒運転であり、裁判官に対し、単に「もう飲酒運転をしません」と話したところで説得力に欠ける部分があることは否定できません。
そうした状況下で執行猶予の可能性を高めるのであれば、今回の件を真摯に受け止めていること、更生の余地があることをよりしっかりとアピールする必要があるでしょう。
執行猶予を目指すなら、まずは弁護士に相談するのが賢明と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して尽力します。
飲酒運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、示談の締結をはじめとする的確な弁護活動を行います。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)