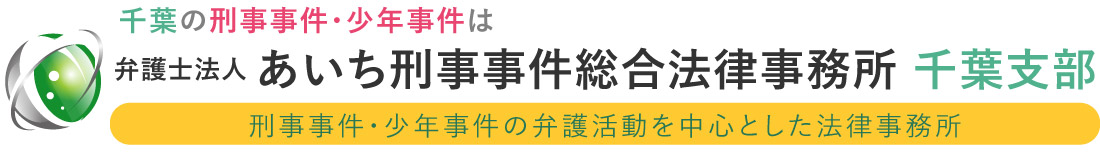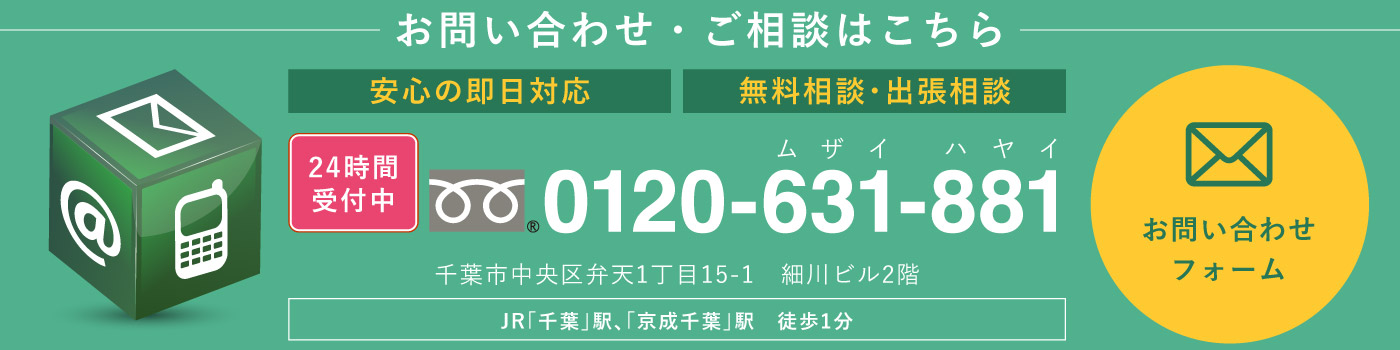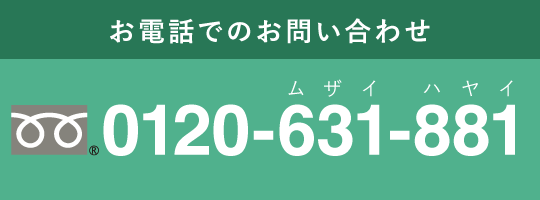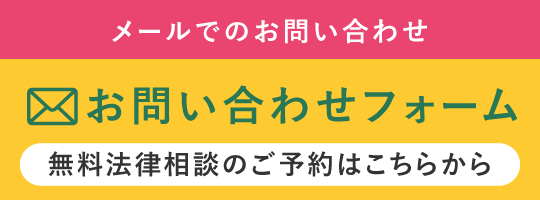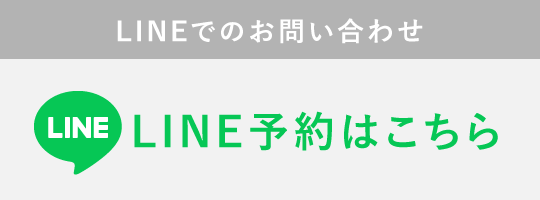Author Archive
盗撮事件で示談
盗撮事件で示談
盗撮事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県山武郡横芝光町のスーパーマーケットで買い物をしていた際、女子高生が数人いるのを見て下着を盗撮したくなりました。
そこで、手に持っていた鞄にペン型の小型カメラを仕込み、女子高生の背後に立ってスカートの中が写るようにカメラを向けました。
その現場を店員が目撃し、Aさんは事務室に連れていかれたうえで警察に通報されました。
カメラには女子高生の下着が写りこんでおり、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、示談を行うべく被害者の両親との接触を試みることにしました。
(フィクションです。)
【盗撮の罪について】
盗撮が犯罪であることは、今や一般によく知られているかと思います。
実は、盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体がある程度自由に定めることができるようになっているため、盗撮について定めた条文の文言や刑罰の重さは各条例により異なります。
千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
ただ、千葉県の場合は、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」を禁止し、その中に盗撮を含めるというかたちをとっています。
そのため、「ひそかに撮影すること」などの表現で盗撮が明記されているわけではなく、規制が若干分かりづらいものになっています。
盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科が複数あったり余罪が大量にあったりすれば、常習盗撮として厳しい刑が科される可能性は高まるでしょう。
ちなみに、公共の場所または公共の乗物以外で盗撮をした場合は、迷惑防止条例ではなく軽犯罪法に違反するとして罰則が軽くなります。
ただし、都道府県によって公共の場所または公共の乗物以外での盗撮も条例がカバーしていることがあるため、その点は注意が必要です。
【示談交渉の困難さ】
盗撮を含む性犯罪のケースでは、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
その理由としては、恐怖心や嫌悪感を抱いている、加害者に対する処罰感情が強い、傷害事件などと異なり金銭的損害を被ったわけではない、などが考えられます。
そのため、盗撮事件においては、一般的に示談交渉が難航しやすいという特徴があります。
弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がない点が挙げられます。
弁護士が介入すれば、被害者と接触できる可能性が高まるだけでなく、非難される側として足元を見られるリスクも回避できます。
被害者としても、加害者と連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できる点が挙げられます。
弁護士は刑事事件において意味のある活動を把握しているのが通常であるため、事件との関係で必要十分な活動を的確に行うことができます。
加えて、示談書のかたちで適切な内容の合意を結ぶことで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高くなります。
以上の点から、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
麻薬所持事件で接見禁止
麻薬所持と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県木更津市に住むAさんは、東京都内をぶらついていた際、「気分が良くなる」などの宣伝文句で薬のようなものが売られているのを見かけました。
Aさんはそれが日本で規制されている何らかの薬物かもしれないと思い至りましたが、以前から興味があったこともあって少量購入しました。
Aさんが購入した薬物を何度か服用していたところ、木更津警察署の警察官から職務質問を受け、薬物の鑑定が行われることになりました。
後日、Aさんが購入したのはMDMAであることが判明し、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんは勾留の際に接見禁止決定を受けたことから、弁護士が接見禁止の解除を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【麻薬所持について】
麻薬は、鎮痛薬として医療に用いられることがある一方で、心身に様々な悪影響を及ぼすと共に依存性を有する危険なものです。
日本では、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「法」)によって、麻薬の所持や譲渡などの様々な行為が禁止されています。
法2条1号は、規制の対象となる「麻薬」を「(法に記載されている)別表第一に掲げるもの」としています。
別表第一を見てみると、70を超える化学物質およびその塩類が「麻薬」に当たることが示されています。
更に、それらに加えて「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が約130種類の化学物質およびその塩類を別途「麻薬」としています。
そのため、規制の対象となる「麻薬」は相当数に上ることが見込まれます。
いわゆるMDMA(3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン)もその一種です。
麻薬所持の罰則は、所持したのが「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそのいずれかを含有する麻薬)か否かで異なります。
ジアセチルモルヒネ等であれば、通常の場合10年以下の懲役、営利目的があった場合1年以上の有期懲役(上限20年)であり、後者は情状により500万円以下の罰金が併科されます。
一方、ジアセチルモルヒネ等以外であれば、通常の場合7年以下の懲役、営利目的があった場合1年以上10年以下の懲役であり、後者は情状により300万円以下の罰金が併科されます。
【接見禁止決定を受けたら】
逮捕後に長期の身体拘束が必要だと考えられる場合、検察官と裁判官の判断を経て勾留が行われることになります。
その際、外部の者との接触を制限するために、接見禁止と呼ばれる措置をとられることがあります。
接見(等)禁止とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、勾留されている被疑者・被告人との面会や物のやりとりを制限することを指します。
勾留がなされている全ての事件において行われるわけではなく、共犯事件など特に逃亡や証拠隠滅のリスクが高い事件について行われる傾向にあります。
接見禁止決定が出た場合であっても、弁護士であれば被疑者・被告人の防御のために接見などを行うことが認められています。
ですので、たとえ接見禁止が付いていても、弁護士を通せば逮捕されている方と意思の疎通を行うことができます。
また、接見禁止決定に対して不服を申し立て、接見禁止の一部または全部を解除するよう求めることも可能となっています。
一部の解除については比較的認められやすく、事件に関与していない配偶者の方やご両親に限って面会の制限が解除されるのはよく見られます。
ですので、接見禁止を理由に面会などを断られても、諦めずに弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見禁止の解除による面会の実現に向けて奔走します。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
同意殺人罪の取調べ対応
Aさんは、SNS上で自殺願望を持つ者を探し、その者の希望を叶えようと考えるに至りました。
そして、「本当に死にたい。誰か殺してほしい」という投稿をしていたVさん(千葉県市原市在住)と接触し、「一緒に死にませんか」と持ち掛けました。
Vさんがその誘いを承諾したため、Aさんは市原市でVさんと会い、市内にあるホテルに入りました。
そして、後を追って死ぬ旨Vさんに伝え、AさんはVさんの首を絞めて殺害しました。
しかし、Aさんは急に死ぬのが怖くなり、警察に「人を殺しました」と通報しました。
すぐに市原警察署の警察官が駆けつけ、Aさんを殺人罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから話を聞き、嘱託殺人罪が成立するにとどまると主張することにしました。
(フィクションです。)
【同意殺人罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
故意に他人を殺害したときに成立する罪を聞かれた際、多くの方は殺人罪を挙げられるのではないかと思います。
殺人罪は、他人を殺害したときに成立する可能性のある代表的な罪と言えます。
ですが、刑法には、それ以外に同意殺人罪が規定されています。
同意殺人罪は、その名のとおり他人の同意を得てその者を殺害した場合に成立する可能性のある罪です。
他人の頼みを引き受けて殺害に及ぶ嘱託殺人罪と、他人に殺害を申込み、その承諾を受けて殺害に及ぶ承諾殺人罪に分けられます。
同意殺人罪に関して注意すべきは、表面上は被害者の同意が見られたとしても、それに実が伴っていなければ殺人罪に当たる余地があるという点です。
たとえば、被害者が知的障害により「死」について理解しないまま殺害に同意した場合、同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する可能性があります。
このように被害者が正常な判断能力を欠いているケースについては、安易に同意の存在を認めて責任を軽んずるべきではないからです。
時には、正常な判断能力のもと同意が行われたかどうかを巡って、裁判で激しく争われることもあるでしょう。
【殺人罪だと誤解されないために】
同意殺人罪に不可欠な被害者の同意という事情は、殺害に至った経緯に関するものです。
殺人事件の捜査が死体を手掛かりに行われると考えると、捜査の初期段階では同意殺人罪ではなく殺人罪を疑われることもなんら不思議ではありません。
仮に殺人罪で有罪となった場合、①死刑、②無期懲役、③5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかが科されるおそれがあります。
一方、同意殺人罪で有罪になった場合、6か月以上7年以下の懲役または禁錮が科されるおそれがあります。
このように、殺人罪と同意殺人罪のいずれで有罪になるかは、最終的な処分を大きく左右する重要な事柄と言って差し支えないかと思います。
殺人罪か同意殺人罪かを決するにあたり、被疑者・被告人の供述というのは非常に有力な手掛かりとなることが見込まれます。
供述の内容いかんは、自身にとって有利にも不利にも働く可能性を秘めています。
そこで、取調べで供述をするに先立ち、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞いておくことをおすすめします。
刑事事件において捜査機関に丸腰で対峙するのは危険であり、疑われているのが殺人罪のように重大な罪となればなおさらです。
不用意な供述をして不利にならないよう、正しい取調べ対応を身につけて取調べに挑みましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事案に応じた最適な取調べ対応を丁寧にお伝えします。
ご家族などが同意殺人罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
強要未遂罪で逮捕されるか
強要未遂罪で逮捕されるか
Aさんは、SNSを通じて千葉県長生郡一宮市に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。
ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「茂原警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。
一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが重くなることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、弁護士が罪の成立を争う幅も比較的広いと言えます。
【逮捕の可能性】
罪を犯してしまった際、誰しも「逮捕されるのではないか」という不安を抱くことかと思います。
刑事事件において、逮捕されるケースというのは全体の4割程度です。
ですので、刑事事件を起こしたからといって、ほぼ確実に逮捕されるなどと考える必要はありません。
ただ、事件からしばらく経って逮捕されることもあるので、その点は頭の片隅に置いておく必要があります。
逮捕は被疑者の行動の自由を奪うことから、法律により逮捕を行うための要件が厳格に定められています。
逮捕を行うためには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逮捕の理由と逮捕の必要性がなければなりません。
第一に、逮捕の理由とは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれの存在だと考えられています。
その判断に当たっては、事件の内容や被疑者の態度などの様々な事情が考慮されます。
第二に、逮捕の必要性とは、逮捕により被る不利益よりも逮捕により得られる利益の方が大きいことです。
利益と不利益を天秤にかけるようなかたちで判断され、逮捕の理由である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがどの程度かということも考慮されます。
逮捕をするかどうかは結局のところ捜査機関次第であるため、捜査機関でない限り逮捕の有無を断言することはできません。
ただ、刑事事件に詳しい弁護士に聞けば、逮捕の可能性についてある程度予測を立てることが可能です。
それだけでなく、捜査機関に逮捕しないよう働きかけたり、捜査にどう立ち向かうべきか確認したりすることができます。
逮捕に関する不安を少しでも払拭するなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕を含む様々なご相談に真摯に対応いたします。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
犯人隠避罪で執行猶予
会社員のAさん(20歳)は、中学校時代の先輩であるBさんから電話である依頼を受けました。
曰く、Bさんは千葉県勝浦市内でひき逃げをしてしまい、その犯人を勝浦警察署が探しているため、代わりにAさんに出頭してほしいとのことでした。
その依頼を引き受けたAさんでしたが、捜査が進むにつれて矛盾点が明らかとなり、最終的に身代わり出頭であることが捜査機関に知られてしまいました。
それを皮切りに、Bさんが過失運転致傷罪などの疑いで逮捕され、Aさんも犯人隠避罪の疑いで改めて捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、仮に起訴されても執行猶予になる可能性が高いと説明しました。
(フィクションです。)
【犯人隠避罪について】
刑法(一部抜粋)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
犯人隠避罪という罪名自体は、多くの方にとってあまり聞きなれないかもしれません。
犯人隠避罪は、犯人蔵匿罪とまとめて上記のとおり刑法103条に規定されています。
これらの罪は、簡単に言うと刑事事件の犯人に捜査が及ばないよう何らかの手助けをした場合に成立する可能性のある罪です。
今回の事例では、Aさんがひき逃げをしたBさんの代わりに警察署へ出頭しています。
こうした行為が犯人隠避罪に当たるかどうか見ていきます。
犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」、すなわち場所を提供して匿う以外の方法で、犯人が警察などに逮捕・発見されるのを免れさせることを指します。
ここで言う「犯人」とは、真犯人かどうかを問わず、被疑者・被告人として捜査が及んでいる者全てを指すと考えられています。
上記事例では、AさんがBさんの代わりに出頭したことで、BさんではなくAさんがひき逃げの犯人として捜査を受けています。
この場合、捜査機関としては当然に出頭したAさんを被疑者として扱うことになり、その結果としてBさんへの捜査は及ばなくなることが想定されます。
そうすると、Aさんによる身代わり出頭は「隠避」に当たり、犯人隠避罪が成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、「罰金以上の刑に当たる罪」という限定がありますが、実際のところこれに当たらないのは軽犯罪法違反などごく一部でしょう。
【執行猶予の可能性】
犯人隠避罪の罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、率直に言って著しく重いというわけではありません。
ですので、事案の内容次第ではあるものの、初犯であれば一般的に罰金で終わることが多いと見込まれます。
このように比較的軽い罪については、事案を重く見て起訴されたとしても、初犯であれば執行猶予になる可能性が少なからずあります。
執行猶予には刑の一部の執行が猶予される場合と全部が猶予される場合とがありますが、今回は実務上多く見かける全部の執行猶予に絞って解説を行います。
執行猶予とは、有罪として刑を科す際に、一定期間その刑の執行を見送る制度です。
つまり、懲役刑や禁錮刑を言い渡されても直ちに刑務所に行く必要はないということです。
「猶予」とあるように、一定の事情(たとえば新たに重い罪を犯すなど)が生じた場合は執行猶予が取り消されて受刑を余儀なくされます。
ですが、逆にそうした事情が生じることなく期間の満了に至れば、刑を受ける必要がなくなります。
執行猶予に関する規定は複雑であり、その全てを理解するのは非常に骨が折れるかと思います。
ですので、ご自身の事案で執行猶予がつくか疑問に思ったら、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の可能性やその後のリスクなどについて丁寧にご説明します。
犯人隠避罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
準強制わいせつ罪で逮捕
千葉県いすみ市に住むAさんは、帰宅途中にあるコンビニの駐車場で20歳前後と思しき女性Vさんが寝ているのを発見しました。
Aさんが「大丈夫ですか」と声を掛けたところ、Vさんから酒の匂いがしたことから、酒に酔って寝ているのだと認識しました。
それをチャンスだと考えたAさんは、Vさんの服に手を差し入れ、胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。
その様子をいすみ警察署の警察官に現認され、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪について】
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条(執筆者注:強制わいせつ罪の規定)の例による。
準強制わいせつ罪とは、暴行・脅迫を手段とする強制わいせつ罪と異なり、人が抵抗困難な状態にあることを利用してわいせつな行為に及ぶ罪です。
手段となるのは、①「人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ」たこと、②「心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ」たこと、のいずれかです。
心身喪失とは、泥酔や失神などによりわいせつな行為の存在を認識できないことを指します。
これに対し、抗拒不能とは、そうした認識こそあるものの物理的あるいは心理的に抵抗できないことを指します。
こうした状態を利用してのわいせつな行為が強制わいせつ罪と同様の可罰性を有するという考えから、準強制わいせつ罪として定められるに至っています。
ちなみに、暴行または脅迫により抵抗が困難な状態にした場合は、当然ながら強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
たとえば、わいせつな行為をすべく相手方の頭部を殴打して失神させたうえでわいせつな行為に及んだ、というケースがそれにあたります。
【弁護士が行う接見の強み】
刑事事件において、接見とは逮捕されている被疑者・被告人との面会を指します。
一般人が行う接見(面会)を一般接見、弁護士が行う接見を弁護士接見と言い、単に「接見」と言うと多くは後者を指します。
弁護士が行う接見には、以下のとおり一般接見とは異なる点があります。
①日時や回数の制限がない
一般接見の場合、1日1回15分程度というかたちで接見が制限されるのが通常です。
更に、接見ができるのは長期の身体拘束である勾留が決定した後であり、勾留決定まで(おおむね逮捕から2~3日後)は多くの警察署において接見が許されません。
これに対し、弁護士はよほどのことがない限り日時や回数を問わず接見できます。
②立会人を要しない
一般接見では、証拠隠滅の手助けなどを防ぐ目的で、警察署の職員が接見に立ち会うことになります。
一方、弁護士との接見は秘密が保障されており、被疑者・被告人としてどのような内容でも心置きなく話すことができます。
この点は、特に捜査機関に発覚していない罪がある場合などに重要となります。
③接見禁止の影響を受けない
特に共犯事件において、主に証拠隠滅を防ぐという観点からいわゆる接見禁止が付くことがあります。
この場合、一般人は接見を行うことができなくなりますが、弁護士は影響を全く受けません。
④検察庁や裁判所で限られた時間接見できる
一般面会が可能な場所は警察署のみであり、被疑者・被告人が何らかの手続のために検察庁や裁判所にいる間は接見できません。
ですが、弁護士であればそれらの場所で限られた時間接見を行うことが許されており、目前に控えた手続に先立ち助言をすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見してほしいというご依頼に迅速に対応いたします。
ご家族などが準強制わいせつ罪の疑いで逮捕をされたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
過失運転致傷罪で執行猶予
過失運転致傷罪で執行猶予
Aさんは、千葉県長生郡睦沢町にて自動車を運転していた際、Vさん(30歳)と接触する事故を起こしました。
事故の現場は交差点であり、Vさんが横断歩道を渡ろうとしていたのに気づかずAさんが右折したのが事故の原因でした。
これにより、Vさんは全治1か月の怪我を負い、茂原警察署は過失運転致傷罪の疑いで捜査を開始しました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、仮に裁判になっても執行猶予となる可能性があると言いました。
(フィクションです。)
【過失運転致傷罪について】
刑法は、不注意による他人への傷害を過失傷害罪として罰することとしています。
本来なら刑罰を科すに値するのは故意犯であり、過失犯という類型を設けるのは例外的な場合にのみ許されると考えられています。
そのため、過失傷害罪の罰則は30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)と軽くなっています。
ところが、自動車が普及するにつれてその危険性が認知されるようになったことで、自動車による過失傷害は重く罰すべきではないかと考えられるようになりました。
そこで、刑法改正により自動車運転過失致傷罪という特別な規定が置かれ、現在ではそれが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に組み込まれるに至っています。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すると定められています。
ただし、傷害の程度が軽ければ、情状により刑が免除される余地があります。
実際にどの程度の刑が科されるかは、怪我の程度、不注意の内容、被害弁償の有無などにより変わってきます。
不起訴になることもあれば裁判で懲役刑が科されることもあるため、結果については個々の事案により様々です。
ちなみに、特定の状態(たとえば飲酒運転や大幅なスピード違反など)で人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪となります。
その法定刑は1年以上の懲役であり、相当長期の懲役刑が言い渡される可能性も決して否定できません。
【執行猶予の概要】
過失傷害罪と比較すると、過失運転致傷罪の法定刑が重いことは否定できません。
ですが、そうはいっても過失運転致傷罪が故意犯でなく過失犯であることには変わりなく、執行猶予が付く余地は十分あると考えられます。
執行猶予とは、刑の重さが一定の範囲内である場合において、一定期間刑の全部または一部を執行しないでおく制度のことです。
一部執行猶予は再犯防止を図るべく主に薬物事件などで行われるため、以下では全部執行猶予について説明します。
刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す際、情状により付されるものです。
いったん刑の全部の執行を回避できるため、裁判が終わったあと直ちに刑務所に収容されるという事態を防ぐことができます。
それだけでなく、指定された期間執行猶予が取り消されなければ、刑の言い渡しは効力がなくなります。
つまり、猶予された刑を受ける必要がなくなるというわけです。
執行猶予が取り消されるのは、たとえば禁錮以上の実刑が科された場合などが挙げられます。
ご不安であれば、執行猶予となって後のことも含めて弁護士に相談しておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、執行猶予に関するご相談を真摯にお聞きします。
過失運転致傷罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
侵入盗で一部無罪主張
侵入盗で一部無罪主張
千葉県長生郡長生村のアパートに住むAさんは、入居の際に挨拶をした隣室のVさんに好意を抱きました。
AさんはなんとかVさんと親しくなれないか考えましたが、なかなかそのきっかけを掴めずにいました。
ある日、AさんはVさんがアパートの鍵を掛けずに外出する癖があることを知り、不在時を狙えば部屋に忍び込めると考えました。
そこで、Vさんが留守のタイミングを見計らって、Vさんの部屋に無断で立ち入りました。
その数日後、Aさんのもとを茂原警察署の警察官が訪ね、侵入盗を試みたとしてAさんを住居侵入罪および窃盗未遂罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、窃盗未遂罪について無罪の主張をすることにしました。
(フィクションです。)
【侵入盗について】
窃盗罪には、商品数点の万引きや他人口座からの現金の引き出しなど、実に様々なケースが存在します。
侵入盗というのは、そうした窃盗罪に当たるケースのうち、住居や事務所などに侵入して行う窃盗の類型を指します。
ご存知の方も多いかと思いますが、侵入盗に成立するのは、住居等侵入罪および窃盗罪であるのが基本です。
まず、住居等侵入罪は、正当な理由なく他人の住居等に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
注意しなければならないのは、普段自由に立ち入りができる場所だからといって、そのことをのみを理由に住居等侵入罪の成立が否定されるわけではない点です。
たとえば、普段気軽に出入りできる友人の家であっても、あらかじめ窃盗の目的で立ち入れば住居侵入罪に当たる可能性があります。
次に、窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する可能性のある罪です。
窃取による財物の移転をもって既遂となり、既遂に至らずともその危険性が認められれば窃盗未遂罪となる余地があります。
たとえば、金目の物がないかタンスの中身を物色すれば、財物窃取の危険性があったとして窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
【侵入盗事件における一部無罪の主張】
住居侵入罪を犯した際、それと併せて窃盗罪または窃盗未遂罪を疑われることは少なくありません。
これは、物がなくなっていると被害者が感じたり、室内に荒らされた形跡が残ったりしていることがその原因です。
侵入盗は窃盗事件の中でも特に多いことから、住居侵入罪と共に疑われやすいのです。
こうした侵入盗事件のように本来行った以上の犯罪を疑われている場合、一部無罪を主張することが考えられます。
一部無罪は、その名のとおり疑われている犯罪の一部について無罪となることです。
当然ながら、有罪となった際の刑は罪の数が多ければ多いほど重くなるため、一部無罪は量刑を軽くする要素として決して見逃せないものです。
侵入盗も例にもれず、住居等侵入罪および窃盗罪が成立する場合と住居等侵入罪のみが成立する場合とでは全く話が違ってきます。
一部無罪を目指すうえでは、どこまで認めてよく、どこから否認すべきかの線引きをきちんと行う必要があります。
この判断は、各犯罪の成立要件に加えて、個々の行動や供述が犯罪の認定との関係でどういった意味を持つのかという点をも把握することが重要になります。
こうした判断は法律のプロである弁護士が活きる場面なので、一部無罪を主張するならぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、やっていないことを疑われた方のために一部無罪の主張を真摯に検討いたします。
ご家族などが侵入盗の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
強盗罪で逮捕
Aさんは、競馬のために借金をし、その返済に追われていました。
そこで、何か簡単にお金を手に入れる方法はないかと考えた結果、コンビニ強盗を行うことにしました。
Aさんはマスクと帽子で極力顔が割れないようにし、千葉県山武市にあるコンビニへ行きました。
Aさんは様子を探るべく店内を数分歩き回ったあと、レジにいる店員に包丁を示して「金を出せ。殺すぞ」と言いました。
店員は恐怖に怯え、レジのキャッシャーを開けて1万円札と1000円札を全て渡しました。
Aさんはそれを受け取ってすぐに逃走しましたが、後日強盗罪の疑いで山武警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、保釈による身柄解放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人の財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどでは、何らかの凶器を示してお金を要求するケースがよく見られるかと思います。
そうしたケースは、正に強盗罪の典型例と言うべきでしょう。
一般的にはお金や物が対象となることが多いかと思いますが、引用した条文にあるとおり、財産上の利益であっても対象となります。
たとえば、あるサービスの料金の請求を暴行または脅迫により断念させた場合、債務を免れたとしてやはり強盗罪が成立する余地があります。
こうした財産上の利益を対象とする強盗罪は、強盗利得罪や2項強盗罪(刑法236条2項に規定されているため)と呼ばれることもあります。
強盗罪によく似た罪として、恐喝罪が挙げられます。
恐喝罪も暴行または脅迫により財産の交付を受ける罪ですが、両者は被害者の判断能力の程度が異なるとされています。
簡単に言うと、強盗罪は財産の交付に関する被害者の判断を不可能あるいは著しく困難にするのに対し、恐喝罪は被害者の判断を害するにとどまるということです。
こうした区別は主に暴行・脅迫の程度によるので、暴行・脅迫が激しければ恐喝罪を超えて強盗罪となる可能性が高まるでしょう。
【保釈とは何か】
保釈とは、裁判所に一定の金銭を預けるのと引き換えに、少なくとも裁判が終わるまで一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
被告人(被疑者の起訴後の呼称)に限って認められるため、逮捕されてからすぐに行えるわけではありません。
逮捕されてから起訴されるまでに身柄解放を実現するには、検察官や裁判官に対して勾留(逮捕から2~3日後に開始される長期の身体拘束)をしないよう求めることになります。
起訴前の身柄解放が何の犠牲もなく行えるのに対し、起訴後の身柄解放である保釈は高額な金銭の納付が必要です。
そうすると、保釈は起訴前の身柄解放活動より劣っているような印象を受けるかもしれません。
ですが、保釈には、起訴前の身柄解放活動と比べて身柄解放を実現しやすいというメリットがあります。
その理由は、預けた金銭が逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保の役割を果たし、被告人がそうした行動に及ぶ可能性が低いと評価されるためです。
また、そのような役割を持つことから、保釈保証金は逃亡や証拠隠滅を含む一定の事由が発生しない限り後に全額返還されます。
ですので、感覚としては、お金を支払うというより一旦預けると言う方が近いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、保釈の実現に向けて迅速かつ的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちらから)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
強要罪で逮捕
Aさんは、友人らと談笑しながら千葉県東金市内を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかりました。
Aさんが「おっさん気をつけなよ」と言ったところ、Vさんが睨んできたことから、AさんらとVさんは口論になりました。
AさんらはVさんを囲って軽い暴行を加え、スマートフォンで動画を撮りながらVさんに土下座するよう迫りました。
Vさんは言われたとおりに土下座をしましたが、騒ぎを聞いて駆けつけた東金警察署の警察官により、Aさんらは強要罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、今後の事件の流れを説明しました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
強要罪は、暴行または脅迫を手段として、他人に無理やり何かをやらせたり、逆にやらせなかったりした場合に成立する可能性のある罪です。
相手方の意思決定の自由を妨げるにとどまらず、その意思決定に基づく行為を妨げる点において、脅迫罪より重大な罪と言えます。
一時期ニュースなどで「土下座強要」が話題になりましたが、正にそうした行為が強要罪に当たることになるでしょう。
ここで注意したいのは、強要の内容や相手方の意思によっては、強要罪とは別の罪が成立する余地があることです。
たとえば、強要罪の手段となる暴行により相手方に傷害を負わせた場合、強要罪と併せて傷害罪が成立する可能性があります。
また、他人に犯罪を強要すれば、その犯罪の共犯者として責任を問われる可能性があります。
更に、強要したのが自殺であれば、自殺教唆罪や殺人罪が成立する可能性も出てくるのです。
殺人罪については、相手方が自ら死を選択したにもかかわらず自身が殺害したものと扱われることに違和感を覚えるかもしれません。
ですが、実務では実質的に誰が責任を負うかという観点も重視されており、こうした取り扱いが認められています。
【逮捕された場合の事件の流れ】
刑事事件の被疑者として逮捕された場合、捜査はおおむね以下のように進みます。
①逮捕から勾留決定まで
逮捕されると、警察署で弁解の録取などが行われたあと、48時間以内に事件が警察署から検察庁へ送致されます。
検察庁でも同様に弁解の録取などが行われ、検察官が身体拘束を引き続き行うべきだと考えた場合、検察官が被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求を行います。
そして、裁判所で勾留質問が行われたあと、裁判官の判断で勾留の決定が下されます。
以上のそれぞれの段階において、勾留の必要がないと判断されればその場で釈放されます。
②勾留決定から起訴まで
勾留決定が下されると、はじめに勾留請求の日から10日間の拘束が行われます。
この間、捜査機関は必要な捜査を行い、検察官が起訴すべきか不起訴にすべきか判断します。
起訴されれば裁判を行うことが決定し、不起訴あるいは処分保留となれば釈放されます。
処分保留となった場合については、身体拘束こそ解けるものの事件自体は続くので注意が必要です。
これらに対して、長期の捜査が必要であるとして勾留延長が行われることがあります。
勾留延長も検察官の請求と裁判官の判断により行われ、最長で10日間延長される可能性があります。
③起訴後
起訴された被疑者は被告人と呼ばれるようになります。
被告人の勾留の期間は数か月間(2か月に加えて場合により1か月単位で延長)と非常に長期に及びます。
その期間中に裁判が行われ、最終的に判決が下されて事件は終了となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の段階に合わせて的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介