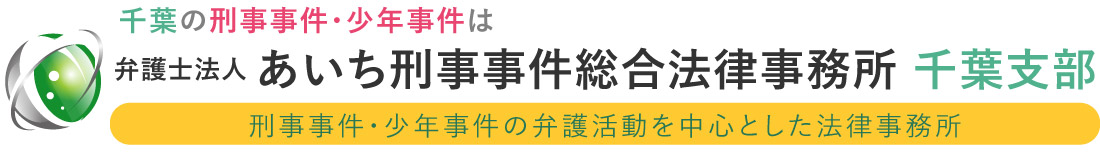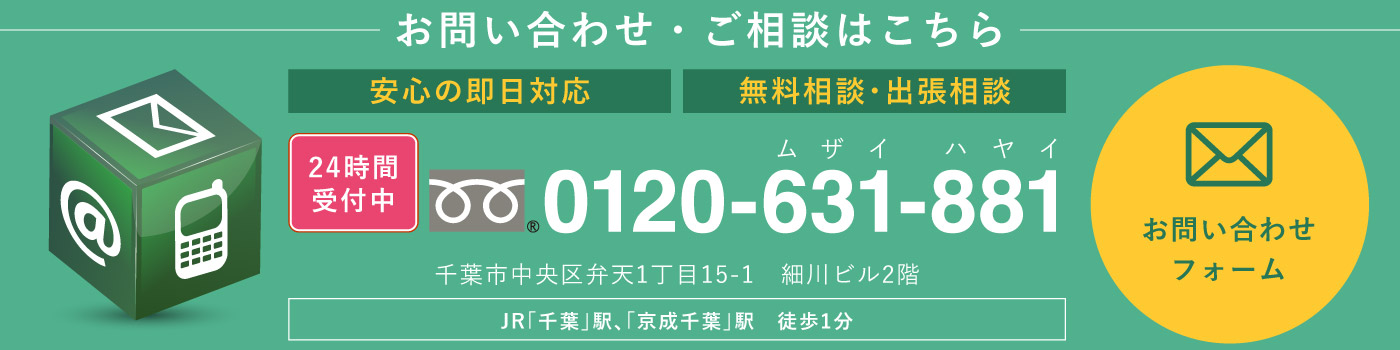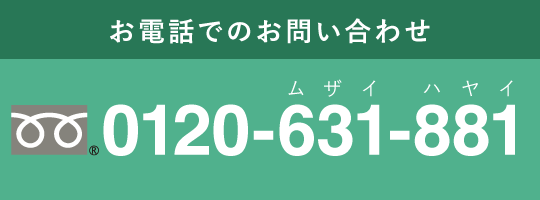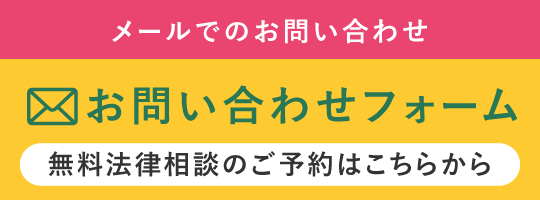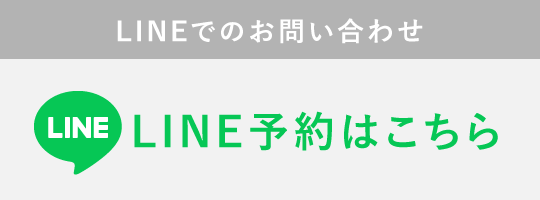Archive for the ‘刑事事件’ Category
千葉県山武市の脅迫事件 脅迫罪にあたる行為
千葉県山武市の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
<千葉県山武市の脅迫事件>
無職Aさんは、千葉県山武市の海浜公園内にて仲間と酒を飲み騒いでいたところ、近くにいたVさんから「もう少し静かにしてもらえませんか。」と声を掛けられました。
Vさんからの注意に腹を立てたAさんは、
「俺は暴力団の組長と親しいから、今度お前を痛めつけてもらうわ」
とVさんに告げました。
後日、Vさんが、Aさんから告げられた内容を警察に相談したところ、Aさんは千葉県山武警察署にて取り調べを受けることなりました。
(フィクションです。)
<脅迫罪とは>
脅迫罪は、刑法第222条第1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
「畏怖させる」とは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、「害悪の告知」と言います。
上記した山武市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「俺は暴力団の組長と親しいから、今度お前を痛めつけてもらうわ」
と伝えたように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。
<相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に>
害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは民法第725条で定められている親族を指しますので、本人のいとこや、配偶者の両親なども含まれます。
これは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているためです。
例えば、「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
<相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する>
害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
例えば、上記した山武市の脅迫事件例において、Aさんの脅迫に対して、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立するということです。
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう、そんな知り合いいないくせに。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります。
<脅迫事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が脅迫罪の罪に問われ、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
脅迫事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
【お客様の声】所得税法違反での解決事件
【お客様の声】所得税法違反での解決事件
【事案の概要】
ご依頼者様は個人事業主として事業をされてきましたが,確定申告の際に実際よりも少ない所得を申告して所得税の一部を納税していなかったという所得税法違反事件でした。
脱税の期間は2~3年で,本来申告するべき所得の半分以下の金額を申告していたところ,国税局の担当者から出頭要請があり,取調べを受けることになりました。
【所得税法違反の罰条】
所得税法238条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【弁護活動】
ご依頼者様が弁護士に相談に来られた時点では,既に何度か国税庁の調査が進んでおり,本来の納税額等を踏まえると,検察庁への告発がなされる可能性が高い事件でした。
国税庁による調査と検察官の取調べへの対応と,裁判時の対応を行うため,ご依頼者様は当所へ弁護活動を依頼されました。
取調べなどにおいては,ご依頼者様の刑事責任が必要以上に重いものになってしまわない様に何度も打ち合わせを重ねていきました。
また,裁判においては,捜査機関によって膨大な証拠が作成されていたため,それぞれについて精査して税額など調査の結果に不備がないか等を確認しました。
税の計算や調査については,捜査機関も間違えることがあるため,弁護士がさらにそれを確認することは重要です。
裁判に向けては,国税庁の調査の結果を踏まえて本来であれば納めるべきであった納税等の処理を適切に行い,また,ご家族からの協力を得て,今後同じ事業によって脱税となってしまわない様に,会計業務,経理業務のための人を雇う等して再発の防止に努めました。
これらに加えて,ご依頼者様が反省して二度と同じことをしてしまわないという意思を行動で明らかにするために,公的な財団への贖罪寄付も行いました。
実際の裁判ではこれら,ご依頼者様にとって有利になる事情を主張,証明したところ,執行猶予付きの判決を得られました。
また,検察官は罰金刑も求刑しましたが,判決では検察官の求刑から数百万円が減刑された罰金刑の言い渡しとなりました。
【まとめ】
所得税法違反事件では,まずは国税局が捜査を行い,本来の納税額等を検討したうえで検察庁への告発が行われます。
所得税法違反事件で重要な点の一つは「金額の算定」です。
金額の算定は,捜査機関側は実際の所得を算定することになりますが,その証拠の量は膨大で,計算も容易ではありません。
しかし,捜査機関の主張する金額が必ずしも妥当である保証はなく,ともすればご依頼者様が必要以上に厳しい刑事罰を受けることになるかもしれません。
そのため,弁護側としてもご依頼者様のお話を捜査機関側の証拠書類を逐一照らし合わせ、捜査機関が主張する逋脱税額が妥当なものであるか,しっかりと確認する必要があります。
脱税などの所得税法違反事件の場合,弁護の経験がある刑事事件専門の弁護士事務所に相談されることをお勧めします。
所得税法違反で国税庁の調査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
御予約:0120-631-881
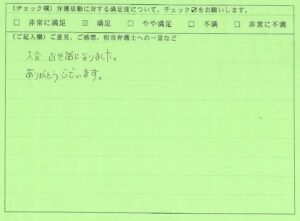
千葉県浦安市の有価証券偽造等事件 偽造事件に強い弁護士
千葉県浦安市で起きた有価証券偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
<千葉県浦安市の有価証券偽造等事件>
アルバイトのAさんは千葉県浦安市が発行した「生活応援クーポン券」を、自分が使用する目的で偽造しました。
Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」とは、浦安市内の商店において、商品券と同じように使用できるクーポン券でした。
そして、Aさんは浦安市内の各店舗で、偽造したクーポン券を複数回使用しました。
しかし、クーポン券が偽造されたものと気付いた店員が警察に通報し、後日、Aさんは千葉県浦安警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
<有価証券とは>
有価証券とは、財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につき、その証券の占有が必要とされるもののことです。
例えば、手形や小切手、商品券や株券などが該当するので、Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」も有価証券にあたります。
これら有価証券を偽造したり、変造する行為は、刑法162条有価証券偽造等罪にあたります。
<有価証券偽造等罪>
刑法162条第1項において「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記刑事事件例のように有価証券を行使の目的で偽造した場合、有価証券偽造等罪に問われるでしょう。
<偽造有価証券行使罪>
また、偽造された有価証券を行使しただけでも、その行為は違法となります。
刑法163条第1項において「偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
行使罪の法定刑は先述した有価証券偽造等罪と同じです。
いずれの場合も罰金刑が予定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予を得ない限り刑務所に服役することとなります。
<有価証券偽造等罪以外の罪に問われることも>
上記したAさんのように、偽造した有価証券を使用して商品を購入する行為は、店員から商品を騙し取ったという詐欺罪にも抵触します。
つまりAさんの行為は、有価証券偽造罪、偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの罪に該当し、これらの罪は牽連犯となります。
また、偽造した有価証券の種類によっては特別法が適用されることもあります。
例えば、使用する目的で切手を偽造した場合は郵便法違反となり、同法85条より、10年以下の懲役に処すると規定されています。
<偽造事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
有価証券偽造等罪など、過去に多くの刑事事件を取り扱かって参りました。
もし、ご自身が有価証券などを偽造し、警察に取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
有価証券偽造等罪に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
半年前の窃盗事件で警察から呼び出された時の対処
半年前に起こした窃盗事件で千葉県鴨川警察署に呼び出された時の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
事件を起こして半年も経過したので「もう大丈夫だろう。」と安心していたら、急に警察署から電話がかかってきて呼び出された・・・
警察は、事件を認知してすぐに犯人を特定することもあれば、捜査に時間を要し、発生から相当な時間が経過して犯人を特定する場合もあります。
特に最近は、DNA捜査などの科学技術の進歩によって、何年も前の事件の犯人が特定されることも珍しくありません。
そこで本日は、半年前に起こした窃盗事件で、千葉県鴨川警察署に呼び出されたAさんの事例(フィクション)を紹介したいと思います。
半年前に鴨川市で起こした窃盗事件
Aさんは、半年以上前に鴨川市の銀行ATMコーナーで、機会の上に置いてあった現金10万円が入った封筒を、そのまま自宅に持ち帰りました。
しばらくは警察が来た時のために現金に手を付けずにそのまま保管していましたが、事件から1ヶ月経過しても警察から何の連絡もないので、Aさんはパチンコ等のギャンブルで10万円を使い果たしたのです。
それから半年ほどして、急に千葉県鴨川警察署の警察官からAさんの携帯電話に電話がかかってきました。
警察官から半年以上前の事件について追及されましたがAさんは「覚えていない、知らない」と惚けました。
警察官から千葉県鴨川警察署に出頭するように指示されたAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
窃盗罪
人の物を盗むと窃盗罪となると思っておられる方が多いかと思いますが、「人の物を盗る=窃盗罪」とは限りません。
窃盗罪が成立するのは、他人の占有する他人の財物を盗んだ場合です。
例えば道に落ちている財布を盗ったとしましょう。
盗ったのは他人の財布なので一見すると窃盗罪が成立しそうですが、道に落ちている財布は、財布の所有者の占有下にはないので「他人の占有する」には該当しません。
よって、このような事件の場合は窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高いのです。
この理論からすると、Aさんの事件の場合、Aさんが盗ったのは、ATMコーナーに置き忘れていた現金在中の封筒ですので、この封筒はすでに持ち主の占有を離れていたと考えられます。
つまりAさんの行為は遺失物横領罪が適用されそうですが、落とし物でも、人が管理する施設内の落とし物の占有は、その施設の管理者にあるとされる場合もあります。
その場合は、窃盗罪が成立するのです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
適用される法律によって科せられる刑事罰が全く異なりますので、警察の取調べを受ける前に専門の弁護士に相談することをお勧めします。
事件から相当期間経過しての取調べ
事件を起こしてから、相当期間経過して警察の取調べを受ける場合、様々なことに注意しなければなりません。
特に時間が経過している場合は、犯行時の記憶が薄れている可能性も高く、警察官の質問に対して曖昧な答えをしていると、自分の意思に反した内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
もしその様な供述調書が作成されてしまうと、その内容を後から覆すのは非常に困難ですので、取調べにおいて供述したり、警察官が作成した供述調書に署名、押印する際には細心の注意を払わなければいけません。
ご自身で対応するのが困難な場合は、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
千葉県鴨川市の刑事事件に強い弁護士
千葉県鴨川警察署に呼び出された方、千葉県鴨川市で刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、初回の法律相談を無料で受け付けております。
無料法律相談に関するお問い合わせは
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
千葉県内の傷害事件
千葉県内で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<傷害事件の事件例>
千葉県在住の会社員のAさんは会社からの帰宅途中、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかりました。
AさんはVさんを無視してそのまま通り過ぎようとしましたが、Vさんは「謝ることもできないバカ」とVさんに向かって嫌味を言いました。
Vさんの言葉に腹が立ったAさんは、Vさんを殴りつけ、Vさんに全治3週間の怪我を負わせました。
(フィクションです。)
<傷害罪について>
刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する」と傷害罪を規定しています。
傷害罪でいうところの「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。
傷害を生じさせる方法は、通常は暴行行為のように、有形力の行使によるものが通例ですが、刑法204条は方法に限定を加えていません。
つまり、傷害の結果を生じさせることができる方法であれば、無形的方法または不作為による傷害も認められます。
例えば、自宅から隣家に居住する被害者に向けて、ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続け、被害者に精神的ストレスを生じさせ、慢性頭痛症や睡眠障害等を負わせる行為が、傷害罪と認定された事件があります。
<千葉県内の傷害事件の発生状況>
千葉県警察の発表によると、令和2年度の粗暴犯(凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝)の認知件数は2,045件でした。
そのうちの約半数は傷害事件(1,025件)だったようです。
(千葉県警察『令和2年 犯罪の概要 犯罪統計』より)
このうち、903件は被害者や被害関係者からの届け出により、事件が発覚していたようです。
また、傷害事件が発生した場所のうち、もっとも多かった場所は「住宅」で358件、次に多かったのは「道路上」で238件だったようです。
(千葉県警察『人口1万人当たりの犯罪発生件数 《令和2年中》確定値』より)
<傷害事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害事件をはじめとする刑事事件に迅速に対応し、数々の勾留阻止や示談交渉に成功しています。
千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方、又はご家族等が傷害罪で逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
傷害事件に関する無料法律相談や初回接見サービスはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
千葉県四街道市の侵入窃盗事件 不起訴を獲得するために
千葉県四街道市の侵入窃盗事件で不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<刑事事件例>
無職のAさんは、千葉県四街道市の民家に窃盗目的で不法侵入し、部屋の中を物色してたところ、家人が帰宅したことから、手当たり次第に現金等を盗んで逃走しました。
Aさんは、民家の近くに止めていた車で逃走したのですが、家人の通報で駆け付けた千葉県四街道警察署のパトカーに捕まってしまい、住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
<住居侵入罪について>
住居侵入罪は、刑法第130条前段において、正当な理由がないのに、人の住居もしくは看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定されています。
今回の事件ですと、Aさんは窃盗の目的で他人の家に侵入しているので、当然、正当な理由が認められるわけはありません。
ここでいう「正当な理由」とは、法令によって捜索又は検証するために立ち入る行為や、正当防衛や緊急避難に該当する場合です。
正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されるのが通常です。
<窃盗罪について>
窃盗罪は、刑法第235条において、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
今回の事件の場合、窃盗の目的で他人の家に不法侵入しただけですと、窃盗の着手がないので窃盗罪は成立せず、住居侵入罪だけが成立します。
窃盗罪の着手が認められるには、少なくとも不法侵入した家内において物色を開始していなければなりません。
逆に、家内で物色中に家人に見つかって逃走していれば、例え何も盗らずに逃走したとしても、住居侵入罪の他に、窃盗未遂罪が成立してしまいます。
<牽連犯について>
牽連犯とは、複数の犯罪が「目的⇒手段」または「原因⇒結果」の関係になっている犯罪のことです。
今回、例に挙げたように、窃盗目的で住居侵入した場合、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係になります。
牽連犯は科刑上一罪とよばれ、最も重い罪の法定刑が適用されます。
ですから、窃盗罪と住居侵入罪の2つの犯罪が成立する場合、窃盗罪の法定刑で処断されることになります。
<不起訴処分を獲得するために>
2019年の法務省の統計結果によると、検察庁が受理した窃盗罪にあたる事件のうち、約4割が起訴されているようです。
つまり半数以上は不起訴処分になっているので、まず弁護士は不起訴処分を獲得することを目標に弁護活動を進めます。
被疑者が犯行を認めている場合、不起訴処分を獲得するには被害者との示談が必要不可欠となる場合がほとんどです。
弁護士は、被疑者に代わって被害者の方に謝罪と被害弁償を尽くすなどの活動をし、その示談交渉の経過や結果を捜査機関に伝え交渉することで、不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。
<侵入窃盗事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、住居侵入罪や窃盗罪をはじめとする多くの刑事事件において、示談を成立させてきた実績があります。
千葉県四街道市で、住居侵入罪や窃盗罪で逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が逮捕されて悩まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
松戸市の公然わいせつ事件
松戸市の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、会社の同僚女性と交際しています。
先日、松戸市内の居酒屋で、この女性と飲酒していた際にいやらしい気分になったAさんは、お店の近くの路上で女性に口淫してもらいました。
その状況を偶然、パトロールしていた警察官に目撃されたAさんは、公然わいせつ罪の疑いで検挙されて、彼女と共に千葉県松戸警察署に任意同行されてしまいました。
逮捕されずに帰宅することが許されたAさんは、今後の手続きや処分が不安で、千葉県の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談しました。
(フィクションです。)
◇公然わいせつ罪◇
公然とわいせつ行為をすれば、刑法第174条に規定されている「公然わいせつ罪」となります。
この法律は、社会的法益である性秩序を保護法益としており、被害者は存在しません。
この法律でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態をいいますが、現実に不特定又は多数の者によって認識されたことまで必要とせず、その可能性があれば足りるとされています。
Aさんのように、路上でわいせつ行為及んだ場合、もし行為中に、その場に誰もいなかっとしても、いつ人が来るかもしれない場所であるので、このような場所でわいせつ行為に及べば不特定の人に認識し得る状態にあるといえるでしょう。
屋内の場合でも同様で、その場所が容易に外部から見えるような解放された場所であれば、公然性を有するものと判断されます。
また認識する者が、特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められるので、その場に知人しかいなかったとしても、その数が多数であれば公然性を帯びることとなります。
ちなみに公然わいせつ罪でいうところの「多数」とは、おおむね5~6人以上と解されています。
~特定の少人数の場合は?~
特定の少人数の場合は、公然わいせつ罪でいうところの「公然性」は否定される傾向にありますが、特定の少人数に対する密室における行為であっても、一定の計画のもとに反復する意図で、その特定小人数が、不特定又は多数の中から観客として選択された者である場合は、公然性があると解されるので注意しなければなりません。
◇刑事手続きの流れ◇
Aさんのように、公然わいせつ罪で警察に検挙された場合の刑事手続きをみていきましょう。
まず警察署に任意同行された後に警察官の取り調べを受けることになります。
そこでは、事件に関すること以外にも、身上関係についても聞かれて書類を作成されます。
また警察官を犯行現場に案内したり、どのよう行為をしていたのかを再現させられることもあります。
このような警察官の取り調べは、検挙された当日も含めて2~3回ほど行われるのが通常ですが、場合によってはそれ以上の取り調べを受ける場合もあります。
こういった取調べ以外に、警察署では被疑者指紋を採取されたり、被疑者写真を撮影されます。
こういった手続きが終了すると、警察署で作成された書類は検察庁に送致されます。
よく新聞やニュース等で「書類送検」といわれているのが、この手続きです。
検察庁に送致されると、受付を経て事件を担当する検察官が決定します。
この担当検察官のもとに、警察署で作成された書類が渡ると、検察官は書類を確認して被疑者の取り調べを行います。(事件によっては、検察官の取り調べが行われないまま不起訴処分が決定する場合もあり、その場合は、何の連絡もないままに刑事手続きが終了している。)
よく「どれくらいで、検察官から呼び出しがあるのですか?」というご質問がありますが、検察庁に送致されて検察官からの呼び出しまでの期間は、早くて1週間~2週間、遅い場合ですと2、3カ月経って呼び出される場合もあります。
そして検察官の取り調べを終えると、検察官は起訴するか不起訴にするのか、若しくは略式罰金にするのかの処分を決定します。
公然わいせつ罪(法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」)の初犯の場合ですと略式罰金となる可能性が非常に高く、その場合は、検察官から取調べの際にその旨を告げられます。
松戸市の公然わいせつ事件でお困りの方、松戸市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
勾留期間を短くしたい 早期釈放に強い弁護士
勾留期間を短くしたいという方に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市内に彼女と同棲しているAさんは、同棲中の彼女から別れ話を切り出されたことで、カッとなり、彼女の顔面を複数回殴打してしまいました。
Aさんのことが怖くなった彼女が警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは傷害罪の容疑で千葉県千葉西警察署に逮捕されてしまいました。
彼女は、Aのさん顔面殴打行為によって全治3週間の顔面打撲の傷害を負ったようです。
傷害罪で勾留されたAさんは、勾留期間が長くなることによって自営の飲食店を長期閉店に追い込まれてしまうことを気にして、勾留延長を阻止できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
傷害事件
今回の事件でAさんは彼女の顔面を殴打(暴行行為)しており、それによって彼女は全治3週間の傷害を負っています。
Aさんには傷害罪(刑法204条)が成立するといえます。
勾留期間
上記の様ないわゆるDV行為によって逮捕された場合、被害者と加害者が近い関係にあることから逮捕後に、長期間にわたって身体拘束が続く、勾留という手続きが取られる可能性が高いといえます。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことをいい、勾留は、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定をすることによって開始されます。
勾留決定がなされると、10日間にわたり、拘置所や留置所において、身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証がなされたりします。
勾留期間の10日目には、検察官が、大きく分けて、被疑者を釈放若しくは起訴するか、勾留を延長するかという選択をします。
まず、検察官が10日間の勾留期間中に必要な捜査が終了し起訴できると判断した場合は起訴されますし、これ以上勾留の必要性がないと判断し、不起訴を決定した場合には、被疑者は釈放されることになります。
他方で、検察官がさらに身柄拘束を行って捜査を継続する必要があると判断した場合には、刑事訴訟法上、1回に限り勾留の延長を請求することができると定められています。
上記の勾留延長の期間については最大でも10日間とされており、DVの程度や被疑者のこれまでの取り調べ状況及び被害者の感情等が総合的に判断されることになります。
このように勾留延長されてしまうと、逮捕から起算すると最大で23日間もの間、身柄拘束がなされてしまうことになります。
早期釈放に向けた活動
以上のような勾留及び勾留延長に対して、弁護士としては、被疑者が少しでも早期に釈放されるよう働きかける活動を行うことになります。
勾留がなされる前の段階において、弁護士として行うことができる活動としては、まず選任後すぐに被疑者と面会を行い、事件の詳細を聞いて今後の見通しを被疑者に伝えるという初回接見という活動が挙げられます。
この活動によって、逮捕されてしまった被疑者の心理的負担を軽減し、黙秘権や調書訂正申立権、署名拒否権といった権利があることを伝えることが可能となります。
また、弁護士の主な活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
上記の事例のように、被害者である彼女が、加害者であるAさんともう2度と会いたくないと主張している場合には、当事者間やその家族での円満な示談交渉は事実上不可能であるといえます。
一方、弁護士が介入する場合には、被害者としても心理的圧迫等を感じることなく、示談交渉を円滑に進められることも考えられます。
被害者との間で早い段階で示談が成立すれば、場合によっては勾留請求そのものが却下される可能性があり、身柄拘束の期間を非常に短縮することが可能になりますし、勾留期間中であっても、勾留決定が取り消される可能性が出てきます。
刑事事件に強い弁護士
このような弁護活動は迅速性と専門性が要求されることになるので、暴力事件に巻き込まれた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が確かな知識と経験を元に弁護活動をさせていただきます。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
金融機関を偽って融資を受けたら詐欺罪に発展
金融機関を偽って融資を受けて詐欺罪に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
金融機関を偽って融資を受けたら詐欺罪に発展
千葉県四街道市に住む自営業のAさんは、資金運用をしようと考えていました。
そんな矢先、会社を経営する知人から「フラット35でマンションを買ってその部屋を自分で使わずに返済する金額以上の金額で誰かに賃貸すれば、利益が得られる」と聞きました。
そこで、Aさんは金融機関に行って、自身が住むように偽って四街道市内のマンションを購入するための資金を借り入れたのです。
その際、金融機関からは「ご自身が住むということで間違いないですよね。」と何度も念押しされましたが、自分が住むために購入すると嘘をつき、その旨が記載された書類にも署名等しました。
こうしてAさんは、四街道市内にマンションを購入することができたのですが、購入後すぐに見つかると思っていた入居者が見つからず、家賃収入を得ることができず、次第に金融機関への返済が滞り始めてしまったのです。
その結果、金融機関が調査に乗り出したらしく、借入時にAさんの嘘がバレてしまいました。
金融機関の代理人弁護士から「刑事告訴する」旨の通知を受けたAさんは、今後どうなっていしまうのか不安でなりません。
※フィクションです。
借金を返済していても刑事事件に発展するのか?
借金の返済をめぐるトラブルについて、仮に借金を返済出来ないからと言ってすぐに刑事事件に発展するわけではありません。
では、どのような場合に問題となるかというと、「相手を偽って金を借りた(ローンを組んだ)場合」が問題となるのです。
ケースで用いたフラット35とは、民間金融機関と独立行政法人である住宅金融支援機構が提携して取り扱っている固定金利住宅ローンで、本人が住むことを条件に金を貸しています。
一方でAさんは投資運用のために住宅を購入する目的で、金融機関に対して嘘をついて申請をしていることから、相手を欺罔して金銭を受け取っていると評価され、詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪は、「相手方が事実を知れば財物の交付をしないであろうというべき重要な事項につき虚偽の意思表示をする」ことで、相手方が騙され、相手方から金品を受け取った場合に成立します。
詐欺罪
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
この他、例えば金融機関に対して収入や職業などを偽って借り入れした場合等も詐欺罪の適用が検討されます。
また、最近ではスマートフォンや銀行口座を、自分で使う目的がないにも拘らず契約・口座開設した場合にも詐欺罪が適用されています。
これらで得たスマートフォンやキャッシュカードは、最終的に特殊詐欺事件などで用いられることがあるため、このような詐欺事件を起こすことは絶対に避けるべきです。
刑事事件と民亊事件の違い
刑事事件は、法律に記載されている禁止事項に違反した場合に警察をはじめとする捜査機関が捜査を行い、検察官が捜査で得た証拠や自身で行った取調べの状況を踏まえ起訴するか否か検討し、起訴した場合には裁判官が刑罰の判断を行うというシステムです。
一方で民事事件は、一般人同士の紛争を解決する問題になります。
つまり、ケースの場合は詐欺という法律に違反するということで刑法が定める詐欺罪に当たることから刑事事件で懲役刑などの刑罰を受けるほか、不正融資に基づいて金を貸していることから「直ぐに全額返還するように」という民事上の請求を行う可能性があります。
なお、(詐欺罪に財産刑の罰条はありませんが)刑事事件で罰金刑・科料といったかたちでお金を支払う刑罰を受けることがありますが、これは国庫に帰属するものであり、例えば被害者の弁済に充てられるなどのことはありません。
刑事事件と民事事件は別の手続きですので、罰金や懲役刑を受けたからと言って民事上の債務が無くなるわけではありません。
刑事事件に強い弁護士
千葉県四街道市において、詐欺罪などの刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、事件の内容にかかわらず刑事事件に関するご相談は初回無料で承っております。
まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
市川市の刑事事件 殺人未遂事件の刑事責任能力
殺人未遂事件の刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~殺人未遂事件の刑事責任能力~
◇事件◇
会社員のAさんは市川市の建設会社に勤めています。
先日、仕事を終えて会社の同僚と共に、会社の近くにある居酒屋に飲みに行きました。
そこでビールや焼酎を飲んだAさんは相当酔っ払い、その後の記憶がありません。
翌朝、目を覚ますとAさんは、千葉県市川警察署の留置場でした。
そしてのその日の取調べで、担当の刑事さんから「居酒屋でトラブルになった若者を殴り倒し、居酒屋の階段から突き落とした。被害者は階段から転げ落ちて、頭を強打し全治1カ月の重傷を負って入院している。殺人未遂罪で現行犯逮捕した。」と、昨夜の出来事を聞かされました。
そして、Aさんの家族が手配した弁護士と面会したAさんは、弁護士から、今後の手続きや、処分の見通しを聞き、早急に被害者との示談を望んでいます。
(フィクションです。)
刑事事件が報じられるニュースなどで「刑事責任能力」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。
刑法においては、心神喪失者の行為は罰しない(刑法第39条1項)、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する(同第39条2項)と、責任能力のない者の行為についての規定があります。
Aさんのように、記憶を失うほど酒に酔っていた時の行為は、刑事罰の対象となるのでしょうか?そこで、本日はAさん起こした事件と責任能力について検討します。
◇殺人未遂罪◇
人に暴行して傷害を負わせると「傷害罪」で逮捕されるのが通常ですが、暴行の程度や被害者の怪我の程度によっては、Aさんのように、殺人未遂罪で逮捕される場合もあります。
殺人(未遂)罪が成立するには、行為者に「殺意」が必要となりますが、殺意とは殺人の故意であって、これは行為者の心の声です。殺意があるか否の真相は行為者にしか分からず、当然、第三者が知り得ることはできません。
取調べ等において「相手を殺そうと思った。」とか「相手が死んでも構わないと思った。」と供述すれば、殺意は明らかなものになりますが、供述がなくても被害者に対する暴行の程度や内容と、被害者の怪我の程度等によって総合的に判断され、客観的に殺意が認められてしまう場合があります。
Aさんの事件を検討しますと、被害者の顔面を殴る程度の暴行ですと「傷害罪」が適用されるにとどまるでしょうが、被害者を階段から突き落としている行為については
・故意的に階段から突き落としたのかどうか。
・階段の何段目から突き落としたのか。
・階段の形状。
等が総合的に考慮されて、「殺人未遂罪」が適用される可能性があります。
◇責任能力◇
お酒を飲んで記憶がなくなるほど酩酊している場合の行為は、刑事罰に問われないのでしょうか?
前述したように、刑法では、心神喪失者や心神耗弱者の行為に対しては、刑事責任能力が認められず、刑の免除や減軽を規定してますが、お酒に酔った酩酊状態での行為も、これに該当するのでしょうか。
「お酒に酔って酩酊状態=刑事責任能力がない」ではありません。一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されますので、どの程度のアルコールを摂取し、犯行時にどの程度酩酊していたのかが、重要な判断基準になると考えられています。
酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば、刑法第39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらず、完全な責任能力が認められる可能性が非常に高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
Aさんの事件を検討しますと、取調べにおいて「酒に酔っていて何も覚えていない。」と供述したとしても、それだけで「刑事責任能力が認められないほど酩酊していた。」とは認められないでしょう。これまでのAさんの酒癖や、実際に飲んだお酒の量、そして犯行前後の言動が総合的に考慮されて、判断されることなるのです。
実際にこれまで、お酒に酔って酩酊状態であるとして「心神耗弱」が認められた事件もありますが、単純酩酊の場合は、責任能力は認められると思われますので、不安な方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。