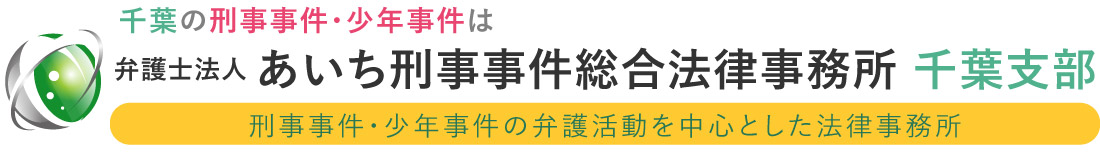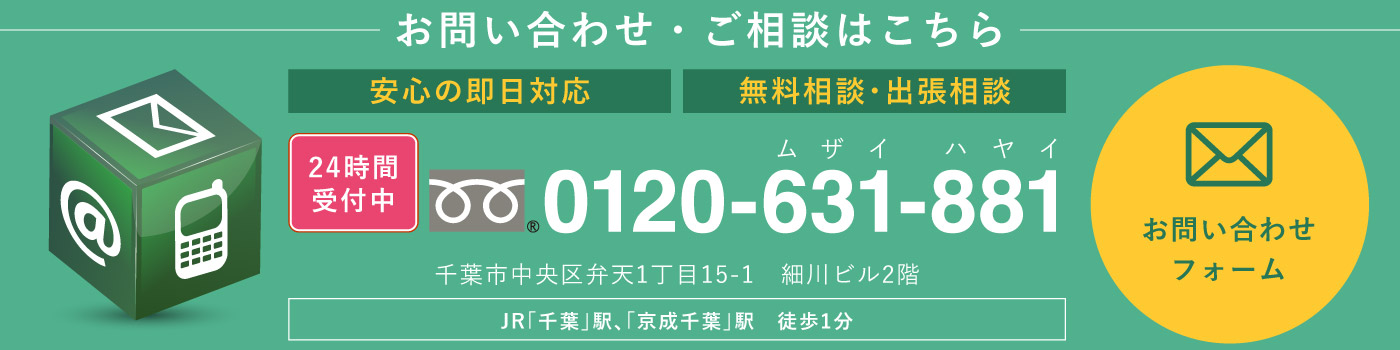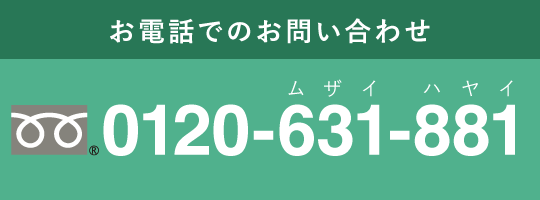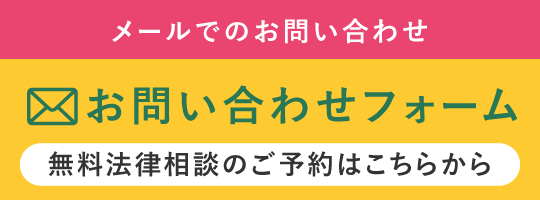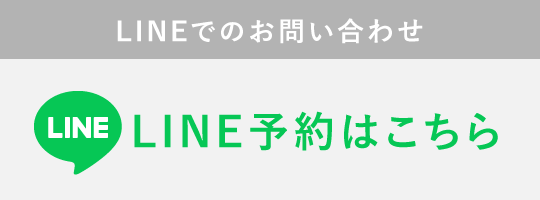Archive for the ‘刑事事件’ Category
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
Aさんは、交際相手から交際の解消を言い渡されたことに大きなショックを受け、千葉県千葉市花見川区の居酒屋に酒を飲みに行きました。
そこで大量に飲酒したAさんは、千鳥足で近くに停めていた自身の自動車に乗り込み、自宅へ帰ろうと周辺の道路を走行しました。
その際、道中にあったVさん宅のコンクリート壁に車体を擦らせてしまったうえ、その様子を千葉北警察署の警察官に目撃されました。
警察官は、Aさんが明らかに酒に酔った状態であったことから、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転は文字どおり酒を飲んで運転する行為を指し、その危険性と刑罰の存在は公共の場所に貼られたポスターなどでたびたび目にするところです。
ですが、飲酒運転が酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられていること、道路交通法上異なる罰則が定められていることは、意外と知られていないのではないかと思います。
まず、酒気帯び運転は、身体に一定以上のアルコールを保有した状態での飲酒運転です。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血中であれば0.3mg/mL、呼気中であれば0.15mg/Lです。
実務上よく目にするのは呼気検査なので、0.15mgの方を覚えておくとよいかもしれません。
他方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での飲酒運転です。
酒気帯び運転のように数値が基準となるわけではなく、その判断は酒酔い運転の嫌疑を抱いた警察官の判断によります。
具体的な判断に当たっては、白線の上をまっすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などが見られることになるでしょう。
それぞれの罰則を見てみると、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転が5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
これらは決して軽いものではなく、もし繰り返せば懲役の実刑となる可能性も否定できません。
たとえ事故を起こさずとも、飲酒運転自体重大な行為であることは認識しておくべきでしょう。
【逮捕の種類】
刑事事件においては、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に、捜査機関が逮捕を行うことがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
まず、通常逮捕とは、裁判官から逮捕状の発付を受けて行う逮捕です。
裁判官は逮捕という身体拘束の当否を判断する役割を持ちますが、実務上捜査機関による逮捕状の請求が拒否されることは多くありません。
被疑者の自宅あるいは取調べ中の警察署で逮捕状を見せて逮捕するのが一般的ですが、被疑事実および逮捕状が出ている旨告げて逮捕状を見せることなく逮捕することもあります。
次に、現行犯逮捕とは、犯行の最中かその直後の被疑者に対し、逮捕状の発付を受けることなく行う逮捕です。
誤認逮捕のおそれがなく、なおかつ被疑者の身柄確保の要請が強いことから、現行犯についてのみ例外的に逮捕状なくして逮捕できるようになっています。
現行犯であれば比較的軽微な事件でも逮捕される傾向にありますが、そうしたケースでは逮捕後2日程度で釈放されることも少なからずあります。
最後に、緊急逮捕とは、一定以上の重大な罪を犯した者につき、罪を犯した疑いが十分ある場合に行われる逮捕です。
犯罪の重大性と嫌疑の程度の要件が通常の逮捕より厳格になっており、事後的な逮捕状の取得を条件に逮捕状なくして行われるものです。
以上のとおり、逮捕には大きく分けて上記3種類が存在し、それぞれにつき法律上様々な制限が存在しています。
弁護士の力を借りれば、逮捕の違法性を突いて事件をよい良い方向へと導けることもありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、その能力をいかんなく発揮して依頼者様の利益を図ります。
ご家族などが飲酒運転をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円
傷害致死罪の弁護活動
傷害致死罪の弁護活動
千葉県千葉市中央区に住むAさんは、夫のVさんが定職に就かず外を遊び歩いていることを日頃から疎ましく思っていました。
ある日、AさんはVさんに交際費名目でお金を要求されたことから、ついに我慢の限界に達してVさんに不満をぶつけました。
それがきっかけでVさんから暴力を振るわれたため、Aさんは強い怒りを覚えてVさんを自宅の階段から突き落としました。
後にこの行為が原因でVさんが死亡したことが発覚し、Aさんは傷害致死罪の疑いで千葉中央警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、弁護活動をどう進めていくか検討することにしました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪は、他人に対して傷害を負わせ、それが原因でその他人が死亡した場合に成立する可能性のある罪です。
人を死亡させる点では殺人罪と共通ですが、人を殺害する意思(殺意)がない場合は傷害致死罪に当たります。
傷害致死罪の成立を肯定するには、①傷害の存在、②死亡の発生、③①と②との因果関係が必要です。
つまり、傷害とは無関係に死亡が生じた場合には、死亡の事実まで責任を負わせられないとして傷害罪が成立するにとどまることになります。
ただし、場合によっては、死亡の原因が傷害による受傷以外であっても傷害致死罪に当たることがあります。
裁判例には、激しい暴行を受け暴行の現場から逃走した被害者が、高速道路に進入して事故により死亡した事件で、傷害致死罪の成立を肯定したものがあります。
この事件では、暴行が直接の死因ではないものの、激しい暴行と高速道路への侵入に一定以上の結びつきがあるとして因果関係の存在が肯定されました。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
関連する罪の法定刑を見てみると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、殺人罪が死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役です。
このように、法定刑に大きな違いが見られるため、事案の内容次第では後述のように弁護活動を尽くす必要があるでしょう。
【傷害致死事件の弁護活動】
先ほど触れたように、傷害致死罪は殺人罪と傷害罪のそれぞれに共通点を見出すことができます。
こうした複数の罪の成否が問題となる事件では、より軽い罪の成立を目指して弁護活動を行うべきです。
ただ、そうした主張を行ううえで、深い法律の知識が必要となる点は否定しがたいところです。
法律の専門家である弁護士への依頼は不可欠と言っても過言ではないでしょう。
具体的な弁護活動について見ていきます。
まず、想定されるケースとしては、殺意がなかったにもかかわらず殺人罪を疑われるというものが考えられます。
殺意というのは人の内面であるため、究極的には本人以外誰も知ることができません。
そこで、裁判においては、あらゆる客観的な事情から殺意の有無が推認されることになります。
たとえば、刃渡りの長い包丁で心臓付近を何度も突いた形跡があれば、殺意が存在したと評価されることが予想されます。
ですが、実際の事件では、客観的な事情を考慮しても殺意があったか微妙なケースがあります。
そうしたケースでは、弁護活動により傷害致死罪が成立するにとどまると主張することが大切になります。
また別のケースとして、一見傷害致死罪のように思えるものの、傷害行為と死亡との間に因果関係があったか疑わしいというものが考えられます。
たとえば、被害者が突発的な死亡を引き起こす持病を持っており、偶然にも傷害と時を同じくしてその症状が出た可能性がある場合です。
この場合には、因果関係の存在を否定して傷害罪が成立するに過ぎないと主張することも考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験している弁護士が、よりよい弁護活動を目指して日々奔走しています。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円
不正アクセス事件で勾留取消
不正アクセス事件で勾留取消
Aさん(21歳)は、千葉県習志野市にある大学の講義室でパソコンを使っていたところ、隣にいるVさんがメモに何か記載しているのが見えました。
その後、Vさんが席を立った隙にAさんがメモの内容を見たところ、そのメモには銀行の名前と契約者番号およびパスワードが書かれていました。
試しにAさんがその情報をインターネットバンクで入力してみたところ、Vさんのものと思しき口座にログインできました。
そこで、犯行が発覚しづらいよう、Aさんは自身の口座に小額の送金を何度か行いました。
のちにこの事実が発覚し、Aさんは不正アクセス禁止法違反および電子計算機使用詐欺罪の疑いで習志野警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消を視野に入れて弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
一般的に、不正アクセスとは、本来であればアクセスできないコンピュータにアクセスする行為を指します。
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)という法律が制定されています。
上記法律が定める「不正アクセス行為」とは、アクセス制御機能によるコンピュータの利用制限を解除し、本来できないような利用行為をできるようにすることです。
他人のIDとパスワードを入力する、コンピュータに不正な指令や情報を与える、といった行為が、不正アクセス行為の主な手段です。
この不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、上記事例のAさんは、不正アクセス行為を行ったうえで不正送金も行っています。
そうすると、他人のコンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得たとして、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性もあります。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役という重いものです。
これに不正アクセス禁止法違反が重なるとなると、刑罰は厳しいものになるおそれがあるでしょう。
【勾留取消による釈放】
上記事例のような不正アクセス事件は、複数の犯罪が成立することにより重大な事件として扱われる可能性があります。
そうすると、捜査機関が逃亡や証拠隠滅を疑いやすくなるため、逮捕・勾留により身柄を拘束される可能性が高まると言えます。
その場合、勾留前や勾留直後の釈放が狙いにくいことから、勾留取消という手段に及ぶことが考えられます。
勾留取消とは、勾留の開始後から事情が変わったことを理由に、裁判官が釈放の判断を下すことを指します。
勾留の当否は裁判官が判断しますが、その判断は逮捕から2~3日後の時点で存在する事情に基づいて行われます。
その後の事情の変化は逐一裁判官が把握するわけではないため、時に本来であれば不必要な身体拘束が行われる危険があります。
そこで、弁護士が裁判官に勾留取消を促す申立てをするのが重要となります。
弁護士が事情の変化をきちんと裁判官に伝えれば、裁判官がもはや勾留を継続する必要はないとして勾留取消の判断を下すことが期待できます。
これにより、逮捕直後は釈放が認められにくい事案において、事情の変化を知らせることでいち早く釈放を実現できるというわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留取消をはじめとする身柄解放活動に詳しい弁護士が、釈放を目指して様々な手段を試みます。
ご家族などが不正アクセス事件を起こして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
習志野警察署までの初回接見費用:36,700円
公然わいせつ罪の再犯防止
公然わいせつ罪の再犯防止
Aさんは、千葉県山武郡横芝光町にあるコンビニの駐車場にて、車を停めて自慰行為に及びました。
Aさんの車の窓は特に遮蔽などされておらず、外から車内の様子が目に入るような状態でした。
そのため、車内が周辺住民のVさんの目に入ったうえ、偶然AさんはVさんと目が合ってしまいました。
それを受けてVさんが警察に通報したことから、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで東金警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんに事件を依頼された弁護士は、Aさんに公然わいせつ罪の前科が複数あることを考慮し、再犯防止について検討ことにしました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は、その名のとおり公然とわいせつな行為を行った場合に成立する可能性のある罪です。
強制わいせつ罪や強制性交等罪などと異なり、特定の個人ではなく社会一般を害する罪とされている点で特徴的です。
まず、「公然」とは、不特定または多数人が認識することができる状態を指します。
不特定か多数人のいずれかに当てはまればよいため、「公然」が否定されるのは特定かつ少数人が存在する場だけと言うことができます。
また、認識が可能でさえあれば、実際に公然わいせつ罪に言うわいせつな行為を何人が目撃したかという点は問題となりません。
つまり、不特定または多数人が認識できる場で行為に及べば、結果的に目撃者が特定の1人だったとしても「公然」に当たる可能性があります。
次に、「わいせつな行為」についてですが、これは強制わいせつ罪に当たる「わいせつな行為」とは必ずしも重なりません。
なぜなら、社会一般が被害者となる関係上、社会一般の感覚からしてわいせつな行為に当たるかどうかという視点も加味されるからです。
個人と社会一般とで捉え方に違いが出る行為の例として、キスを挙げることができます。
無理やりキスをすれば強制わいせつ罪に当たる可能性がありますが、その様子を周囲が目撃したことを理由とする公然わいせつ罪の成立は定しがたいでしょう。
【刑事事件と再犯防止】
刑事事件において、再犯防止が重要視されることが少なからずあります。
これは、刑罰を科す目的として、罪を犯した者に対する制裁だけでなく、再犯防止もあると考えられているためです。
刑罰を科すことで、罪を犯した者に矯正を促したり、その他の一般人に注意を促したりするというわけです。
逆に考えると、罪を犯した者が自主的に更生を目指しているのであれば、過度に重い刑罰は必要でないように思われます。
そこで、再犯防止の措置をとることが、刑の内容を妥当なものにするうえで大切になることがあります。
特に、同一あるいは類似の罪を複数回犯しているとなると、規範意識が薄れているとして刑罰は重くなりがちです。
上記事例において問題となっている公然わいせつ罪には、性的嗜好という面でそうした再犯が問題となりやすいことは否定できません。
そうすると、量刑を決める裁判官としても、やはり厳しい刑を科さなければ再犯に及ぶのではないかという点が懸念されるのです。
ここで再犯防止策がきちんと講じられていることをアピールできれば、そのことが刑の減軽につながることも十分ありえます。
弁護士は再犯防止についても造詣が深いことが多いので、特に前科が複数あって不安であれば、弁護士に相談してみることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、再犯防止に向けてあなたと一緒に闘います。
公然わいせつ罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円
同意殺人罪で情状弁護
同意殺人罪で情状弁護
~事件~
千葉県内に住む看護師のAさんは、千葉県山武郡芝山町に住むVさんと交際していました。
最初こそVさんと順調に交際していたAさんでしたが、時が経つにつれだんだんとVさんの欠点が目につくようになりました。
AさんはVさんに何度か改善を求めましたが、一向に変化がなかったことから、Vさんに交際の解消を切り出しました。
すると、Vさんは酷く取り乱し、「別れるぐらいなら私を殺してほしい」とAさんに訴えかけました。
Vさんの要求が激しかったことから、Aさんは仕方なくVさんの首を絞めて殺害しました。
その後、Aさんは自身の過ちに気づいて東金警察署に自首したため、殺人罪の疑いで逮捕されました。
そこで、Aさんの弁護士は、同意殺人罪の成立を主張するとともに、情状弁護の準備を進めることにしました。
(フィクションです。)
【同意殺人罪について】
同意殺人罪は、本人の承諾を得て相手方を殺害した場合に成立する可能性のある罪です。
相手方を殺害することは殺人罪と共通ですが、相手方の同意があるという点で大きく異なります。
暴行罪や傷害罪は、相手方の同意があれば犯罪不成立となるのが原則です。
これは、被害者が暴行や傷害に同意することで、社会一般の感覚からして違法性が欠けると評価できるからです。
ただ、このことを生命の侵害にも当てはめると、生命がもつ究極の価値を無碍に扱うことになりかねません。
そこで、同意殺人罪を規定する一方、同意の存在という点を考慮して法定刑を殺人罪より軽いものにしているわけです。
両罪の刑は以下のとおりです。
・同意殺人罪…6か月以上7年以下の懲役または禁錮
・殺人罪…死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれか
こうしてみると、同意殺人罪の刑が以下に軽くされているかが分かります。
場合によっては、被害者が殺害に同意していたかという点について、弁護士と検察官が激しく争うこともありうるでしょう。
【情状弁護の意味】
同意殺人罪の法定刑が殺人罪より遥かに軽いとは言え、殺人の一種である以上重大な罪であることは否定できません。
示談が困難ということも考慮すると不起訴は狙いにくいですし、罰金刑が定められていないため略式手続というわけにもいきません。
そのため、同意殺人罪を疑われた場合は、正式裁判が行われると考えても差支えはないでしょう。
正式裁判においては、被告人に有利な事情を主張して量刑を少しでも軽くするという弁護活動が考えられます。
これが情状弁護と呼ばれるものであり、ありとあらゆる事件において行うことができる重要な弁護活動と言えます。
先ほど指摘したように、同意殺人罪の法定刑は6か月以上7年以下の懲役または禁錮です。
この重さであれば、情状弁護の内容次第で、宣告される懲役または禁錮が3年以下となって執行猶予が付く余地が出てきます。
情状弁護において主張すべき事情は、事件の内容や被告人の人間性などにより千差万別と言っても過言ではありません。
検討すべき事情としては、犯罪に至った経緯、罪を犯す以外の手段を選択できたか、犯行後の行動・供述、などがあります。
弁護士に相談すれば、情状弁護のために主張するのが効果的な事情が見つかりやすいかもしれません。
ですので、罪を犯したもの以上どうしようもないと諦めたりせず、一度弁護士に相談して情状弁護による刑の減軽を目指してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりに合わせた最適な情状弁護を行うべく丹念に事件を検討します。
ご家族などが同意殺人罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円
建造物損壊罪の逮捕の可能性
建造物損壊罪の逮捕の可能性
~事件~
千葉県山武郡九十九里町に住むAさんは、近所にある弁当屋で買い物をしようとしたところ、会計の際に財布を持ってき忘れたことに気づきました。
そのことを店員に告げたところ、店員が冷たい態度をとったように思えたため、その弁当屋に恨みを持つようになりました。
そこで、ある日の深夜、Aさんは閉店中の弁当屋の壁にスプレーで適当に落書きをしました。
その落書きは水や通常の洗剤では容易に消すことができず、それなりの金額で専門の業者に依頼してやっと綺麗になるようなものでした。
翌日、Aさんは人づてに弁当屋の店長が怒り狂っていることを聞きました。
不安になって弁護士に相談したところ、Aさんは建造物損壊罪の成否と逮捕の可能性について説明を受けました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪について】
建造物損壊罪は、建造物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
類似の罪として器物損壊罪が挙げられますが、単に対象物が異なるに過ぎないと割り切るべきではありません。
器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
それに対して、建造物侵入罪の法定刑は5年以下の懲役のみとなっています。
建造物という対象物の重大性から、こうしたかたちで器物損壊罪より建造物損壊罪の方が重く見られています。
建造物損壊罪における「損壊」には、物理的な破壊のみならず、建造物の外観を損なうような状態にすることも含まれます。
上記事例では、Aさんが水や通常の洗剤で落ちないような塗料で弁当屋を汚損しています。
こうしたAさんの行為も「損壊」に当たる可能性があり、そうであれば建造物損壊罪が成立する可能性はあります。
また、建造物損壊罪が成立しなかったとしても、みだりに他人の家屋を汚したとして軽犯罪法違反になる可能性が別途考えられます。
ただ、軽犯罪法違反の法定刑は拘留(1日以上30日未満の留置)または科料なので、建造物侵入罪が成立する場合より刑は著しく軽くなるでしょう。
【逮捕の可能性】
刑事事件では、逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、逮捕により被疑者の身柄が拘束されることがあります。
場合によっては、逮捕から2~3日後に、引き続き拘束を続ける必要があるとして勾留(拘留との違いに注意)という10~20日の拘束が行われることもあります。
刑事事件において逮捕を行うかどうかは、基本的には警察をはじめとする捜査機関に委ねられています。
捜査機関は個々の事案毎に逮捕すべきかを判断することになるので、ある罪を犯した場合について逮捕されるまたはされないと断言するのは難しいです。
ただ、捜査機関も逃亡などの防止という観点から逮捕の当否を検討しているであろうことは想像がつきます。
そのため、弁護士が具体的な事件の内容を聞けば、逮捕の可能性を高いもしくは低いというかたちで答えることは可能な場合があります。
逮捕の可能性を検討するうえで外せない要素は、やはり事件の重大性です。
重い罪であったり複雑な事件であったりすればするほど、逃亡や証拠隠滅の可能性が一般的に高く、結果的に逮捕の必要性が高いことが予想されるためです。
上記事例は、①建造物損壊罪という軽くない罪であること、②深夜に密かに犯行がなされたこと、③他人から見てコンビニの信用に関わる可能性があること、などの要素が含まれます。
こうした要素から、重大な事件として逮捕の可能性が高まることはありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕の可能性を含む事件の見通しを可能な限り具体的にお伝えします。
建造物損壊罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円
通貨偽造罪で不起訴
通貨偽造罪で不起訴
~事件~
Aさんは、千葉県香取郡東庄町の自宅で小規模の塾を経営しています。
ある日、Aさんは生徒に算数を教えるに当たり「本物のお金に似た教材を使ったら楽しく学べるかもしれない」と思い至りました。
そこで、Aさんは自宅のプリンターを用いて、一般人であれば一瞬本物と見間違えるようなお札を作成しました。
それを授業で利用したところ、Aさんの生徒2名が無断で持ち帰り、近所のコンビニで利用しました。
これにより、Aさんは家宅捜索ののち通貨偽造罪の疑いで香取警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに行使の目的がなかったことを主張して不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【通貨偽造罪について】
通貨偽造罪は、真正な通貨として買い物などに使う目的で、日本で流通している硬貨や札などの通貨を偽造した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「偽造」とは、通貨を作成する権限のない者が、真正な通貨に似た見た目のものを作成する行為を指します。
仮に既存の真正な通貨に加工を加えた場合は、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たる可能性があります。
また、通貨偽造罪にせよ通貨変造罪にせよ、作成される通貨は一般人が真正な通貨と見間違うような見た目のものでなければなりません。
先ほど少し触れましたが、通貨偽造罪の成立を肯定するには、買い物などの本来の用法に従って通貨を流通させる目的がなければなりません。
ですので、こうした目的を欠いたまま偽造を行えば、通貨偽造罪の成立は否定される余地が出てきます。
上記事例では、Aさんが本物の1万円札と見間違うような絵柄の紙を印刷しています。
この行為自体は偽造と言えそうですが、Aさんは飽くまで印刷物を教材として使う目的だったに過ぎません。
そのため、行使の目的を欠くことから通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
通貨偽造罪の法定刑は無期懲役または3年以上の有期懲役(上限20年)なので、もし有罪となれば厳しい刑が見込まれるでしょう。
【犯罪不成立を主張して不起訴を目指す】
先ほど説明したように、Aさんには通貨偽造罪が成立しない可能性があります。
こうしたケースでは、裁判で争って無罪を獲得する前に、検察官に犯罪の立証が困難と思わせて不起訴にすることが考えられます。
刑事事件について一定の捜査が完了すると、得られた証拠を参照しながら検察官が起訴するか不起訴にするか決定することになります。
検察官が起訴を選択すると裁判(略式手続を含む)になり、不起訴を選択すると事件は終了するのが基本です。
この不起訴には数多くの理由があるのですが、そのうちの一つに嫌疑不十分あるいは嫌疑なしというものがあります。
嫌疑不十分あるいは嫌疑なしによる不起訴は、犯罪の立証が困難あるいは犯罪が成立しないことが明らかな場合に行われます。
つまり、検察官が裁判において有罪を示すのが難しいと判断した場合は、上記理由により不起訴になる可能性があるのです。
上記事例では、客観的に見れば通貨偽造に当たる行為を行っている一方、Aさんの主観において通貨偽造罪の成立要件である「行使の目的」を欠くと考えられます。
このような事情を検察官が捜査の段階で把握すれば、裁判に至る前に不起訴というかたちで疑いが晴れることになるでしょう。
ただ、こうした内面に関する弁護活動には、取調べ対応をはじめとして難しい問題があります。
もし犯罪の成立を争って不起訴を目指すなら、弁護士による入念な弁護活動が極めて重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、不起訴を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが通貨偽造罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
香取警察署までの初回接見費用:43,100円
公務執行妨害罪で観護措置回避
公務執行妨害罪で観護措置回避
Aさんは、千葉県銚子市内の中学校に通う中学3年生です。
Aさんには悪友のBさんとCさんがおり、放課後に2人で遊ぶのが日課となっていました。
ある日、Aさんは学校近くの空き地でBさんらと集まり、着火剤とライターを用いて火遊びを始めました。
その様子を目撃した銚子警察署の警察官は、「君たち、何してるの」とAさんらに声を掛けました。
気が強くなっていたAさんは、近づく警察官に対して「おいポリ公。それ以上近づくと制服燃やすぞ」などと笑いながら言ってライターの火をかざしました。
この行為により、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
事件が家庭裁判所へ送致された後、Aさんの付添人となった弁護士は、Aさんの観護措置回避を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、公務員の職務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の手段となる暴行・脅迫は、暴行罪・脅迫罪に当たる一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い範囲の行為を指すことがあります。
上記事例では、Aさんらの行為を見つけて近づいてきた警察官に対し、Aさんが制服を燃やす旨告知してライターの火をかざしています。
このような行為は、普段数々の犯罪者と対峙する警察官にとって取るに足らない行為と思われるかもしれません。
ですが、こうした行為も職務の執行を妨害するおそれがある以上、公務執行妨害罪が成立する可能性はあります。
ちなみに、公務執行妨害罪を犯すに際して公務員に怪我などの傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪と併せて傷害罪が成立する可能性もあります。
そうなれば事件の重大性は高まるので、少年の要保護性は高いと評価されることがあるでしょう。
【観護措置回避を目指す】
被疑者を20歳未満の者とする少年事件では、通常の刑事事件とは異なり、保護処分という少年の更生および健全な育成を目指した措置が目指されます。
その関係で、そこに至るまでの手続も通常の刑事事件と比べて様々な違いが見受けられます。
少年事件に特有の手続の一つとして、家庭裁判所における諸々の手続があります。
その中に、少年に対する処分を決めるための調査および審判に向けて、少年の行動観察や精神鑑別などを行う監護措置というものがあります。
観護措置には在宅で行うものと少年鑑別所で行うものがありますが、実務上殆どの場合は少年鑑別所が選ばれます(収容観護)。
収容観護による観護措置の決定が下されると、少年は2週間から8週間(多くの場合4週間)少年鑑別所に収容されます。
これは通常の刑事事件の手続である逮捕・勾留が行われた後になされることもあり、そうなると身体拘束は長期に及んでしまいます。
この観護措置による不利益を回避するには、観護措置の必要性が薄く、なおかつ観護措置が行われた場合に生ずる不利益が大きいことを積極的に主張する必要があります。
こうした主張は少年事件に詳しい弁護士の得意分野なので、もし観護措置を回避して早期釈放を目指すなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避をはじめとしてお子さんの不利益を回避する様々な弁護活動を行います。
お子さんが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
銚子警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
ストーカー事件で前科回避
ストーカー事件で前科回避
~事件~
Aさんは、千葉県内の大学に通う学生(21歳)です。
Aさんは千葉県香取郡多古町に住むVさんと交際していましたが、Aさんがあまりに私生活に口を出すため、嫌気が差したVさんから交際の解消を言い渡されました。
ですが、諦めきれなかったAさんは、メールアドレスをいくつも取得してVさんに連絡したり、Vさん宅付近をうろついたりしました。
その後、Aさんは香取警察署から口頭で注意を受けましたが、その後も上記のようなストーカー行為がやまなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか前科を回避できないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)
【ストーカー行為について】
「ストーカー行為」と聞くと、相手方に電話やメールなどで何度も連絡したり、相手方につきまとったりする行為を想像されることかと思います。
日本において定められている「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(略称:ストーカー規制法)には、「ストーカー行為」の具体的な内容が定められています。
それによると、「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」と定義される行為を反復継続して行う行為を指します。
「つきまとい等」の具体的な内容は、つきまといなどの直接的な接触と、電話やメールなどの間接的な接触が代表的です。
そのほかに、行動の監視あるいはそう思わせる行為、乱暴な言動、不快感や嫌悪感を抱く物の送付、名誉や性的羞恥心を害するような発言、行動なども含まれます。
ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、そのストーカー行為について警察から禁止命令が出されていた場合、罰則の上限は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
禁止命令は刑事事件には至っておらず行政上の措置にとどまりますが、警察が警戒を強めているという点では注意すべきものです。
禁止命令が出ていれば逮捕の可能性も高くなってくるため、自分の中ではストーカー行為だと思っていなくとも細心の注意を払うべきでしょう。
【前科の存在による不利益】
刑事事件を起こして刑罰を科されると、その事実は前科というかたちで残ることになります。
一般的に「前科」という言葉の意味は複数ありますが、ここでは罰金以上の刑が確定したことを指すものとします。
前科には様々なデメリットがあると言えます。
まず、前科の元となった罪を犯した後で更に罪を犯した場合、規範意識が薄れているとして前科の存在が処分を重くする一事情となることが予想されます。
特に、同種前科、すなわち新たに犯した罪と類似あるいは同様の前科であれば、その危険性および事の重大さは増すことになります。
また、前科が存在することで、一部の資格の取得や職業への就職が制限される可能性があります。
たとえば、医療系の資格であれば、罰金以上の刑に処せられることが資格の取得を妨げる事情となることがあると法律で定められています。
また、身辺調査が行われたり前科の申告を求められたりする職業においては、前科の存在は著しい不利益につながります。
そのほか、海外渡航や選挙権が制限されることもあり、前科の不利益は多岐に渡ると言えます。
示談を行うなどして前科を避けるのは可能なことがあるので、もし前科による不利益が不安であれば、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する数多くの相談を受けてきた弁護士が、前科回避に向けてできる限りの弁護活動を行います。
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
香取警察署までの初回接見費用:43,100円
放火罪で控訴
放火罪で控訴
~事件~
千葉県香取郡神崎町にて、Vさん宅が何者かの手により放火されるという事件が起きました。
幸いにも火は比較的早期に消し止められ、他の建造物への延焼や負傷者の発生などはありませんでした。
この事件を受けて捜査を開始した香取警察署は、現場付近での目撃証言を聞いて現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
その後Aさんは勾留され、否認をしていたものの起訴されて裁判となりました。
Aさんは「きっと裁判で無罪になるだろう」と思っていましたが、予期に反して有罪となったため、Aさんの両親が弁護士に控訴を依頼しました。
(フィクションです。)
【放火罪について】
放火罪は、特定の物に放火し、その対象を焼損させた場合に成立する可能性のある罪です。
単に放火するだけでなく、それにより焼損させる、すなわち、マッチやライターなどの媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態に至らせることが必要となります。
放火罪には、①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3種類があります。
「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑であり、現住は住居として利用されていることを、現在は現に人がいることを指します。
つまり、住居あるいは人がいる建造物等を放火すれば①に、そのいずれにも当たらない建造物等を放火すれば②に当たることになります。
また、③については、成立に「公共の危険」を要するとされています。
ここで言う「公共の危険」とは、不特定または多数人の身体、生命、財産が害される危険を指します。
こうした危険が認められなければ③の成立は否定されますが、その場合には器物損壊罪の成否が問題となることがあります。
法定刑は、①が死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれか、②が2年以上の有期懲役、③が1年以上10年以下の懲役です。
いずれも重いものであり、懲役の実刑が科される可能性は一般的に高いと言えるでしょう。
【控訴について】
刑事事件では、所要の捜査が遂げられた後、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すことになります。
そして、起訴の判断が下された場合、略式起訴の場合を除いて正式裁判で犯罪の成否および量刑が決定されます。
正式裁判を経て有罪となっても、それにより判決の内容が直ちに確定するわけではありません。
判決は言い渡しの翌日を1日目として14日目の終了時に確定することになっており、それまでに控訴を申し立てることができます。
控訴とは、1回目に行われた判決(第一審)の内容に不服がある際に、より上級の裁判所である高等裁判所に判決の内容が妥当か審査してもらえる制度です。
上記事例のように、無罪を主張したにもかかわらず有罪となってしまったケースでは、控訴の申立てを検討するのが得策です。
控訴の申立てを認めてもらえる場合というのは限られており、たとえば裁判のやり方に重大な違法があった場合や、裁判の内容に判決に影響を及ぼす違法があった場合などです。
もし控訴の申立てを認めてもらえれば、検察官が控訴を申し立てない限り、第一審より悪い結果となることはありません。
この点において、控訴の申立ては積極的に行うべきだと言えます。
弁護士に事件を依頼すれば法的な問題をクリアできる可能性が高まるので、判決の内容に少しでも不満を感じたらぜひ控訴の依頼を検討してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、控訴審からの弁護活動も責任を持ってお引き受けいたします。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
香取警察署までの初回接見費用:43,100円