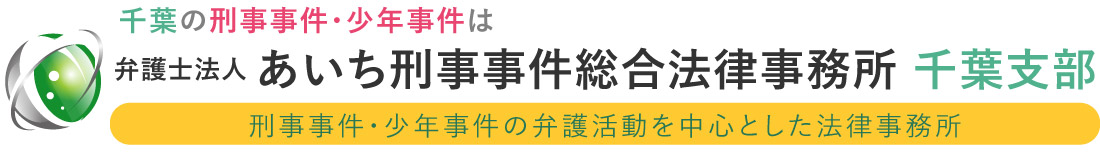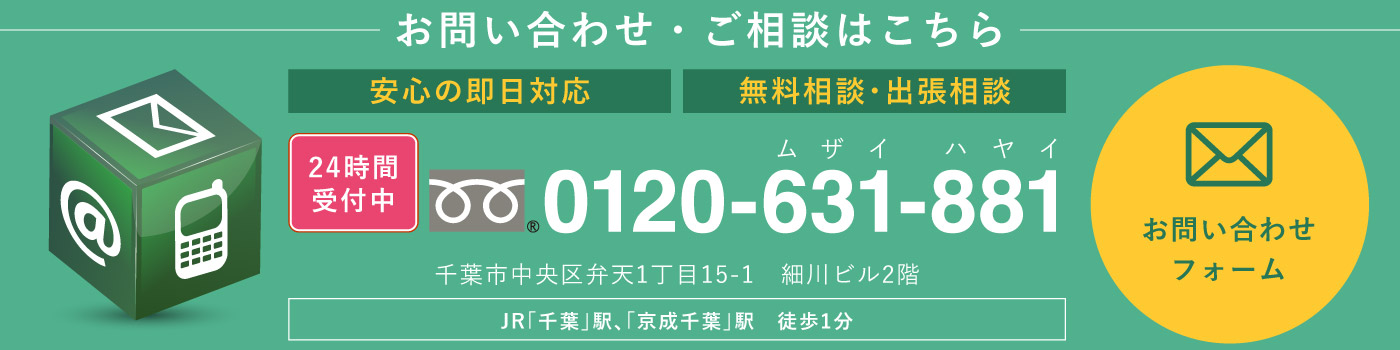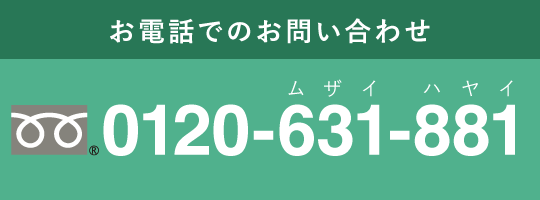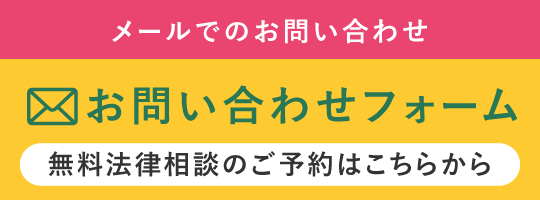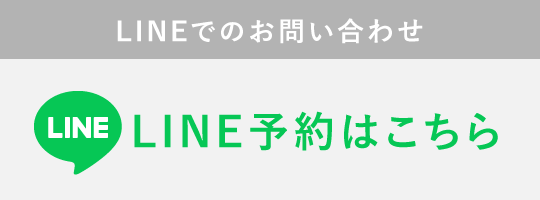Archive for the ‘交通事件’ Category
「フル電動自転車」で無免許運転 千葉市美浜区の交通事故
フル電動自転車の道路交通法上の扱いや、無免許運転で過失運転致傷罪に問われてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市美浜区のフル電動自転車事故
20代大学生Aさんは、千葉市美浜区内をフル電動自転車などと呼ばれる車両を無免許で運転していました。
AさんがT字路を左折したとき、歩道を歩いていたVさん(70代)に衝突し、Vさんに大けがを負わせてしまいました。
Aさんのフル電動自転車には、ナンバープレートの表示もなく、自賠責保険にも加入していませんでした。
Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで千葉西警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
フル電動自転車は原動機付自転車
フル電動自転車は、ペダル付電動自転車やペダル付電動バイクと呼ばれ、電動で自走する機能を備える自転車のことを指します。
フル電動自転車は道路交通法上の原動機付自転車にあたります。
なお、市販されている駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは全く違うものになります。
フル電動自転車を道路上で運転するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 原動機付自転車を運転することができる免許を受けていること
- 原動機付自転車の通行方法等によること
- 乗車用ヘルメットの着用義務があること
- 道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
- 自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
- 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両後面に見やすいように表示すること
これらの条件を満たさずに道路上を走行することはできません。
フル電動自転車で事故を起こしたら
上記した千葉市美浜区のAさんのように、フル電動自転車を無免許で運転し事故を起こした場合、過失運転致傷の罪に無免許運転の刑が加重され、10年以下の懲役が科される可能性があります。
もし、Aさんが事故を起こさず、ナンバープレートを表示しないまま運転していた場合でも、その行為は道路運送車両法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
フル電動自転車は、インターネット上で1台あたり数万円から十数万円程度で販売されていますが、公道での使用を想定していないものもあるようです。
手軽に購入できる反面、事故を起こした際の責任はとても重いです。
上記した千葉市美浜区Aさんのように無免許で人身事故を起こした場合、逮捕されるだけでなく、公判請求されたのち、実刑判決が下される可能性もあります。
無免許過失運転致傷の罪に問われたら
無免許運転で事故を起こしてしまった場合、被害者との示談が難航することがあります。
このような場合、弁護士に相談して示談成立に向けて活動することをおすすめします。
また、無免許運転で事故を起こしてしまったことで、今後どのような刑事処分が下されるのかも不安だと思います。
弁護士ならば、無免許過失運転致傷罪の処分軽減のための弁護活動も可能です。
もし、ご自身が無免許過失運転致傷罪の疑いで警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が無免許過失運転致傷罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・365日受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。
飲酒運転中の人身事故で危険運転致傷容疑で逮捕
危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市緑区在住のAさん(40代男性)は、飲酒運転中に自動車で歩行者をひいてしまい、歩行者に骨折等の怪我を負わせてしまった。
Aさんは、人身事故の通報を受けて駆け付けた警察官により、危険運転致傷罪の疑いで、千葉県千葉南警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、千葉南警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼し、その後に弁護士から、今後の事件の見通しについて接見報告を受けた。
Aさんの家族は、弁護士に刑事弁護を依頼し、Aさんの釈放活動や、事故被害者との示談交渉や、警察取調べの弁護対応に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~「危険運転」による人身事故の刑事処罰~
飲酒運転中に人身事故を起こし、被害者側が怪我をしたり、死亡した場合には、自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪に当たるとして、危険運転を受ける可能性が考えられます。
自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)は、2014年に法律が新しく施行され、自動車等の危険運転によって人を死傷させた場合に、従来より重い刑事処罰が与えられるようになりました。
以下に挙げるような危険運転の態様で自動車等を運転し、人を負傷させた者は15年以下の懲役刑、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役刑という法定刑の範囲内で、刑罰を受けることになります。
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態。(酩酊運転)
- その進行を制御することが困難な高速度。(制御困難運転)
- その進行を制御する技能を有しない。(未熟運転)
- 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(妨害運転)
- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法。(妨害運転)
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為。(高速道路等妨害運転)
- 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(信号無視運転)
- 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(通行禁止道路運転)
~人身事故の弁護活動~
人身事故が起こした場合には、警察の取調べに呼ばれて、事故のことを聞かれ、刑事処罰に向けた調書が作成されます。
警察の取調べは、日帰りで警察署への呼び出しを受けることもあれば、他方で、逮捕されて身体拘束を受けた上で、厳しい取調べを受けることもあります。
事故を起こしてから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談して、取調べの供述対応を検討し、逮捕を避けるための弁護方針や、釈放のための弁護方針を立てることが重要です。
また、人身事故のように被害者の存在する交通犯罪においては、弁護士を仲介とした示談交渉を行うことで、被害者側に謝罪や慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意を含む示談を成立させることが重要となります。
弁護士の側より、捜査機関や裁判所に対して、被害者との示談成立の事情を主張することで、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まることが期待されます。
まずは、危険運転致傷事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市緑区の危険運転致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
電動キックボードによる交通事故
電動キックボードを無免許で運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県市川市の電動キックボードによる交通事故
会社員Aさんは、千葉県市原市の県道で、電動キックボードを無免許で運転し、赤信号を無視し続け、時速40kmの速度で交差点に進入しました。
その時、Aさんは、横断歩道を通行していたVさんと衝突してしまい、Vさんに軽傷を負わせました。
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた千葉県市川警察署により、危険運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
電動キックボードの運転には免許が必要
キックボードに取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)により走行する電動キックボードは、道路交通法及び道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。
つまり、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
もちろん、走行できる場所についても、原動機付き自転車と同様に、車道に限られており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。
電動キックボードの交通違反の罰則
電動キックボードは前述したように、原動機付自転車に分類されるため、信号無視などをした場合は、道路交通法違反になります。
道路交通法に違反した場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2種類があります。
ここでは刑事処分について説明します。
例えば、原動機付き自転車の免許を受けていない者が、電動キックボードを走行させた場合、いわゆる無免許運転として扱われ、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があります。(同法第117条の2の2 第1号)
しかし、上記した千葉県市原市の例のように無免許で信号無視をし相手を負傷させた場合、自動車運転死傷行為等処罰法で規定される危険運転致傷罪に問われる可能性があります。
危険運転致傷罪の刑罰
自動車運転死傷行為等処罰法の第2条では、危険運転致傷罪にあたる行為がいくつか挙げられています。
同条1号は飲酒・薬物摂取状態での運転、2号でスピード違反、3号で技術がない状態での運転、4号で妨害行為、5号で赤信号無視、6号で通行禁止道路進行の危険運転行為がそれぞれ定められています。
上記した千葉県市原市の事件では、3号の技術がない状態での運転と5号の赤信号を殊更に無視により、人にケガを負わせているため、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
この場合の危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役とされており、起訴された場合、重い刑罰が下される可能性が非常に高いです。
電動キックボードによる事故の増加
電動キックボードをめぐっては、今年に入ってから交通事故の発生件数が増加しているようです。
警視庁交通捜査課の発表によると、東京都内では今年8月までに電動キックボードによる人身・物損事故が34件起きているようです。
電動キックボードは、運転免許のない人でも、ネット通販で数万円程度で購入することが出来るため、幅広い世代が手軽に購入することが可能です。
しかし、その手軽さから、公道を走るために必要な知識や、手続きを知らないまま、道路交通法を守らずに電動キックボードを利用してしまい、事故を起こしてしまった方もいるようです。
交通事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が交通事故を起こし、警察から取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は24時間、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
無免許運転で人身事故を起こしてしまった方の弁護活動
無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県富里市で発生した無免許運転の人身事故
会社員Aさんは、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、現在は無免許です。
しかし先日の大雨の日、どうしても行かなければいけない用事があったAさんは、、一度だけなら大丈夫だろうという安易な考えで無免許運転をしてしまいました。
そして大雨で視界が悪かったせいで、前方に赤信号のために停止していた車に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。
衝突した車の運転手に、むち打ちなどの傷害を負わせてしまったAさんは、通報で駆け付けた千葉県成田警察署によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
無免許運転の罪
「無免許」と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。
しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます。
ただしうっかりして免許の更新を失念していた場合、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。
過失運転致死傷罪の無免許運転による加重
過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されると規定されています。(第5条)
しかし、上記したAさんの事故のように、過失運転致死傷罪を故意的な無免許運転で犯した場合は、刑が加重されます。
「加重」とは、法定刑の範囲を超えて、刑を重くすることです。
同法第6条第4号において、無免許運転をし、過失運転致死傷罪を犯した場合は、無免許過失運転致傷罪が成立し、この罪は「10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります。
そのため、起訴された場合は、必ず公開の法廷で裁判を受けなければならず、無罪判決や執行猶予判決が下されない限り、刑務所にいかなくてはなりません。
無免許過失運転致傷罪の弁護活動
無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、
①取調べの際のアドバイス
②被害者との示談交渉
③裁判に向けた情状弁護の準備
などが考えられます。
たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。
ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。
もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉では、無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
警察から取り調べを受けている方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
千葉県印西市でひき逃げ事件 ひき逃げの刑事責任は?
千葉県印西市でひき逃げ事件を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県印西市のひき逃げ事件で取り調べ>
会社員Aさんは取引先の会社に向かうために、千葉県印西市内を自動車で走行している際、カバンの中の書類が気になり、カバンを手に取ろうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、歩行者Vさんに接触してしまいました。
Aさんは、車が接触した衝撃で被害者が転倒し怪我をしているのが分かりました。
しかし、事故を届け出ていると取引先との約束の時間に間に合わなくなると思い、車を停止させることなく、事故現場を走り去ってしまいました。
その後、事故の様子を目撃していた通行人が警察や救急に通報したらしく、その日の夜にAさんは、千葉県印西警察署に呼び出されて取調べを受けることになりました。
そこで警察官から、被害者のVさんが骨折等の大怪我を負っていること聞きました。
Aさんは、今後の手続きや刑事処分が不安で、ひき逃げ事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
<ひき逃げは何の罪に問われるのか>
1.過失運転致(死)傷罪について
過失運転致(死)傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に適用される罪です。
過失運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第5条において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
2.救護義務違反について
道路交通法第72条第1項前段では、交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに危険防止措置を講じなければいけない旨が規定されています。
これが事故を起こした車の運転手等に課せられている救護義務のことで、この義務を果たさずに逃走すれば救護義務違反となります。
ちなみに、救護義務違反の刑事罰は、誰の運転が原因で、交通事故が発生したのかによって異なります。
これは、道路交通法第117条に規定されており、救護義務違反した者の運転が原因でその交通事故が起こっていた場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法第117条第2項)」です。
一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起こっていた場合は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法第117条第1項)」となります。
3.警察への報告義務違反について
道路交通法第72条第1項後段では、運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10項の規定により、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」で処罰されます。
<ひき逃げ事件に強い弁護士>
過失運転致傷罪や、道路交通法違反(ひき逃げ)の弁護活動は、弁護士が被害者の方に対し、謝罪や見舞金支払いを提案するなどの交渉を進めることができます。
また、示談が締結し、被害者の方が加害者を許し、刑事処分を求めていないこと(宥恕)を検察官に伝えることで、不起訴処分を獲得できる可能性を高められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、交通事故を起こした被疑者の刑罰が軽くなるように、被害者の方への交渉や、捜査機関に対するはたらきかけをすることができます。
千葉県印西市でひき逃げ事件を起こし、警察から取り調べを受け不安を抱えている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
交通違反や交通事故に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
飲酒運転で略式手続
飲酒運転で略式手続
飲酒運転で略式手続を受けるケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Xさんは、千葉県千葉市に勤務する会社員でしたが、最近在宅勤務になり、残業がなくなったことから連日千葉県市原市にある自宅でオンライン飲み会を行っていました。
ある日、夕方6時頃からいつものようにお酒を飲み始めたところ、車で15分ほど行ったところにあるレンタルショップのレンタルDVDの返却を忘れていたことに気づきました。
Xさんは、まだ最初の1缶目を飲み終えたばかりで、まだそんなに酔ってはいないし大丈夫だろうと思い、自宅の車を使ってレンタルDVDを返却しようと思い、車に乗り込みました。
Xさんは、車を順調に走行していましたが、「早く帰って飲み会の続きに参加したい」と思い、一時停止を無視して車を走行してしまいました。すると、どこかで見ていたのか千葉県警市原警察署の警察官に停車を命じられました。
警察官は、当初、一時停止無視のみを咎め、反則金7000円を求めてきましたが、Xさんの呼吸からお酒を飲んでいるのではないかとの疑念を抱きました。
そこで、警察官は、Xさんに対し、呼気検査を行うよう要求しました。Xさんはしぶしぶ応じると、呼気アルコール濃度が0.2mg/lと出てしまい、酒気帯び運転として、警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
一般的に、飲酒運転は酒を飲んだあとに自動車などを運転する行為を指します。
ですが、飲酒運転という言葉は飽くまで日常用語であり、法律上は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
まず、道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として酒気帯び運転の禁止を定めています。
酒気帯び運転については、アルコールが①血液1ミリリットルにつき0.3グラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上ある場合に刑罰が科されます。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
更に、酒気帯び運転時において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だった場合は、酒酔い運転としてより重く扱われます。
酒気帯び運転の具体的な確認方法としては、警察官の問いに対してきちんと受け答えができているか、白線の上をまっすぐ歩けるかなどが考えられます。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。酒酔い運転とは、酒気帯び運転よりも重い刑罰が科されるものですが、必ずしも、体内のアルコール量が多ければ酒酔い運転になるというものではなく、アルコールの影響をその人がどれだけ受けているかを問題にする犯罪といえます。
要するに、少量のアルコールしか摂取していない人であっても、アルコールに弱かったり、その日は普段より酔いやすかったりする場合には、酒気帯び運転ではなく、酒酔い運転に当たる可能性があるということです。
酒気帯び運転や酒酔い運転は、確かに交通違反の一つではありますが、販促手続きが使えるものとは異なり、反則金を納めれば刑事手続きを免れることができるものではありません。
よほどのことがない限り、飲酒運転は厳禁だということを日頃から心に留めておく必要があるでしょう。
【略式手続とは】
酒気帯び運転で、体内のアルコール残留量が多くない場合で、かつ初犯のケースにおいては、多くのケースで正式裁判ではなく、略式手続により刑事罰が科されることが少なくありません。
略式手続とは、100万円以下の罰金を科す場合において、当事者が合意した場合、正式裁判によらずに、事務手続きのみで事件を終了させる手続です。
略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨、③書面による同意の確認が行われることになります。
略式手続と正式裁判との決定的な違いとしては、略式手続は簡易裁判所における書面審理のしか行わないため、自分自身が裁判所の法廷に行く必要がありません。
もっとも、一度略式手続に同意したものの、やはり裁判で争いたいと考えた場合、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられるのですが、それが送達されてから14日間は正式裁判できちんと争うよう求めることもできます。
略式手続による処理を行う場合、上記のように正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。
もし事実関係を争って無罪や刑の減軽を希望する場合には、略式手続ではなく、正式裁判で事実関係を争っていくこととなります。
どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし飲酒運転を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。
(無料法律相談のご案内はこちら)
飲酒運転と執行猶予
飲酒運転と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Xさんは普段はお酒を飲まないため、同僚や上司飲み会を断っていました。ところが、年末の忘年会だけはどうしても断ることができず、参加することになりました。
忘年会でもXさんはお酒を飲むつもりがなかったため、当日は自身の車で千葉県市原市にある会社まで通勤し、仕事終わりに、会社の近くにある居酒屋で会社の同僚と忘年会を行いました。
忘年会では飲むつもりはなかったXさんでしたが、社長から「乾杯くらいはいいだろ。あと数時間もすればお酒も抜けるよ。」と言われ、どうしても断ることができず乾杯だけすることにし、ビールをグラスで1杯だけ飲みました。
その後、Xさんはお酒を飲むことなく忘年会が終了し、自分の車で帰ることになりましたが、普段からの疲労と久しぶりの飲み会で気が緩んだのか、うとうとしてしまい、運転中、壁に激突してしまいました。
その後、通行人から通報があり、千葉県市原警察署の警察官がやってきて、呼気検査がなされ、その結果が呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.3mgであったため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで取り調べを受けることになりました。
実は、Xさんは、3年前に飲酒運転で罰金刑を受けたことがあり、今回注意をしていたのですが、すっかりアルコールが抜けていると思っていたので運転してしまっていたのでした。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転については、道路交通法に禁止規定と罰則が定められています。
まず、道路交通法65条は、「酒気帯び運転等の禁止」として、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
この規定が飲酒運転の禁止を定めたものです。
他方で、飲酒運転の罰則については、飲酒運転の具体的な内容に応じて以下のとおり2通り存在します。
ひとつは、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。
酒気帯び運転は、身体に一定程度以上のアルコールを保有した状態で運転した場合に成立するものです。
具体的なアルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、令和元年12月現在,①血液1mlにつき0.3mgまたは②呼気1ℓにつき0.15mgです。
実務においては、②の基準を通常利用します。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(同法117条の2の2の3号)。
もうひとつは、「酒酔い運転」と呼ばれるものです。
酒酔い運転は、「酒に酔つた状態」、すなわち「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合に成立します。
酒酔い運転に該当するかどうかは、飲酒運転を検挙した警察官などが視認することで確認する場合が多く、呼気検査の数値が大きいかどうかだけで判断されるものではありません。
たとえば、道路の白線の上を真っすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などの事情が考慮されることとなります。
警察によりこういった判定がなされた結果、酒酔い運転と判断された場合、たとえ呼気検査の結果が低かったとしても安心することはできないので、注意が必要です。
罰則は、酒気帯び運転よりも重い、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています(117条の2の1号)。
【執行猶予を獲得するには】
飲酒運転が発覚した場合、初犯(これまで前科がなかった人)であれば、呼気検査の結果がそれほど重いものでなければ、略式命令(法廷ではなく書面で裁判を行う簡易な手続)による罰金刑で終わる可能性があり、裁判所に出頭することなく、簡便に事件が終了する可能性も見込めます。
ところが、上記事例のXさんのように2回目の飲酒運転となると呼気検査の結果が高い数値でなかったとしても、反省を促すなどの目的で、検察官が裁判を請求する可能性が出てきます。
そうなってしまった場合、刑務所への収容を回避するために、公判廷で罰金刑を求めるかあるいは、懲役刑を受けるとしても、執行猶予を目指していくこととなります。
執行猶予付きの判決とは、被告人に対し、懲役刑を課しながら、一定期間社会内で更生のチャンスを与え、その期間被告人が何らかの犯罪行為を犯すことなく期間が経過した場合には、懲役刑を免除するという判決であり、懲役刑の判決を受けたとしても、刑務所に行かず引き続き社会内で生活を行うことができる判決です。
裁判官が、懲役刑執行猶予を付するかどうかは、アルコール濃度ももちろんですが、アルコールを摂取するに至った経緯や飲酒運転に至った経緯、事件後の被告人の反省の程度、更生に向けた被告人の動きなどの様々な事情を考慮して決めるものです。
今回のXさんは2度目の飲酒運転であり、裁判官に対し、単に「もう飲酒運転をしません」と話したところで説得力に欠ける部分があることは否定できません。
そうした状況下で執行猶予の可能性を高めるのであれば、今回の件を真摯に受け止めていること、更生の余地があることをよりしっかりとアピールする必要があるでしょう。
執行猶予を目指すなら、まずは弁護士に相談するのが賢明と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して尽力します。
飲酒運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、示談の締結をはじめとする的確な弁護活動を行います。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、交際相手から交際の解消を言い渡されたことに大きなショックを受け、千葉県千葉市花見川区の居酒屋に酒を飲みに行きました。
そこで大量に飲酒したAさんは、千鳥足で近くに停めていた自身の自動車に乗り込み、自宅へ帰ろうと周辺の道路を走行しました。
その際、道中にあったVさん宅のコンクリート壁に車体を擦らせてしまったうえ、その様子を千葉北警察署の警察官に目撃されました。
警察官は、Aさんが明らかに酒に酔った状態であったことから、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転は文字どおり酒を飲んで運転する行為を指し、その危険性と刑罰の存在は公共の場所に貼られたポスターなどでたびたび目にするところです。
ですが、飲酒運転が酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられ、道路交通法上異なる罰則が定められていることは意外と知られていないかと思います。
まず、酒気帯び運転は、身体に一定以上のアルコールを保有した状態での飲酒運転です。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血中であれば0.3mg/mL、呼気中であれば0.15mg/Lです。
実務上よく目にするのは呼気検査なので、0.15mgの方を覚えておくとよいかもしれません。
他方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での飲酒運転です。
酒気帯び運転のように客観的な基準があるわけではなく、その判断は酒酔い運転の嫌疑を抱いた警察官の判断によります。
具体的な判断に当たっては、白線の上をまっすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などが見られることになるでしょう。
それぞれの罰則を見てみると、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転が5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
これらは決して軽いものではなく、もし繰り返せば懲役の実刑となる可能性も否定できません。
たとえ事故を起こさずとも、飲酒運転自体重大な行為であることは認識しておくべきでしょう。
【逮捕の種類】
刑事事件においては、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に、捜査機関が逮捕を行うことがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
まず、通常逮捕とは、裁判官から逮捕状の発付を受けて行う逮捕です。
裁判官は逮捕という身体拘束の当否を判断する役割を持ちますが、実務上捜査機関による逮捕状の請求が拒否されることは多くありません。
被疑者の自宅あるいは取調中の警察署で逮捕状を見せて逮捕するのが一般的ですが、被疑事実および逮捕状が出ている旨告げて逮捕状なしに逮捕することもあります。
次に、現行犯逮捕とは、犯行の最中かその直後の被疑者に対し、逮捕状の発付を受けることなく行う逮捕です。
誤認逮捕のおそれがなく、なおかつ被疑者の身柄確保の要請が強いことから、現行犯についてのみ例外的に逮捕状なくして逮捕できるようになっています。
現行犯であれば比較的軽微な事件でも逮捕される傾向にありますが、そうしたケースでは逮捕後2日程度で釈放されることも少なからずあります。
最後に、緊急逮捕とは、一定以上の重大な罪を犯した者につき、罪を犯した疑いが十分ある場合に行われる逮捕です。
犯罪の重大性と嫌疑の程度の要件が通常の逮捕より厳格になっており、事後的な逮捕状の取得を要件に逮捕状なくして行われます。
以上のとおり、逮捕には上記3種類が存在し、それぞれにつき法律上様々な制限が存在しています。
弁護士の力を借りれば、逮捕の違法性を突いて事件をよい良い方向へと導ける可能性が出てくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、その能力をいかんなく発揮して依頼者様の利益を図ります。
ご家族などが飲酒運転をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
過失運転致傷罪で執行猶予
過失運転致傷罪で執行猶予
Aさんは、千葉県長生郡睦沢町にて自動車を運転していた際、Vさん(30歳)と接触する事故を起こしました。
事故の現場は交差点であり、Vさんが横断歩道を渡ろうとしていたのに気づかずAさんが右折したのが事故の原因でした。
これにより、Vさんは全治1か月の怪我を負い、茂原警察署は過失運転致傷罪の疑いで捜査を開始しました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、仮に裁判になっても執行猶予となる可能性があると言いました。
(フィクションです。)
【過失運転致傷罪について】
刑法は、不注意による他人への傷害を過失傷害罪として罰することとしています。
本来なら刑罰を科すに値するのは故意犯であり、過失犯という類型を設けるのは例外的な場合にのみ許されると考えられています。
そのため、過失傷害罪の罰則は30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)と軽くなっています。
ところが、自動車が普及するにつれてその危険性が認知されるようになったことで、自動車による過失傷害は重く罰すべきではないかと考えられるようになりました。
そこで、刑法改正により自動車運転過失致傷罪という特別な規定が置かれ、現在ではそれが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に組み込まれるに至っています。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すると定められています。
ただし、傷害の程度が軽ければ、情状により刑が免除される余地があります。
実際にどの程度の刑が科されるかは、怪我の程度、不注意の内容、被害弁償の有無などにより変わってきます。
不起訴になることもあれば裁判で懲役刑が科されることもあるため、結果については個々の事案により様々です。
ちなみに、特定の状態(たとえば飲酒運転や大幅なスピード違反など)で人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪となります。
その法定刑は1年以上の懲役であり、相当長期の懲役刑が言い渡される可能性も決して否定できません。
【執行猶予の概要】
過失傷害罪と比較すると、過失運転致傷罪の法定刑が重いことは否定できません。
ですが、そうはいっても過失運転致傷罪が故意犯でなく過失犯であることには変わりなく、執行猶予が付く余地は十分あると考えられます。
執行猶予とは、刑の重さが一定の範囲内である場合において、一定期間刑の全部または一部を執行しないでおく制度のことです。
一部執行猶予は再犯防止を図るべく主に薬物事件などで行われるため、以下では全部執行猶予について説明します。
刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す際、情状により付されるものです。
いったん刑の全部の執行を回避できるため、裁判が終わったあと直ちに刑務所に収容されるという事態を防ぐことができます。
それだけでなく、指定された期間執行猶予が取り消されなければ、刑の言い渡しは効力がなくなります。
つまり、猶予された刑を受ける必要がなくなるというわけです。
執行猶予が取り消されるのは、たとえば禁錮以上の実刑が科された場合などが挙げられます。
ご不安であれば、執行猶予となって後のことも含めて弁護士に相談しておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、執行猶予に関するご相談を真摯にお聞きします。
過失運転致傷罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
侵入盗で一部無罪主張
侵入盗で一部無罪主張
千葉県長生郡長生村のアパートに住むAさんは、入居の際に挨拶をした隣室のVさんに好意を抱きました。
AさんはなんとかVさんと親しくなれないか考えましたが、なかなかそのきっかけを掴めずにいました。
ある日、AさんはVさんがアパートの鍵を掛けずに外出する癖があることを知り、不在時を狙えば部屋に忍び込めると考えました。
そこで、Vさんが留守のタイミングを見計らって、Vさんの部屋に無断で立ち入りました。
その数日後、Aさんのもとを茂原警察署の警察官が訪ね、侵入盗を試みたとしてAさんを住居侵入罪および窃盗未遂罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、窃盗未遂罪について無罪の主張をすることにしました。
(フィクションです。)
【侵入盗について】
窃盗罪には、商品数点の万引きや他人口座からの現金の引き出しなど、実に様々なケースが存在します。
侵入盗というのは、そうした窃盗罪に当たるケースのうち、住居や事務所などに侵入して行う窃盗の類型を指します。
ご存知の方も多いかと思いますが、侵入盗に成立するのは、住居等侵入罪および窃盗罪であるのが基本です。
まず、住居等侵入罪は、正当な理由なく他人の住居等に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
注意しなければならないのは、普段自由に立ち入りができる場所だからといって、そのことをのみを理由に住居等侵入罪の成立が否定されるわけではない点です。
たとえば、普段気軽に出入りできる友人の家であっても、あらかじめ窃盗の目的で立ち入れば住居侵入罪に当たる可能性があります。
次に、窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する可能性のある罪です。
窃取による財物の移転をもって既遂となり、既遂に至らずともその危険性が認められれば窃盗未遂罪となる余地があります。
たとえば、金目の物がないかタンスの中身を物色すれば、財物窃取の危険性があったとして窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
【侵入盗事件における一部無罪の主張】
住居侵入罪を犯した際、それと併せて窃盗罪または窃盗未遂罪を疑われることは少なくありません。
これは、物がなくなっていると被害者が感じたり、室内に荒らされた形跡が残ったりしていることがその原因です。
侵入盗は窃盗事件の中でも特に多いことから、住居侵入罪と共に疑われやすいのです。
こうした侵入盗事件のように本来行った以上の犯罪を疑われている場合、一部無罪を主張することが考えられます。
一部無罪は、その名のとおり疑われている犯罪の一部について無罪となることです。
当然ながら、有罪となった際の刑は罪の数が多ければ多いほど重くなるため、一部無罪は量刑を軽くする要素として決して見逃せないものです。
侵入盗も例にもれず、住居等侵入罪および窃盗罪が成立する場合と住居等侵入罪のみが成立する場合とでは全く話が違ってきます。
一部無罪を目指すうえでは、どこまで認めてよく、どこから否認すべきかの線引きをきちんと行う必要があります。
この判断は、各犯罪の成立要件に加えて、個々の行動や供述が犯罪の認定との関係でどういった意味を持つのかという点をも把握することが重要になります。
こうした判断は法律のプロである弁護士が活きる場面なので、一部無罪を主張するならぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、やっていないことを疑われた方のために一部無罪の主張を真摯に検討いたします。
ご家族などが侵入盗の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
« Older Entries Newer Entries »