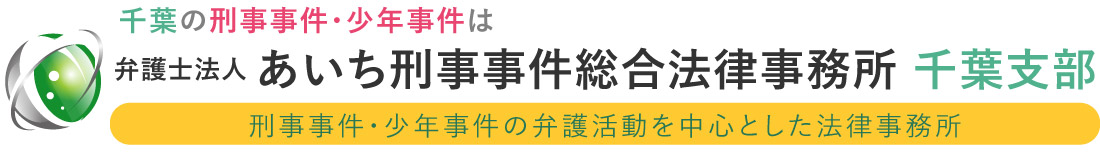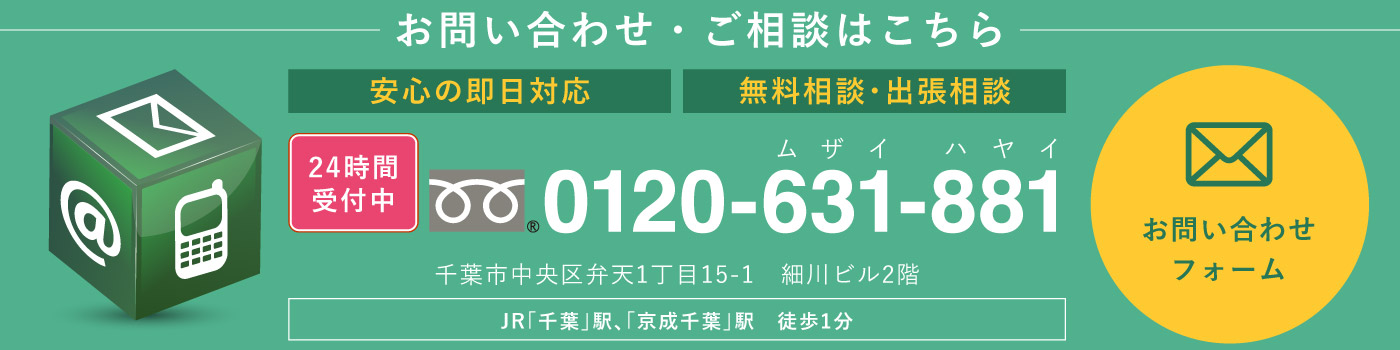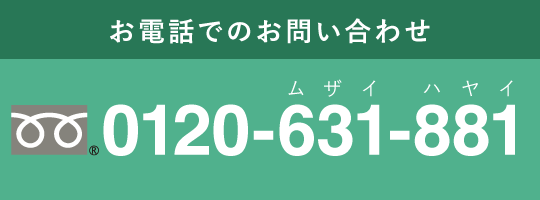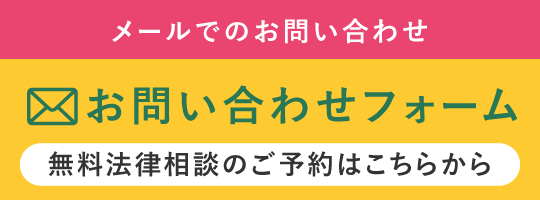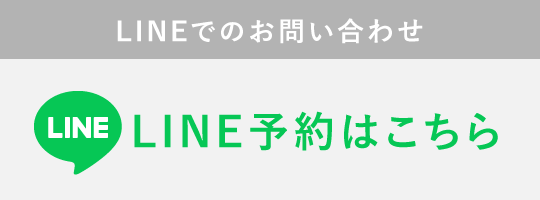※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
大麻の所持で逮捕された,という事件報道は珍しいものではありません。
大麻は覚醒剤と並んで著名な規制薬物ですが,規制される行為や刑罰の重さ,規制を行う法律に違いがあります。
まずはその違いを確認していきましょう。
大麻は,以前,大麻取締法という法律で規制されていましたが,令和6年12月12日からは、大麻の栽培については「大麻草の栽培の規制に関する法律」で,栽培以外の大麻の輸入,輸出,製造,所持,譲り受け,譲り渡し及び使用といった行為については「麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」といいます。)」により規制されることになりました。
これに対して覚醒剤は,従来どおり,覚醒剤取締法で規制されていますが,いずれにしても,法律がそもそも異なることになります。
以前,大麻については,覚醒剤と異なり,使用そのものでは罰せられませんでしたが,今回の改正では,大麻の使用も処罰されることとなりました。
また,今回の改正に伴い,大麻の単純な所持や使用の罰則も,従来の5年以下の拘禁刑から7年以下の拘禁刑とされるなど厳罰化されることとなりました。
麻薬取締法による大麻の規制
上記のように,今回の改正では、大麻を「麻薬」として位置づけることで,麻薬取締法で規制することとなり,使用が処罰された上、全体として厳罰化が進みました。
従来,大麻は,覚醒剤と比較すると,比較的軽い刑罰であったわけですが,厳罰化が進んだことにより,その起訴率も上がってくることも考えられます。
起訴とは
起訴とは,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)を裁判にかけることを決定することです。
つまり,起訴率が高いほど,裁判になりやすくなるのです。
覚醒剤取締法違反の場合,起訴率が75パーセント以上という特徴があります。
この数字は,覚醒剤取締法に違反した場合,相当数の人は裁判にかけられることを意味しています。
従来の大麻取締法違反の場合ですと,起訴率は約45パーセント程度となるため,覚醒剤取締法違反に比べると,裁判にかけられる可能性は比較的低かったといえます。
しかし,今回の改正で、大麻の使用が処罰の対象となり,さらに厳罰化も進んでいることからすると,今後,この起訴率が上がっていくことも十分に考えられるところです。
以上のように,従来の大麻取締法違反では,覚醒剤取締法違反に比べれば起訴率が低かったわけですが、今後,これが上がっていくことも予想されるため,これまで以上に,不起訴の処分を得るための適切な弁護活動が重要となってきます。
執行猶予とは
執行猶予とは,有罪ではあるもののすぐには刑を科さず,一定の期間罪を犯さずに過ごせば,裁判所に言い渡された刑罰を受けなくて済む制度のことを言います。
つまり,拘禁刑を言い渡されても,執行猶予の場合は刑務所に収容されずに済むのです。
それゆえ,執行猶予獲得を目指した弁護活動にも実効性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件専門の弁護士事務所として培ったノウハウを活かし,早期の釈放に向けた弁護活動を行います。