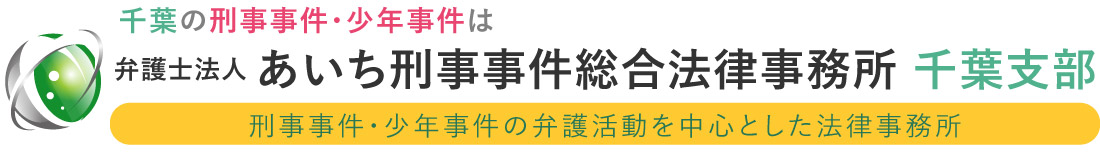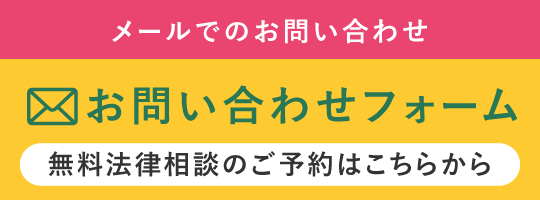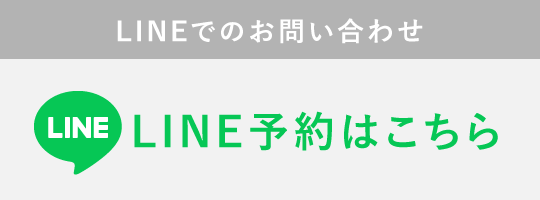少年事件は新聞,テレビ等の事件報道で大きく話題になることがあります。
少年法の改正に対する議論を耳にされた方も多いと思います。
少年事件と言うと,刑事手続の少年版というイメージを持たれる方もいるかもしれませんが,実際には,成人の刑事手続とは異なるところも多いのです。
ここでは,少年法,少年審判を始めとした少年事件について見ていきましょう。
少年法が適用される少年とは,20歳に満たない者のことを言います(少年法2条1項)。
少年が罪を犯した場合,逮捕されたり,警察官,検察官から取調べを受けたりする点では,成人の場合と手続は同じです。
なお、令和4年4月1日から民法上の「成年」は、18歳からとなりました(民法4条)。しかし、少年法ではこれまでと変わらず、「少年」を20歳に満たない者としており、基本的には以前と変わりません。ただ、18歳以上の少年については、「特定少年」としてその他の少年とは異なる場合があるので注意が必要です。
少年事件の特徴
少年事件の特徴は,検察官の取調べを受けてからです。
成人の場合,検察官は被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)を起訴するか,起訴猶予等の理由で釈放するかを決定します。
検察官は犯罪への関与が証拠上認められても,罪の重さや再犯可能性を考慮して起訴をしないという決定ができます。
これに対して少年事件の場合は,検察官は事件を家庭裁判所に送る必要があるため(少年法42条1項),起訴猶予で処分を免れる選択肢がないのです。
家庭裁判所に送られた少年は,裁判官による面談を受けます。
裁判官の判断によって,少年審判が開始されます。
ここで観護措置という処分が取られると,少年は少年鑑別所に送られます。
鑑別所は刑務所や少年院とは目的を異にしていますが,少年は鑑別所内で過ごすことになります。
観護措置から4週間ほどで審判が行われます。
審判は通常の裁判とは異なり,非公開です。裁判官は観護措置期間に鑑別所や家庭裁判所調査官から少年の起こした事件や成育歴について情報を得ているため,審判は通常1回で終わります。
社会内で生活しながら指導・監督を受ける保護観察,少年院への収容等の処分が下されます。
保護観察の期間や少年院に収容する期間は原則20歳までとされています。ただ,特定少年に対する保護所観察の場合,6か月の保護観察と2年の保護観察という2種類になっています。
観護措置決定から審判までの期間を見てもらえばお分かりいただけると思いますが,少年事件は成人の事件以上に時間との勝負になります。
成人の事件では,裁判官は裁判が始まってから証拠を見ることができますが,少年事件ではあらゆる証拠を審判前に見ることができます。
それゆえ,審判当日には既に裁判官の中でおおよその結論は固まっています。
審判当日になって,弁護士(なお,少年事件でつく弁護士を付添人と呼びます。)が頑張ってみても,結論に影響を与えるのは困難です。
また,少年事件では要保護性という観点が非常に重視されます。
要保護性とは
要保護性とは,少年が再非行に及ぶ可能性のことを言います。
成人の場合も再犯可能性は考慮事情になりますが,量刑を決めるうえで最も重要なのは行為です。
つまり,犯罪行為の動機,態様,結果が極めて重要な考慮事情になります。
具体的に言うと,被害が甚大であったり,悪質性の強い行為であったりするほど,罪は重くなります。
これに対して,少年事件では再非行の可能性が重視されるため,やったことが軽微だから軽い処分になるとは言えないのです。
少年法を改正して厳罰化すべきとの主張もありますが,少年事件であることが,かえって成人より処分を重くする場合もありうるのです。
今回ご紹介したのは少年事件のごく一部の特徴ですが,それでも成人事件とは大きな違いがあることはお分かりいただけたと思います。
それゆえ,通常の成人刑事事件と同じように弁護活動を展開しても,思ったような効果が期待できないことがあります。
さらに,特定少年の事件の場合,刑事事件における考慮要素である「犯情の軽重」を考慮して保護処分を決めることになっており,刑事事件的要素と少年事件的要素の双方を考える必要があります。
少年事件の場合,少年事件に精通した弁護士に依頼することが何より重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所として,少年事件の特性を踏まえた,適切な弁護,付添人活動を行います。
少年事件でお悩みの際には,ぜひ一度ご相談してみてください。