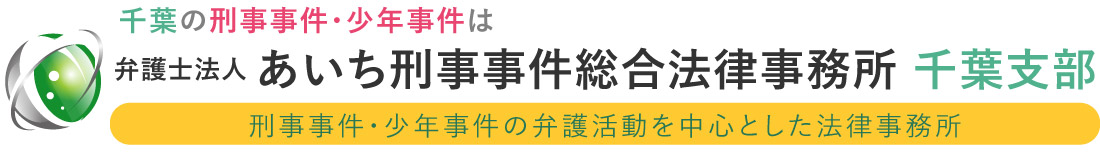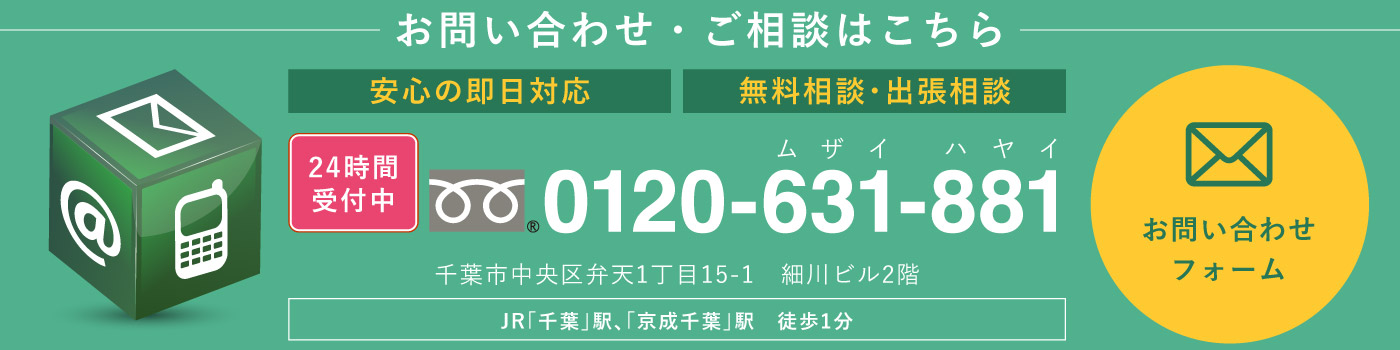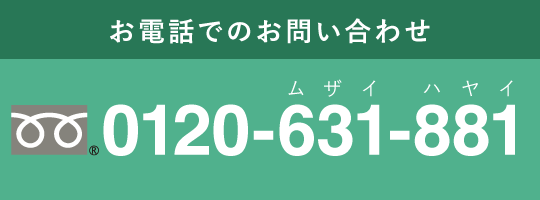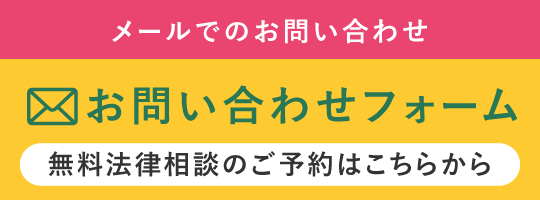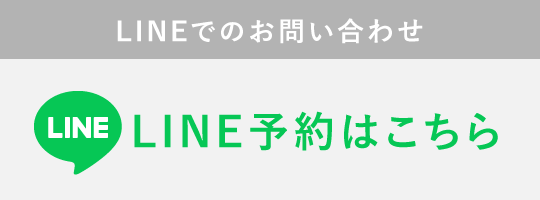※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
最近ではSNSが普及したことにより,これを悪用して児童ポルノを手に入れるというケースも増えています。
児童買春・児童ポルノ法(正式名称,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)が改正されたことで,平成27年から児童ポルノの単純所持や製造も罰せられます。
また、若年者を騙してわいせつな画像を送信させる行為は不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に問われます。
ここでは架空の事例をもとに,児童ポルノ画像を送らせてしまった場合に,どのように刑事手続が進むのかを見ていきましょう。
事例
Aはオンラインゲームを通じて知り合ったBとLINEで連絡を取り合っていた。
やりとりを重ねるうちに,AはBが女子中学生であることを知った。
Aが裸の画像を送ってほしいと頼んだところ,Bから上半身裸の画像が送信されてきた。
どのように刑事手続が進むのか
児童買春・児童ポルノ法違反(児童ポルノ製造)
事例の行為で画像を送信させた場合、児童買春・児童ポルノ法の児童ポルノ製造に該当する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ法での「児童」は18歳未満の者を指します(同法2条1項)。
送られてきた画像が中学生のBの上半身裸の画像ものである場合,Bは「児童」に該当します。また、その内容は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(同法2条3項3号)」という要件を満たすため,児童ポルノに該当します。
画像の送信経緯から,AがBにこのような姿態をとらせて、Bにとらせることで「電磁的記録に係る記録媒体・・・に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した」と考えられるため,Aには児童ポルノの製造罪が成立します(同法7条4項)。
罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
不同意わいせつ
また、Bは女子中学生ですので、16歳未満の者ですから、Bに対してわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります(Bが13歳以上の場合は、AがBの生まれた日より5年以上前の日に生まれた場合のみ成立します)。
わいせつな行為とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものとされています。
AはBに裸の画像を送ってほしいと頼み、Bに上半身裸の画像を撮らせています、これは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえるので、わいせつな行為に該当すると考えられます。
したがって、Aには不同意わいせつ罪が成立します。
罰則は6月以上10年以下の拘禁刑(令和4年の改正刑法が施行された後は拘禁)です。
なお、このような画像を撮影する行為は性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項4号)にも該当しますが、不同意わいせつ罪が成立する場合は不同意わいせつ罪が適用されます。
事件の発覚
児童ポルノの所持や製造、不同意わいせつなどがが発覚する経緯は様々です。
別の犯罪を行って警察から家宅捜索をされて発覚することもあれば,職務質問に伴う所持品検査で発覚することもあります。
また,事例のAのように,画像を送った児童の側で発覚することもあります。
画像を送った児童が後になって後悔し,両親に相談して露見する場合も少なくありません。
児童買春(同法4条)の場合は,相手方児童が後に補導されて,買春だけでなく児童ポルノの製造が発覚するということもあります。
事例のAのように,SNSを介して児童ポルノを受け取った場合,相手方児童のパソコンやスマートフォンにも証拠が残るため,忘れた頃に刑事事件化する場合があります。
児童の年齢や行為者との年齢差によっては、不同意わいせつ罪となる可能性もあります。
客観的な証拠が残りやすい犯罪ですので,児童買春・児童ポルノ法違反や不同意わいせつ罪で起訴される可能性は他の犯罪よりも高いといえます。
もっとも,起訴された場合であっても,児童買春・児童ポルノ法違反に留まるのであれば、罰金刑で終了することも少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件の弁護士事務所として,被害者との示談や適切な取調べ対応の助言を始めとした弁護活動を行います。
不同意わいせつや児童ポルノ製造で罪に問われないかご不安な方は,まずは一度ご相談ください。