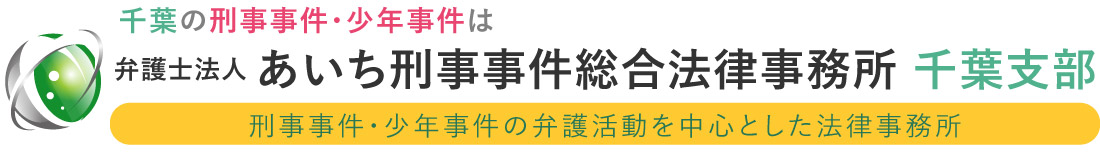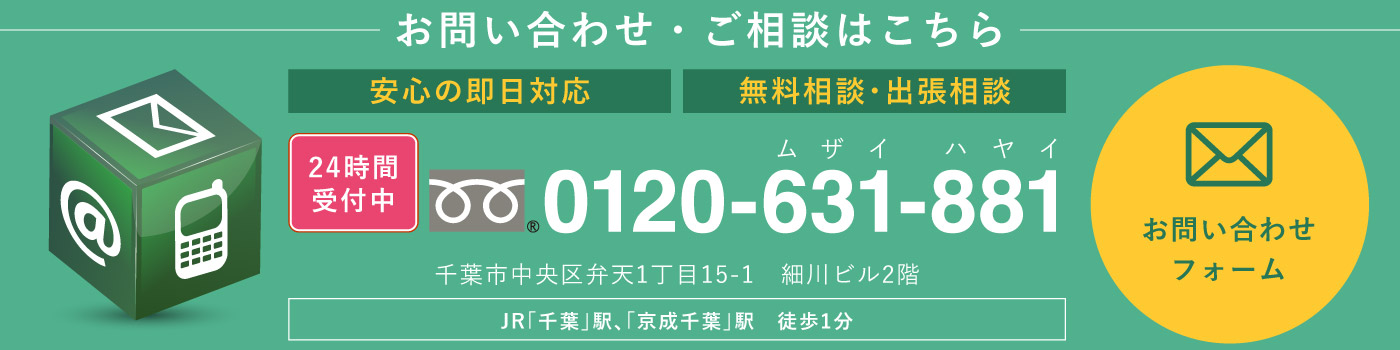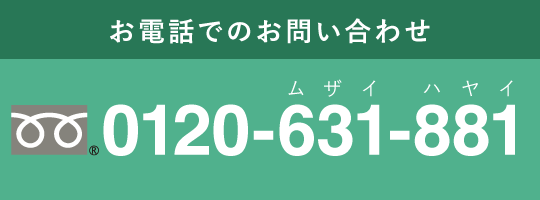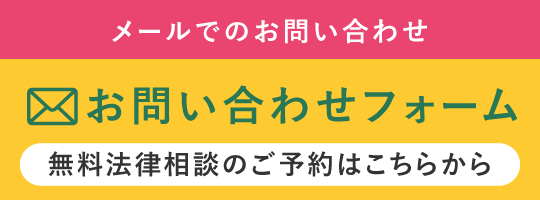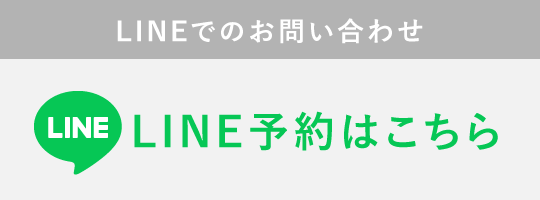※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
執行猶予とは
執行猶予判決とは、裁判所が有罪を言い渡すとともに、一定期間刑の執行を猶予する内容の判決です。例えば,懲役3年,執行猶予5年の有罪判決を受けた場合は,判決から5年間,罪を犯すことがなければ,言い渡された3年の懲役刑に服さなくても済むようになります。
これに対して,執行猶予が付与されない有罪判決を実刑と呼びます。
執行猶予判決の場合、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行が猶予されます。
そのため、判決で拘禁刑が言い渡された場合でも、直ちに刑務所に入らなくても良いことになります。
したがって、有罪判決を受けたとしても、それまでと変わらず通常の生活を送ることができます。
そして、無事に執行猶予期間を経過した場合、裁判所の刑の言い渡しは効力を失います。
その結果、拘禁刑などの刑を執行されることはなくなります。
もっとも、執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、執行猶予が取り消される可能性があります。
再び罪を犯し執行猶予が取り消された場合、執行猶予中の刑と新たに犯した罪の刑を合わせて、刑が執行されることになります。
執行猶予のメリット
- 刑務所に入らないなど、直ちに刑を執行されずに済む
- 会社や学校を休まなくてよく、それまで通りの日常生活を送ることができる
執行猶予を獲得するために主張すること
犯罪に関すること
- 悪質でない
- 危険性が少ない
- 被害が軽い
- 動機に同情の余地がある など
犯人に関すること
- 被害弁償、示談成立済み
- 前科・前歴なし
- 更生の意思、更生のための環境が整っている
- 常習性、再犯可能性がない など
執行猶予が取り消される場合
1 必ず執行猶予が取り消される場合
- 執行猶予期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前5年以内に他の罪について拘禁刑以上の実刑に処せられたことが発覚したとき
2 執行猶予が取り消される可能性がある場合
- 執行猶予期間内に罰金に処せられたとき
- 保護観察付きの執行猶予期間中に保護観察に付された者が、その間守るべき事項を守らず、その情状が重いとき
- 執行猶予言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑の全部執行猶予判決を受けていたことが発覚したとき
注)拘禁刑以上の刑の執行猶予が取り消された場合、他の拘禁刑以上の刑の執行猶予も取り消されます。
再度の執行猶予
執行猶予期間中の犯罪については、一般的に実刑判決になると言われています。
しかし、例外的に再度執行猶予が付される場合があります。
法律上、
- 2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け
- 情状に特に酌量すべきものがある
- 再度の執行猶予期間中における犯行ではない(保護観察の仮解除中を除く)
という3点を満たす場合、執行猶予中に犯した罪について再度執行猶予判決を得ることが可能となります。
執行猶予制度の改正
改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。
1 再度の執行猶予の条件緩和
これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。
改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。
拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。
2 保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予
改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。
改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。
ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。
3 執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続
執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。
これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。執行猶予とは,事件の重大性や被告人(裁判にかけられた人のことを言います。捜査の段階では被疑者と呼ばれます。)の事情等を考慮して,社会内でも更生が期待できる場合に,文字通り刑の執行を猶予することを指します。
実刑の場合
実刑の場合,判決が言い渡されたら直ちに刑務所へ収容されます。
なお,法改正により新たに刑の一部執行猶予という制度ができましたが,一部執行猶予はあくまで実刑です。
判決言い渡しとともに刑務所に収容され,残りが猶予期間のみになった場合,初めて釈放されます。
一部執行猶予は社会復帰準備を社会の中で行えるようにすることに意味があり,薬物犯罪に対して用いられることが多いです。
実刑が回避される場合
次に,実刑が回避される場合をご紹介します。
まずは先ほど説明した執行猶予です。
ただし,執行猶予を付与できない場合が法律で定められているため注意が必要です(刑法25条1項)。
言い渡された刑が3年以下でないと執行猶予は付けられないので,例えば懲役3年6月の場合は執行猶予が付けられません。強盗罪(刑法236条)のように,法律の定めた刑の下限が3年を超えている場合も,特別な減軽事由がなければ実刑は避けられません。
他にも,5年以内に実刑を受けたことがある場合には,執行猶予を付与するための条件が非常に厳しくなります(刑法25条2項)。
そこで,執行猶予の獲得自体も重要なのですが,そもそも起訴(裁判にかけられることを言います。)されないことが重要になってきます。
起訴の権限は検察官が有しているため,証拠に基づいて起訴の必要がないことを説得的に主張する必要があります。
また,名誉棄損罪のような親告罪の場合,被害者と示談をして告訴を取りやめてもらえば,裁判になることはありません。
親告罪ではない犯罪も,警察に発覚していない段階で示談が成立していれば,事実上,以後の刑事手続が進まなくなります。
このように,実刑を回避するには起訴猶予の獲得を第一に目指し,起訴されてしまったら執行猶予を求めて弁護活動を進めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件専門の弁護士事務所として,被害者との示談を始めとして,起訴猶予,執行猶予の獲得を目指します。
刑事事件でお悩みの際は,まずは一度ご相談ください。